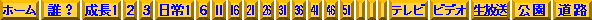ともちゃん
 の日常31
の日常31
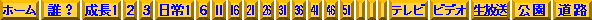
 の日常31
の日常31
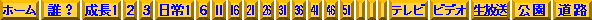
最初にタイトルの一覧があります。タイトルをクリックすると本文が読めます。
「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークをクリックするとそのタイトルに関する写真/動画/連組写真が見られます(「ビデオ」/「スライド」はファイルのダウンロードに1~2分かかります)。
本文の最初にも「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークがありますが、タイトル一覧と同じ写真/動画/連組写真です。

 8日(日)
8日(日)
 28日(土)
28日(土)
「京都府立植物園」
 5日(日)
5日(日)
 26日(日)
26日(日)
「二条城」
 20日(水)
20日(水)
 24日(日)
24日(日)
「赤根天神社」
 25日(月)
25日(月)
「お家で過ごす誕生日」
 5日(金)
5日(金)
 7日(日)
7日(日)
「北陸道を通って余呉湖へ」
 9日(火)
9日(火)
「びわ湖大橋米プラザ」

 ともちゃんは、引越してきた自然豊かな街でゆったりとした生活を楽しんでいます。お父さんが通販で屋上用のバタフライテーブル(折りたたみ式のテーブル)を買ったので、眼下に広がる田園風景を見ながら、家族揃って屋上で朝食(ともちゃんはお粥ペースト)を食べたりもしましたが、このお話はまたの機会に書くことにしましょう。連休の後半も、ともちゃんは「近くの観光地」にお出かけしました。
ともちゃんは、引越してきた自然豊かな街でゆったりとした生活を楽しんでいます。お父さんが通販で屋上用のバタフライテーブル(折りたたみ式のテーブル)を買ったので、眼下に広がる田園風景を見ながら、家族揃って屋上で朝食(ともちゃんはお粥ペースト)を食べたりもしましたが、このお話はまたの機会に書くことにしましょう。連休の後半も、ともちゃんは「近くの観光地」にお出かけしました。
【大山崎山荘】養護学校で「以前遠足で行って良かったよ。」と教えてもらったところです。早速行ってみました。大山崎山荘は天王山(名神高速が片側2車線だった頃は渋滞の名所だった天王山トンネルの上)に建てられた洋酒メーカー創業者の元山荘で、今は系列のビールメーカー保有の美術館になっています。2階の喫茶テラスからの眺めがよくて、三川(桂川、宇治川、木津川)合流点の向うに八幡の山が見えるとのことでした。眺望のよい喫茶室でのミルクの注入は、ともちゃんも大好きです。
山荘前には一般の駐車場はありませんが、車椅子の障害者であれば、事前に電話をしておくと山荘の前まで車で上がって行くことができます。ともちゃんは開館前に到着して、入館までの間に話を聞くと、2階のテラスに上がるのはエレベータではなくて、係の方々が車椅子ごと抱えて階段を上って下さるとのことでした(お母さんが事前に調べたつもりのエレベータは地下の展示室に行くものでした)。歴史的な建物なので、バリアフリーに改造することができないのだそうです。
開館と相前後して次から次へと入館者が詰掛けて、チケット売場には長い列ができました。美術館よりもテラスが目当てのともちゃんは、さっそく係の方にお願いして、2階に運んでもらいました。駐車場の件でもそうですが、障害者には大変親切に対応して下さって、特に構造上の不備を人力でカバーしようという熱意に両親はとても感激しました。
テラスは評判通りの見晴しで、とても気持ちの良い所でした。新緑を近くに遠くに眺めつつ、さわやかな風に吹かれると、お腹も空いてきます。ともちゃんのミルクもおいしかったでしょう。両親もケーキセットを食べた後にプレッツェルも頂きました。再び係の方に抱え降ろしてもらい、館内の美術鑑賞をしました。本館1階の陶芸などを見ていると、釣鐘の上に櫛を付けたような作品の前でともちゃんは「ハハーン」と笑い出しました。これが気に入ったようです。
次にエレベータで新館の地下に降りて、絵画も見ました。円筒状の部屋にぐるりと絵画が展示されています。ともちゃんは他の絵画には反応を示さなかったのに、モネの睡蓮の前に来るとうれしそうに「ニャハハ」と笑いました。気に入ったのかなともう一度回ってきても、やっぱり笑います。ともちゃんは睡蓮もお気に入りのようです。それならと、お土産に睡蓮のポストカードを買いました。
【勝龍寺城公園】明智光秀の娘、細川ガラシャの最期の地として有名なお城が一部再現されて、日本庭園や展示室を設けた公園になっています。駐車場から水掘を挟んで土塀に沿って行くと小ぶりの門があって、覗いてみると段差はなさそうです。その先には立派な高麗門がありますが、手前の門から入ることにしました。サツキの咲くスロープを上がると、庭園の端っこに孔雀の檻があって、びっくりしました。
櫓を備えたこじんまりとした日本庭園を散歩して、ガラシャ像の横のベンチでミルクの注入をしました。明るい5月の日差しの元、日傘を掲げてそよ風に吹かれると、気持ちがリフレッシュしていいものです。時折、プァーンと孔雀の鳴き声が園内に響いて、ともちゃんは笑っていました。訪れる人もそれほど多くはなくて、落着いて園内を眺めながら、注入しました。
市自慢のアメニティ下水道を利用した修景池にはアヒルと鯉が泳いでいます。これを横目で見ながら、管理棟に入ってみました。1階はガラス張りの休憩室になっていますが、飲食は禁止でした。2階の展示室には出土品が並んでいます。勝龍寺はお父さんの会社の近くなので、少し遠回りをして会社の前を通って帰りました。「ここが自転車ではしんどい坂道やねん。」とか、「あの建物の6階で働いてるねんで。」などと教えてもらいました。
 ともちゃんが大阪に住んでいた頃は、京都市内を通るお出かけは道が混んで時間がかかるので、(お父さんから)禁じ手とされていました。けれども、京都府下に引越した今は家から近いので、ともちゃん時間でも京都市内にお出かけできるようになりました。通行解禁となった初めてのお出かけは、京都府立植物園でした。
ともちゃんが大阪に住んでいた頃は、京都市内を通るお出かけは道が混んで時間がかかるので、(お父さんから)禁じ手とされていました。けれども、京都府下に引越した今は家から近いので、ともちゃん時間でも京都市内にお出かけできるようになりました。通行解禁となった初めてのお出かけは、京都府立植物園でした。
行きは国道171号線から西大路通りを北上しました。昨日から張切っていたともちゃんは、今日は少し痰があって昨日ほど絶好調という訳ではないので、車に乗込むとお母さんはともちゃんの背中をトントンして寝かせようとしました。「植物園に着くまでは寝とき。京都市内は道が混んでるから、なかなか着かへんで。」、ともちゃんは最初はボーっとしていましたが、171号線が京都市内に入る頃にはしっかりと覚醒して、辺りをキョロキョロと眺めています。生粋の難波っ子のともちゃんには、京都の町並みが珍しいのでしょうか。
ともちゃんの両親はどちらも京都に縁があります。お母さんは京都市内の出身です。平安京の南端にある羅生門のさらに南で、小、中、高校時代を過ごしました。とはいえ、お母さんは京都の歴史にも名所旧跡にも全く興味がなかったので、「京都人の京都知らず」です。お父さんは学生時代、京都に下宿していました。大学では「京都を歩く会」(略称、京歩会)というサークルに属して、観光名所や隠れた名跡をあちこち訪ね歩いていました。ですから、ともちゃんの京都案内は、もっぱらお父さんの役目です。
西大路通りは渋滞して動かないということはありませんでしたが、車が多い上に信号が多くて、予想した通り時間がかかりました。前を走る京都市バスの行先表示を見て「えっ、快速の市バスなんか、あるんや。」、通過する標識に「嵐電の駅(白梅町)やな。」、「金閣寺の近くやで。」、「船岡山って低い山やで。」と車内から市内観光をしながら行きました。ともちゃんも両親の話を聞いて、窓の外を観察しています。
植物園に着くと、まずは植物園会館2階のレストランでミルクの注入を行いました。ともちゃんが得意とするレストラン一番乗りです。選取りで窓際の席に陣取り、窓の外の大きな木々を眺めながら注入しました。お母さんが窓の下を覗くと、草花の苗や肥料、土を売っています。「ともちゃん、引越ししたら屋上でガーデニングしようと思ってたのに、なかなかそんな暇ないなあ。」
ともちゃんの注入をしながら、両親は園内地図と見所案内を見て、散歩コースを検討しています。バラが見頃ということなので、バラ園から園の東側を散歩することに決まりました。ともちゃんの注入の終了の作業を始めたお母さんは、ともちゃんの後ろの衝立のところで待機している接客係の視線を感じました。お母さんは、誇らしい気持ちで「よく見ておいてね。こうして栄養を摂って楽しく生きている子供もいることを知っておいてね。」と心の中で言いました。
バラ園はバラの種類も多いのですが、一斉に咲いている一種類の花の数が多くて見応えがあります。写真を撮りながら、バラ園から噴水のある沈床花壇へ向かいました。こちらは色々な花が咲き乱れるお花畑です。ともちゃんもご機嫌でケラケラ笑っているかと思うと、撮影のために止まると急にお澄まし顔になったりしています。森の中に入り、北上して北山門の花壇を経てまた森の中を抜け、中央休憩所のある芝生の広場に到着しました。
ここでともちゃんは水分補給です。中央休憩所は一杯だったので、木陰のベンチに座りました。一杯だったのは車椅子の団体さんです。京都府立植物園は大正時代に開園された伝統のある古い施設ですが、13年前に植物園会館や温室を改築してバリアフリーの構造にしたので、車椅子でも心置きなく訪ねることができます。お母さんは、ともちゃんのお出かけ先で車椅子の人たちを見かけると、とてもうれしい気持ちになります。
水分補給を終えて出口に向かうと、温室の前に出ました。ともちゃんが生まれる前に、お母さんは当時2歳のお姉ちゃんと2人で、電車に乗ってこの植物園に来たことがあります。お父さんは来ておらず、休日出勤だったか、体調を崩して家で寝ていたかのどちらかです。「植物園に行ったら、温室があるねん。温室に行こな。」とお母さんはお姉ちゃんにずっと話していたのですが、植物園でお弁当を食べていると、お姉ちゃんがいきなり「温泉なかったな。」と言いました。
よく聞いてみると、どうやら2歳のお姉ちゃんの頭の中では「温室」と「温泉」がゴッチャになっていたようでした。お母さんは「温室の中は暖かくて、暑いところの花も咲いている・・・」と説明したつもりだったのですが、確かに「温泉」の中も暖かいので納得しました。今、目の前にある温室は、当時のお椀を伏せた形の温室とは異なり、この間に改築されたようです。「温室の中は今度来た時に見よな。」とともちゃんに約束して、帰路に着きました。
帰りはカーナビの指示に従って、烏丸通りを下がり(南下し)ました。同志社大学の横を通り、御所の横を通り、予備校生のお姉ちゃんが毎日乗降りする地下鉄の駅を横目に見ながら、ともちゃんはキョロキョロするだけではなく、両親の会話に加わって大きな声でお話しています。ともちゃんもすっかり車中からの京都観光を楽しんでいるようです。東本願寺横から京都駅前に出て、少し東に行って高架でJRの線路を越え、久世橋を渡って171号線に入るコースでした。
 お父さんの京都案内第2弾、「京都に車で行くんやったら、白川通りから北山通りやな。ともちゃん、宝ヶ池に行こか。京都国際会館の庭もあるし、池もあるし、子供の楽園もあるし。」ということで、ともちゃんは宝ヶ池に向っています。今日のコースは九条通りから東大路通りに入り、これを上がり(北上し)ます。
お父さんの京都案内第2弾、「京都に車で行くんやったら、白川通りから北山通りやな。ともちゃん、宝ヶ池に行こか。京都国際会館の庭もあるし、池もあるし、子供の楽園もあるし。」ということで、ともちゃんは宝ヶ池に向っています。今日のコースは九条通りから東大路通りに入り、これを上がり(北上し)ます。
九条通りがJRと京阪電車を高架で越えるところでは、東福寺が見えます。「あっ東福寺が見えてるわ。ともちゃん、東福寺は前に行ったやろ。あそこにほら、屋根が見えてるで。」、ともちゃんは、「ハハーン」と声を出して、両親の話にタイミングよく加わっています。ともちゃんは、元気でしっかり覚醒している時に家族が賑やかに話をしていると、自分もその中に入りたくて声を出します。ともちゃんに声をかけられると、家族の誰もがうれしくなって、ともちゃんに話しかけてしまうのです。
京都は何といっても観光地。道なりに東大路通りに入って北上するだけでも、左右に見所が満載です。八条は今熊野神社、七条は右手に京都女子大学、左手に国立博物館と三十三間堂、五条は坂を上がれば清水寺、四条は八坂神社、丸太町を越えると左右に京都大学が見えてきます。さらに東大路通りを上がり、比叡山や鞍馬まで行く叡山電鉄の路面電車の線路を横切り、叡山電鉄の一乗寺駅の近くまで来ると、お父さんが運転する車は右に逸れました。一乗寺は、宮本武蔵が吉岡一門と決闘したことで有名な一乗寺下り松の一乗寺です。学生時代にお父さんが下宿していたところを見に行こうというのです。
「ここが駅から続いてる商店街で、そこから横にそれるねん。」、細い道に折れます。「ほら、あそこに風呂屋があるやろ。あのお風呂屋さんに行っててんで。」、思わぬタイムスリップに感激するお母さんに、車を少し進めてお父さんが言います。「タイル張りの学生マンションが見えるやろ。あそこや。」、「えっ、あんなええとこに住んでたん。」、「今は学生マンションに建替えられてるけど、昔は染色工場やってんで。その2階に間借りしててん。2階に6部屋あって、6人が下宿してたんや。」、「ともちゃん、お父ちゃんは若い頃ここに住んでてんて。」とともちゃんに話を振られても、ともちゃんにとっては想像できないくらいはるか昔の話です。
ちょっと道草を食ってしまいましたが、再び叡山電鉄を横切り、今度はさらに東の通り、白川通りを上がりました。ともちゃんの家を建ててもらった工務店さんの本店の前を通り、宝ヶ池周辺に到着です。宝ヶ池と言う名の池があって、その一角には国立京都国際会館が建ち、池の反対側は宝ヶ池公園となっています。また、池の500mほど東には、子供の楽園という公園もあります。周囲を一周して駐車場を探し、京都国際会館のイベントホール前の駐車場に車を止めました。
ともちゃんは本館会議場の裏手の日本庭園に向かいました。駐車場からは、地下鉄の連絡路を経て、一度道路に出て、ぐるりと廻って行かなくてはなりません。「庭園から見える国際会館(当時は京都国際会議場という名称だった)は、ウルトラセブンの地球防衛隊の基地として撮影に使用されたことで有名やねんで。」と元「京歩会」(正式には「京都を歩く会」という大学のサークル)のお父さんが教えてくれました。庭園内は砂利道で、車椅子が押しにくくてお父さんは苦労していましたが、ともちゃんは何処吹く風でホホーっとしています。
ミルクの注入はアネックスホールの裏の松の木の下の石垣に腰掛けて行いました。ホールの中から良く見える位置です。「中から他人が見てたら、何をしているんやろと思うやろなあ。」、本館会議室では、全国から薬局関係者が集まる会議が行われていて、「調剤薬局でもドラッグストアでも大のお得意さんのともちゃんに、無関係な会議でもないよなあ。」と言いながら通過ぎたのですが、ホールの方では何か行われていたのでしょうか。ともちゃんはお父さんにウルトラセブンの歌を歌ってもらっていました。これまた、お父さんが今のともちゃんよりも、もっとずっと小さかった頃の昔の昔の歌です。
ミルクの後は池の畔まで散歩してみようとしたのですが、車椅子の座り方が悪かったようで、側湾と股関節脱臼のある右の腰が痛そうです。ゆっくりと抱っこできるところでともちゃんの身体を伸ばしてあげようと、車に戻ってファミリーレストランに行きました。目指すファミレスは、「早い、うまい、安い」をモットーに学生の街京都で生まれ、全国チェーンに発展してきた「餃子の王将」です。学生時代のお父さんも、ファミレスではなく商店街の中のカウンターしかない小さな「王将」一乗寺店に毎週通っていました。
お父さんに抱っこされたともちゃんは、腰を伸ばして水分補給をした後は、散歩疲れでボーっとしていました。けれども、ともちゃんの後に次から次へとやってくるお客さんは、みんな就学前の小さな子供がいる家族連れで、ともちゃんの周りの席全部から子供の気配が感じられる様になると、ともちゃんはハッと覚醒して、オーオーと大きな声を出して、周りの子供達に負けないようにはしゃいでいました。マンゴープリンを頼んでいる子供の声を聞いて、ともちゃんも何か頼んで欲しかったのかもしれません。かわいそうですが、強度の食物アレルギー体質なので、原材料がわからない外食はできません。
そろそろ帰りの時間ですが、まずは「池」、次は「子供の楽園」と近くに駐車場がないか探しに行きました。ともちゃんが元気になったので、また少しでも散歩できればいいかなと思ったからです。しかし、いずれの駐車場も収容台数がとても少なくて、すでに近くの路上まで駐車された車で一杯の状態でした。子供の楽園に至っては、周囲の道路を回ろうと住宅地の狭い道路を入っていくと、さらにどんどん狭くなり、対向車とすれ違うこともできなくなりました。方向転換もままならず、音を上げたお父さんはバックで脱出しました。
「池」も「子供の楽園」もまた今度ということにして、ともちゃん得意の車中観光をしながら帰りましょう。国の天然記念物に指定された生物群落のある深泥池(みどろがいけ)を見た後は、白川通りを南下して、南禅寺界隈から疎水横を通り、動物園や近代美術館を疎水越しに眺め、平安神宮の大きな鳥居を横に見て、東大路通りに入りました。車の中は、お母さんの歓声と、お父さんの解説と、ともちゃんのタイミングのいい突っ込みや笑いでずっと和やかでした。
 ともちゃんの今日のお出かけ先は二条城、京都の有名な観光地、修学旅行や外国人旅行者にも人気のスポットです。京都を知らないともちゃんですから、そういう意味でも見ておきたい二条城ですが、もう一つここはお姉ちゃんの学校の近くでもあるのです。
ともちゃんの今日のお出かけ先は二条城、京都の有名な観光地、修学旅行や外国人旅行者にも人気のスポットです。京都を知らないともちゃんですから、そういう意味でも見ておきたい二条城ですが、もう一つここはお姉ちゃんの学校の近くでもあるのです。
今年、大学受験に失敗したお姉ちゃんは、予備校に通っています。忙しい朝でも、暇を見つけては声をかけてくれるお姉ちゃんが、ともちゃんは大好きです。ある朝、今日は自宅で静養という日に「ほんなら、ともちゃん、おネエの学校について来るか。」と愛想で声をかけてくれました。お母さんに抱っこされてお粥を食べていたともちゃんは、うれしそうに「ハン」と返事をして期待していたにもかかわらず、お姉ちゃんは「バイバイ」と手を振ってそのまま出かけて行ってしまいました。そんなことがあったので、お姉ちゃんの学校を見に行こうというのも、目的の一つです。
車に乗込み、車が動き出すと、ともちゃんはギャハギャハ、アーアーと大きな声を出して、久しぶりのお出かけに大喜びしていました。ですが、ひとしきりはしゃぐとおとなしくなって、ちょっとボーッとして体力温存のモードです。二条城については、事前にお母さんとともちゃんがパソコンで調べて、車椅子での見学について電話でも確認していました。駐車場と入口の場所は、毎日前を通っているお姉ちゃんに様子を聞いています。
駐車場にはすでにたくさんの車が止っていました。お母さんがゲート傍に三角コーンと柵で封鎖された車椅子駐車スペースを見つけ、お父さんが柵を移動して駐車しようとしたところ、どこからか管理人さんがあわててやって来ました。お母さんが大声で「車椅子なんですけど」と説明すると、快く了解してくれました。けれども、ここの車椅子駐車スペースは、タクシーが止ったり、自転車が止められていたりして、障害者には使い難いので、そのあたりの管理をしっかりとお願いしたいところです。
ここまで来て、ともちゃんは日傘を忘れたことに気がつきました。城内を全部を見るのは無理なので、ともちゃんは庭園を中心にお散歩しようとしていましたが、急遽予定を変更しました。二の丸御殿は車椅子でも上がることができると電話で聞いています。国宝の御殿の中を見てみることにしましょう。電話では、「室内用の車椅子に乗換えてもらいます。」とのことでしたが、雑巾でタイヤを拭けばそのまま乗入れても大丈夫でした。
二の丸御殿の入口には車椅子用のスロープも作られていて、荷物を持ったお母さんがボーッと見ている間に、係りの方が雑巾を持ってきてお父さんと一緒にタイヤをきれいに拭いて下さいました。車椅子にも親切に対応して頂いて、ありがたかったです。他の人が履物を脱いで上がっている御殿の中に、ともちゃんは車椅子で入れてもらいました。御殿の中は外に比べて薄暗く、黒光りしている太い柱や床は歴史を感じさます。独特の雰囲気を感じて、ともちゃんは目をしっかりと見開いて神経を集中させた顔つきでキョロキョロしています。
御殿にはいくつも部屋があって、部屋ごとに襖絵が違います。廊下の天井にもきれいな絵が描かれています。ともちゃんと「虎が描いてあるな。こわいなあ。」、「ここはガアガア(水鳥)のお部屋やで。」、「天井も見てみ。きれいやわ。」と話しながら行きました。各部屋の前には音声案内をスタートさせるボタンが備えてあるので、ともちゃんも押してみました。ともちゃんは、重厚な雰囲気に圧倒されたのか、みんな静かに観覧しているのを感じたのか、ギャハギャハはしゃぐこともなく、おとなしく観覧していました。
一箇所だけ、大広間の前で「二重折上げ格天井」を見て、「将軍さん(の座る場所)の上の天井はもう一段凹んでるわ。見てみ。」とお母さんが話しかけた時に、ニャハハと笑って答えていました。大広間は華やかな造りの上に、人形によって将軍が大名を集めて対面している様子が再現されていたので、ともちゃんも賑やかそうに感じたのかもしれません。棟と棟を繋ぐ廊下に出た時は、周りの暗さが変ったので、ともちゃんは緊張してキョロキョロしていました。。
休憩所でミルクの注入をしました。ここは二条城内で唯一飲食が許されている場所です。修学旅行生の団体と外国人観光客で混合っていましたが、広い休憩所で座席は十分確保できました。混雑にも波があるようで、ともちゃんが注入している間にもかなりの人が入替り、混雑も解消されていきました。休憩所の中は、椅子席を取囲むように京都土産の売店があって、ともちゃんは空いて移動しやすくなった店内を見て回りました。そして、二の丸御殿を背景にして新撰組に扮したキティちゃんのタオルと葵の御紋の鈴を買いました。
さて、お腹も一杯になったし、お土産も買ったし、お姉ちゃんの予備校を見たら帰ります。お父さんも、お母さんも、予備校が二条城の北側にあるということだけしか知りません。けれども、「窓が開かへんようになっているけど、窓が開いてたら、二条城が真ん前に見えるのに。」とか「ラストサムライの宣伝でトム・クルーズが来日した時に、トム・クルーズが二条城にも来たんや。そのときは、みんな授業を抜出して、見に行ってんて。」とか、お姉ちゃんが話していたところから推測すると、ごく近くにあるのでしょう。
運よく曇っていますから、お城の中を北の端まで行ってみることにしました。城内の北側の塀の向うに予備校のビルの頭が覗いているかもしれないとお母さんは期待しています。砂利道を車椅子で行くと、小刻みに揺れるのがともちゃんには愉快らしく、御殿の中とは違ってギャハギャハ大きな口を開けて笑っていました。お城の北の方には緑の園や清流園といった庭園があります。残念ながら、予備校の建物らしき物は見当りませんでした。
そういう意味では当て外れでしたが、ともちゃんの散歩コースとしては楽しめました。曇っていた空から太陽が照りだしたので急いで車に戻り、帰りの道すがら車の中から偵察することにします。お城の北側の道を隔てて、幼稚園の隣に探し物はありました。「ともちゃん、これがおネエが毎日通っている学校やで。見てみ。」というお母さんの声に、抱っこされたともちゃんは、首を回してしばらく見ていました。やがてフワァーと大きなあくびをして、「なーんや。ビルみたいで、面白くなさそうな学校やな。私の学校のほうがよっぽど楽しいわ。お散歩もしたし、私は眠いわ。」と言いたげな顔をしていました。
学校大好きのともちゃんは、無理しない程度になるべくたくさん登校していますが、本当は訪問学級籍の生徒です。ともちゃんの養護学校では、学校に登校できない子供のために訪問教育が実施されています。「訪問学級」というと、通常は先生に家に来て頂いて、特別に決められたスクーリングの日にだけ登校するという風に思われますが、登校できる日はいつでも登校してもよいという説明を受けました。
「最初は訪問生として在籍していたけれど、ほとんど毎日登校できたので、翌年には通級生に変えた生徒もいますよ。」と聞き、それならともちゃんにちょうどいいかもしれないと両親は思いました。外出好きのともちゃんですが、冬になると体調が安定しないので、無理をさせずに家で冬籠りをしています。今までは、その間何度も先生から「学校からのプリントを持って、ともちゃんの様子を見に行ってもいいですか。」と声をかけて頂いていました。
ありがたいと思いながらも、実際のところは授業が終ってからの夕方の時間ではともちゃんの予定にゆとりがなくて、いつもお断りしていました。訪問籍にしておくと、冬籠りの間もともちゃんにとって都合のよい午前中に先生に来てもらうことができます。そんな訳で、ともちゃんは訪問学級籍にしたのですが、クラスにもちゃんと所属しています。高等部1組、略してK1組(ちょっと強そう)です。
ともちゃんの養護学校では、小、中、高ともに学年別ではなく、障害別にクラス編成がなされています。クラスの数字の若い方が重症心身障害児のクラスです。通常の授業はクラス単位で行いますが、もっと大きな「グループ」という集団と、「チーム」という集団での授業もあります。「グループ」は障害の種類や程度が同じようなクラスが一緒になったものです。一方「チーム」の方は障害の種類や程度を混合した集団で、高等部のクラスを3つに分けたものです。
ともちゃんのグループは重症心身障害児のクラスK1組からK3組までが集った1グループです。他に自閉のグループ、比較的軽度な知的障害のグループなどがあるそうです。毎週、木曜日にはグループ単位で授業をするほか、遠足や宿泊学習もグループ毎にそれぞれの障害の状態に応じて行われています。
ともちゃんのK1組は青チームに属しています。毎週金曜日にはチームでの活動があります。チーム活動では、軽度の知的障害の生徒が司会を担当したり、軽度の子と重度の子がペアを組んだりして、生徒の自主的な活動や交流ができるように構成されています。2学期になると、この高等部のチーム編成に小学部、中学部のクラスが合流して、チーム対抗で運動会が行われるそうです。
ともちゃんは、この1学期の間に、クラスの授業も、グループの授業も、チーム活動もすべて経験しました。それだけではありません。泊りこそしていませんが、学校で行われた宿泊学習の翌日の記念品作りにも、PTAのバザーにも参加しました。もちろん、たくさん訪問にも来て頂きました。お母さんは、この季節なら週2回ぐらい登校できるだろうと思っていたのですが、なかなかそうもいかず、訪問学級にしておいたことを、つくづく良かったと思っています。
ともちゃんの1学期の授業出席日数(訪問学級も含む)は22日でした。訪問学級生なので、授業日数(出席すべき日数)も22日。ともちゃんが授業を受けたい日(授業を受けられる状態にある日)がすなわち出席すべき日になるのです。少しだけともちゃんの様子を振返ってみましょう。
クラスの授業でイチゴの学習に参加しました。実際のイチゴに触って、においをかいで、イチゴの歌を歌って、蝶々や蛇やカエルなどいろんな動物がイチゴを食べに来るお話を聞いて、最後はイチゴジュースを作って飲むという、イチゴづくしの楽しい授業です。その中で、ともちゃんもお母さんもびっくりしたのは、寄宿舎の庭にテントを張って、その中でイチゴの授業が行われたことです。
「イチゴを摘みに行きましょう。」と教室で歌ってから、教室を出て、広い校内を回ります。アヒルの池を見て、竹薮の横を過ぎて、グラウンドと学校の畑の間を通り、寄宿舎の裏に到着するのですから、本当にイチゴ摘みに行ってきたような気分になります。おまけにテントの中でお話を聞いて、ジュースを作るので、キャンプに出かけているようでした。
開校当初から狭い敷地が問題になっていて、3階建ての校舎や体育館屋上のプールが当り前だった市街地の養護学校から転校してきたともちゃんにとっては、カルチャーショックで感激でした。ともちゃんはイチゴをちょっとなめてみたり、イチゴジュースも少し飲みました。イチゴの歌やお話も大好きです。訪問学級でも、何度もイチゴの歌やお話を聞かせてもらったのですが、特に動物たちがチューチューチューやムシャムシャムシャとイチゴを食べるところなど、ニコニコ笑顔がこぼれていました。
大きな集団の授業では友達も賑やかで、ともちゃんも気配を感じて一段とダイナミックに笑っていました。「グループ」ではカエルを題材にした学習(歌や朗読、作り物のおたまじゃくしをつかんでバケツに入れるゲームなど)でした。先生に抱っこしてもらって、みんなに紹介してもらいました。最初は少しおとなしくしていたのですが、だんだん場の雰囲気に慣れてくるに従って、うれしそうな笑顔になって、そのうちギャハハハと大声で笑っていました。
「チーム」では、青チームのマークや歌を決める会議に参加した後、スイカのボールでの玉入れゲームを見ながら、みんなのいる場所でミルクの注入を行いました。もちろん、ここでも紹介してもらいました。色々な障害の友達が集まると、さらに賑やかで、会場は華やいでいます。ゲームが盛上がってみんなの歓声を聞くと、ともちゃんも興奮して大きな口を開け、大喜びでした。でも、これは刺激が強すぎたようで、家に帰ってからも興奮が抜けず、翌日けいれん発作が出てしまいました。楽しすぎると興奮するというのが、ともちゃんの泣き所です。
訪問学級では、よく笑うともちゃんだけではなく、ともちゃんの細かい表情の変化や、タイミングの良い反応なども、先生に知って頂きました。毎週水曜日には、訓練部の先生が一緒に来て下さって、家でリハビリの訓練をしてもらえるというのも、訪問学級の大きな魅力となっています。今日の終業式は訪問学級で行いました。訓練もして頂き、夏休みの予定について話しました。2学期にはたくさん夏休みのお話ができるように元気で過ごして、たくさんお出かけしようね。
 このところ、ちょっと痰が多くなっていて、遠出するのは心配なともちゃんなので、今日は新しいお家の近くを探検することにしました。日頃の生活の中で、「あれって、どうなってるんや。」と家族で話題になっていて、調べてみたい場所が2ヶ所あります。車椅子で養護学校の方向に出かけてみます。
このところ、ちょっと痰が多くなっていて、遠出するのは心配なともちゃんなので、今日は新しいお家の近くを探検することにしました。日頃の生活の中で、「あれって、どうなってるんや。」と家族で話題になっていて、調べてみたい場所が2ヶ所あります。車椅子で養護学校の方向に出かけてみます。
一つ目の謎は、家の屋上から養護学校方面を望んだ時に、こんもりと茂って見える森がどこかということです。養護学校に行く途中にあかね幼稚園という幼稚園があるのですが、お父さんは「この幼稚園の裏に赤根神社という神社があるねんで。」と言います。屋上から見える森は赤根神社だと言うのです。通学の時、タクシーで幼稚園の前を通っているともちゃんとお母さんですが、「幼稚園の裏に神社があるなんて、そんなはずないわ。」。それなら、本当にあるのか、どこにあるのか、どんな神社なのか、行ってみることになりました。
もう一つの謎は、家の近くを東西から南北へと直角に折れ曲って続く大通りの端っこがどうなっているかです。養護学校に行く時は、東西の大通りに出て、南北の大通りへ道なりに曲って、ガソリンスタンドの角のところで左折して大通りを離れ、例の幼稚園の前を通るというコースを辿ります。この大通りはガソリンスタンドの次の交差点で、急に細い路地になってしまうということです。本当にそうなっているのか、確かめに行きましょう。
学校の先生や障害者用の装具屋さんなど、ともちゃんを訪ねてくれる人はたくさんいたのですが、自分がお出かけするのは久しぶりなので、ともちゃんはうれしくて仕方ありません。車椅子に乗っただけでも自然と笑顔が溢れてきて、大きな口を開けて、ギャハギャハと声を出して大笑いしています。ご機嫌なともちゃんを乗せた車椅子を押して、お父さんは乙訓寺に行った時に通った坂道を登ります。
幸い曇り空なので、お散歩にもぴったりです。途中で乙訓寺とは反対の方向に曲って、さらに坂道を登ります。この辺りは、坂道に沿って左手には大きなお屋敷が続いています。右手は、畑を挟んで小ぶりなたくさんの家が新築中です。「あの家の壁も変った目立つ色やな。」、「ほんまや、あの家、チョコレートケーキみたいやな。」、両親は家を建ててから、よその家の壁の色も気になります。
道がT字路に突当りました。タクシーでともちゃんが通る道より、一筋手前の細い道です。赤根神社(正確には赤根天神社でした)は確かにありました。もう、左斜め前に古い鳥居とその後ろに茂る森が見えてます。見るからに樹齢が古そうな大きな木もあります。鳥居をくぐると四方から蝉の声に包まれました。砂利道を通って本殿にお参りしました。赤根天神社は小さな無人の神社ですが、本殿は市の文化財に指定されている由緒正しい神社でした。
天神池の横を通って再び大通りに戻ったともちゃんは、今度はこの大通りをまっすぐ北に向います。次の信号のところで、大通りは大通りではなくなって、狭い住宅街の道路になってしまっていました。証拠の写真を撮って、帰ります。ガソリンスタンドの交差点を養護学校とは反対方向に向かい、来た時とは違う道を通って帰ることにしました。
一見、料理屋さんのような建物に老舗のおかきやさんの看板が上がっていました。丹波黒豆を使ったおいしいおかきで有名なところで、このおかきはお祖母ちゃんから時々お土産にもらいます。「こんな近所に本店があったんや。入ってみよ。」、ショーウインドウがあるわけでも、入口が開いているわけでもないので、引き戸を開けて中に入るのは、ちょっと勇気が要りました。
「入ってみて、贈答用の高い商品しかなかったら、どうしよう。」、「ほんじゃあ、黙って出て来よう。」、入ってみると、広い土間のような店内にはお客さんが一杯で、カウンターになっている承り所に何人も並んでいます。どうやら、お中元を贈りに来ているようです。カウンターの横には、お祖母ちゃんにもらう袋詰めのおかきも並べてあって、一安心。お母さんは黒豆おかきと山椒のあられを買いました。
広い通りから、住宅地の中の狭い道に入って、坂道を下りました。お母さんもともちゃんもこの辺りは来たことがなくて、どの辺なのか全く見当がつきません。方向的には、家のほうに向かっているはずです。坂道を下り終えると、住宅地の中、中央に白線を引いた道路に出ました。「この道は郵便局の前の道やな。」、お父さんの道相(みちそう)判断(道の雰囲気でどんな道かを当てる)です。
どんどん進むと見慣れた風景になってきました。やはり家の近くの郵便局の前を通る道路でした。おかきやさんは、ともちゃんの家の前の田んぼの向こうの住宅地にあって、田んぼの周りにある住宅地の道を通って帰ってきたのでした。1時間に満たないお散歩でしたが、新しい発見がたくさんありました。
いつもなら、リビングに連れて来られてお着替え中のともちゃんは、まだ余裕がなく笑顔になることは少ないのですが、今日はお母さんがカードを読んでくれると、顔がほころんできました。財布を見せてもらって、また笑顔です。「ここにおこづかい入れて、お買物したらどうや。子供やからあんまりたくさん入れんと、まあ500円くらい入れといて、200円くらいのもん買ったら、楽しいで。」と、お父さんとお話ししました。
お姉ちゃんが起きてきて、いっそう賑やかになりました。今日はたまたまお姉ちゃんの夏期講習はありません。「ともちゃん、オヤジには今年も永久不滅ポイント(どこかお出かけやお買物に行った時に高い物を買ってもよいという権利で、1回限りながら使用期限はなし)をもらったんやろ。お母さんには何もらうんや。」、「お母ちゃんも何か、今度買ってきてあげるやんか。」と、お母さんも負けずに答えたので、思いがけなく今年はプレゼントが多くなりそうです(例年は両親から1つ)。
ともちゃんは食物アレルギーがあるので、ケーキ類は全く食べられません。その代り、生クリームをホイップしてもらって、食べる予定にしています。これには経緯があります。屋上で家族みんなで昼食をとった時に、お母さんとお姉ちゃんがソフトクリームを食べているのをともちゃんは恨めしそうに眺めていました。バニラ系のアイスクリームは卵黄が入っていることが多いので、ともちゃんは食べられません。
「アレルギーがなかったら、どろっとしていて甘いソフトクリームはともちゃんでも食べられるのになあ。」、「けど、ともちゃんは冷たいの苦手やで。」、5月に卵黄などのアレルゲンが入っていないイチゴシャーベットを食べた時のともちゃんは、「冷たい。」と言わんばかりに顔をしかめていました。「前に、生クリームをホイップして、ちょっとだけ食べたことがあったやん。乳脂肪100%のホイップやったら、ソフトクリームみたいな味がするやん。あれ、誕生日にみんなで食べよか。」
ともちゃんは、ホイップしたクリームをしっかりと盛ってもらい(80ccくらいでしょうか)、昼食に添えてもらいました。前菜に食べてみました。口溶けがいいので、咳込むことなくともちゃんはアムアムと口を動かして、でも不思議そうな顔をしてどんどん食べています。「な、冷たくないやろー。ソフトクリームもこんな味やで。オネエも一緒のもん食べてるで。」
お姉ちゃんは自分用に買ったスコーンにホイップクリームをたっぷりつけて誕生日を祝っています。お母さんは、後でお姉ちゃんに少し分けてもらって食べました。お父さんの分は夜まで残しておきましょう。ともちゃんは、お粥ペーストも最近にはない早いペースで食べました。終業式に一度読んでもらった先生方からの誕生日カードをもう一度読んでもらって、誕生会は終わりました。
思えば、去年の誕生日には兵庫県の南光町の一面のひまわり畑に行きました。梅雨も明けたので、本来ならともちゃんのお出かけシーズン真っ盛りのはずなのですが、ともちゃんの体調は絶好調ではありません。引越しした新しい家での、ともちゃんに合った冷房の入れ方を未だに試行錯誤していて、暑すぎると夜眠りが浅くなるし、冷えすぎると鼻がフガフガしたり、痰が多くなったりして、うまくいきません。
寝室の広さ、エアコンの位置や向き、パワーの違い、窓の開け方などが、気温の変化にデリケートなともちゃんには微妙に影響するので、早く最適は方法を見つけなければならないと、お母さんは日夜励んでいます。体調が絶好調ではないけれど、静養するほどでもない休日は、屋上で食事をしたり、家の近くのまだ知らない所をお散歩したりと、無理をせず楽しんでいます。ともちゃんにも、家族にも、楽しいことは遠くにばかりあるわけではありません。家のごく近所にも、屋上にも、おうちの中にも、たくさん隠れています。青い鳥のように。
ともちゃんは、ミルクや水分の注入時間、(長時間の外出は疲れるので)帰宅時間などで制約されるので団体でのお出かけはできませんが、地域の小学校や公民館で行われる行事には参加します。賑やかなことが大好きなともちゃんが喜ぶというのが第一の理由ですが、この地域にともちゃんという重症心身障害児が住んでいることをたくさんの人に知ってもらいたいと、お母さんが思っているからでもあります。
8月1日は地域の小学校で行うプール活動の日でした。プール活動はN市在住の障害児が一同に集うのではなく、主に中学校区で分けた大きな3つのブロックに分かれて行われます。ともちゃんの属するブロックは、今年は幸運なことにともちゃんの家の前の小学校で行われました。普通の25mプールにみんなで入るので、ともちゃんはプールに入ることはできませんが、その前に体育館に集って開会式があり、歌を歌って自己紹介をするところまでは参加できます。
家の前の小学校なので、ほんの少しの参加でもわざわざ出かけて来たのにというような気持ちになることもなく、近所の散歩のつもりで参加できます。また、日頃から小学校の体育館の横を通っているし、歓声も聞こえているので、小学校の中をちょっと覗いてみたい気持ちもあります。養護学校の先生とお母さんと一緒に出かけました。体育館に入ると、ともちゃんはキョロキョロと不安げに辺りを見回しています。「先生と一緒に出かけたのに、ここは私の学校と違うで。」と思っていたのかもしれません。
参加者は4つのグループに分かれて集っていて、ともちゃんはDグループでした。最初は落着かなかったともちゃんも、開会式が始り、みんなで歌を歌う頃になると笑顔が見られるようになりました。グループ内で輪になって自己紹介を行う時も、人懐っこい笑顔を浮かべていました。Dグループは、ともちゃんを含めて養護学校生3名、中学生2名、小学生2名です。この中にはボランティアの健常児も入っていますから、きっと中学生はボランティアなのでしょう。
ともちゃんは、この近くに引越してきたことを先生に自己紹介として話してもらいました。その後、プールに入る他の子供たちは、水から上がった時にお互いの存在を確認しあう相手を決めたりしていました。小学1年生の達者なおしゃべりを聞いて、ともちゃんはギャハハと大笑いしていました。ともちゃんは、この雰囲気にすっかり馴染みましたが、みんなは着替えに行ってしまいました。ともちゃんは、行きとは打って変ってギャハギャハしながら帰って来ました。楽しいお散歩でした。
8月5日、今日は夏の学校の全体会です。N市の夏の学校参加者が中央公民館に一同に集って、パネルシアターや和太鼓の演奏、音楽紙芝居を鑑賞します。ここ数日、ともちゃんは朝に5秒から30秒くらい首を右に曲げて体を硬く硬直させるけいれん発作を何度も起していて、朝食を終える時間が遅くなって心配していました。でも、今朝は予備校が休みのお姉ちゃんに励まされて、しっかりと予定通りに朝食を摂り終えました。先生に家に来て頂いて、お母さんと3人でタクシーに乗って公民館へ出かけました。
公民館では養護学校に勤務されている看護師さんが迎えて下さいました。同じN市に住む同級生のKちゃんも先生と一緒に来ていました。会場は、中央部を円く空けて、それを取り囲むように椅子が並んでいます。車椅子の子供は、お母さんが思っていたほど多くはいませんが、椅子に寄せて車椅子を並べています。ともちゃんが会場に入る時、ちょうど揃いの浴衣を着た女性達がぞろぞろと会場中央部に入って来て、オープニングの盆踊りが始まりました。
盆踊りならともちゃんも浴衣を着てくれば良かったなあとお母さんは話していますが、先生に抱っこされたともちゃんは盆踊りには興味がないのか反応があまりありませんでした。一度目は女性の方々だけで踊って、二度目は皆さんも一緒にということになったのですが、残念ながら会場が狭くて、踊りたくても踊りに参加できない人がたくさんいました。特に車椅子は今の位置から動かすことができず、Kちゃんも断念していました。来年はもっと広い会場で行えたらと思います。
ともちゃんは、抱っこしてもらっているにもかかわらず、筋緊張が強く、周期的に顔をしかめて体をビクっとさせています。車椅子に長く乗っている時も出る症状なのですが、どうやらともちゃん自身がリラックスせず、どこかに力を入れている不安定な状態の時に、ともちゃんの側湾の進んだ身体に歪が生じて痛くなるようです。椅子が狭いので、抱っこしてもらっても不自然な状態なのでしょう。
次の演目に入って、観客の位置が舞台向きに移動(各自、椅子を持って移動)になったので、先生が床に座ってともちゃんを抱っこして下さいました。これで、ともちゃんも腰を伸ばすことができます。ともちゃんは、身体を伸ばしてリラックスできるようになったので、回りのことに注意を向け始めました。舞台ではパネルシアターが演じられています。人形のグリとグラが出てきてグリとグラの歌を歌い出すと、緩んでいたともちゃんの唇の端がじわじわっと持上がり、やがてきゅっと笑顔が現れました。目も好奇心で輝いています。
ともちゃんがもっと大喜びしたのは、その次の和太鼓でした。和太鼓は響くので、近くにいると刺激が強すぎるかもしれないと後ろに移動したのですが、どうしてどうして、トンテケ・テンテケ・テンテケとリズミカルな太鼓の音に、ともちゃんはギャハギャハ笑って大喜びしています。そういえば、以前、大阪の岸和田だんじり会館でお囃子の太鼓を聞いた時も、ともちゃんは大喜びしていました。ともちゃんはお囃子のような軽快な和太鼓の演奏が好きなようです。
ところが、曲目が変り、ドーン・ドーンとお腹の底に響くような演奏方法に変わると、ともちゃんから笑顔が消えて、音が響くたびに目をパシパシさせて、強すぎる刺激に耐えていました。この和太鼓の演奏方法によるともちゃんの反応の違いに、お母さんも、先生も、看護師さんもびっくりでした。お母さんは、ともちゃんにとって(生理的にでも)好きな音、嫌いな音があることがこんなにはっきりと分かって、うれしくなりました。
まだ、「ピアノとフルートによる音楽紙芝居」が残っていますが、ともちゃんのミルクの時間になったので、今回はこれで帰ります。ピアノやフルートにともちゃんがどんな反応を見せてくれたか、ちょっと気になるところですが、それはまたの機会のお楽しみということにします。Kちゃんにさようならをして、看護師さんに見送られて、ともちゃんはタクシーに乗りました。
 カッと照付ける太陽の下、白く輝く高速道路をお父さんの運転する車でお母さんに抱っこされてドライブする、これぞともちゃんの夏休みの醍醐味です。せっかく京都に引越してきたのですから、まずは名神高速からちょっとだけ北陸自動車道を攻略です。北陸自動車道に入って最初のパーキングエリア、神田PAでミルクの注入をして帰ります。
カッと照付ける太陽の下、白く輝く高速道路をお父さんの運転する車でお母さんに抱っこされてドライブする、これぞともちゃんの夏休みの醍醐味です。せっかく京都に引越してきたのですから、まずは名神高速からちょっとだけ北陸自動車道を攻略です。北陸自動車道に入って最初のパーキングエリア、神田PAでミルクの注入をして帰ります。
夏も盛りというのに、未だに各部屋のエアコンをともちゃんにちょうど良い状態に調整できずにいるので、特に夜中暑くて寝苦しかったり、冷えすぎたりしています。そのせいで、痰が多くなったり、朝けいれんの気配が強かったりして、朝食を摂り終えるのに時間がかかっています。ともちゃんの体調は手放しで絶好調とは言えませんが、昼間の体調は良くて機嫌も上々、お出かけしたくてしたくて、お父さんの夏休みを待っていました。そんなともちゃんに、無理のないドライブコースをお父さんが探してくれました。
この方面なら道が混むこともなく、神田PAまで1時間半くらいで行き着くことができるので、少々遅く出発しても昼前にはミルクの注入を終えられます。ともちゃんの家から北陸自動車道に出るには、ずっと名神を走るか、京滋バイパスから名神に入るかという2つのルートがありますが、お父さんが選んだのは京滋バイパス経由です。お母さんは「名神は京都南(インター)が混んでるからなあ。」と納得していましたが、お父さんは「こっち(のルート)の方が100mだけ距離が短いんや。」と言ってはぐらかします。「100mやったら、人間が走っても20秒ぐらいの違いやで。」
名神高速に入ると、以前に彦根まで行った時に通過ぎた地名が次々に見えてきます。彦根に行った時は、ここまでやって来るだけでも随分かかりました。「やっぱり京都からやったら(大阪からより、北陸が)近いなあ。」、米原の分岐点近くでは名古屋までの距離が100kmくらいと表示が出ていて、そのうち名古屋方面にも行けるかなあと話しました。ともちゃんは、ファーと小さな口を細長く開けて何度もあくびをしてウトウトするのですが、どうもぐっすりと寝られないようです。
ともちゃんが寝られないまま、とうとう神田PAに着いてしまいました。ここの売りは伊吹山に向い合った展望台があって、反対側には琵琶湖や竹生島が見えることです。車椅子駐車スペースの裏から展望台に続く坂道が見えていましたが、今日は展望台には登りません。まっすぐに食堂に向かいます。建物に向って左端に食堂があり、その先には屋根の下にベンチを備えた休憩所があります。かつて中国自動車道かどこかで立寄ったパーキングエリアにも、これによく似た構造のところがありました。
まだお昼には間があるので、駐車場も食堂の中も空いていて、席に着いて外を眺めるとホッと落着きます。屋外の休憩所では揃いのユニフォームを着た学生が昼食を摂っていました。大阪の私立大学の名前が描かれたバスが止っていたので、そこのクラブの遠征でしょうか。往路元気がなかったともちゃんですが、注入中に食堂のテレビでやっていた漫才を見て(声を聞いて、雰囲気を感じて)笑っていました。さすが、浪速っ子です。
伊吹山を背景に北陸自動車道初走行の記念写真も撮って、後は高速を一旦降りて車をUターンさせて帰るという段になりました。長浜インターチェンジで降りて長浜の町並みを見て折返すか、木之本インターチェンジまで足を伸ばして余呉湖を見て帰るか、両親で検討しました。長浜よりは遠いけれどきっと余呉湖の方が楽しいだろうとなり、「ともちゃんの笑顔も戻ったことだし。」ということになりました。
北陸自動車道を行くと、両サイドに防音壁がなく、その外側の地面から高速の路面までが近いので、高速道路であることを忘れそうになります。車も少なくて快適ですが、木之本インターまでは思っていたよりも時間がかかりました。地道をしばらく走ってようやく辿り着いた余呉湖はとても美しい所でした。木々の葉っぱの緑も湖面の紺青も、太陽の光でキラキラと白く輝いています。湖の反対側を見るとすぐ近くに針葉樹の山肌が迫っていて、その手前にはJRの駅があります。エアコンの効いた車内から見ると、まるで絵に描いた避暑地の湖のようです。
「でも、(車を降りると)本当はムワッと暑いんやろうなあ。」と言いながら、ともちゃんも一緒に車を降りて、水際まで行ってみました。光の眩しさに惑わされますが、湖面を渡ってきた風は予想外に涼しくて、気持ちのいいものでした。写真を撮って、車の中でともちゃんの水分補給をしていると、思ったよりも時間がかかってしまいました。帰りも来た時と同じだけの時間が必要です。ともちゃんは「もう、帰るだけやから、寝ときや。」と言われていますが、数分ウトウトすると目が開いて、ボーッとしています。急ぐ帰路ですが、暑い季節なのでこまめな水分補給はかかせません。草津PAにも立寄って、さらにもう一度水分補給をしました。
帰り道、硬直発作が頻繁に起こっていたともちゃんは、もう少しでお家というところで、とうとうガクガク発作を起こしてしまいました。眠いのに寝られない、脳がピリピリと興奮するという悪い条件が重なってしまいました。神田PAを出た後、ちょっと頑張り過ぎたと、両親は反省しています。ガクガク発作自体は、ともちゃんの生活では付合っていかなければならないことで、週に1度くらいはあるのですが、できれば外出先で起こることは避けたいものです。今回は大事に至らなくて、何よりでした。
帰宅したのは、午後4時近くになっていました。急いで、遅い昼食を摂ろうとしていると、再びガクガク発作が起こり、けいれん止めの坐薬を使うことになりました。ともちゃんの座右の銘「頑張らない(無理はしない)」を改めて肝に銘じた両親でした。これぞ夏休みというような今日のお出かけは面白かったし、余呉湖もよかったけれど、「近く、短く、でも楽しい」というお出かけもあることを忘れないようにしましょう。
[翌日談]坐薬を入れて、12時間ぐらいぐっすりと眠ったともちゃんは、機嫌よく起きてきました。それでもまだ昼寝もして、でも食事はしっかりとしたペースで早く食べ終えました。大きな声を出したり、ギャハギャハ笑ったり、「元気やでー、明日もどっか連れて行ってやー。」とアピールしています。
 一昨日の反省を込めて、今日は琵琶湖方面を目指すも近場にお出かけすることにしました。今日の行先は、両親が比較的近場で道が渋滞しない所として検討を重ねた結果、道の駅「びわ湖大橋米プラザ」に決定です。京滋バイパスで琵琶湖の東岸に出た後、琵琶湖大橋を渡って橋の西詰めにある「びわ湖大橋米プラザ」のレストランに向い、琵琶湖を見ながらミルクの注入をしようというものです。滋賀県は近江米の産地なので、道の駅の中にお米についての展示館もあるのです。
一昨日の反省を込めて、今日は琵琶湖方面を目指すも近場にお出かけすることにしました。今日の行先は、両親が比較的近場で道が渋滞しない所として検討を重ねた結果、道の駅「びわ湖大橋米プラザ」に決定です。京滋バイパスで琵琶湖の東岸に出た後、琵琶湖大橋を渡って橋の西詰めにある「びわ湖大橋米プラザ」のレストランに向い、琵琶湖を見ながらミルクの注入をしようというものです。滋賀県は近江米の産地なので、道の駅の中にお米についての展示館もあるのです。
京滋バイパスから地道に入って琵琶湖に向うと、水田が広がり、この辺りが近江米の産地であることを納得させてくれます。遠くにはサイロのような建物まで見えています。近付くとやはり農協の近江米サイロでした。この建物の横を通り過ぎると、もう琵琶湖大橋まで一直線。通行料金(普通車200円ですが、手帳を示すと障害者割引で半額)を払って橋を渡ると、両側には青みがかった灰色の湖面が広がっていました。西岸に建つ廃園になった「琵琶湖タワー遊園地」の観覧車の傍に、道の駅はありました。
まだお昼前なので、レストランは奥の琵琶湖側の席が一部埋っているだけです。ともちゃんも一面ガラスの窓際に席を取って、お父さんに琵琶湖が見えるように抱っこして貰いながら、ミルクの注入をしました。せっかく前に琵琶湖が見えるように抱っこして貰っているのに、ともちゃんはお父さんの背中の後ろに見える琵琶湖大橋が気になって体を反らせるので、お父さんは注入中にまた少し向きを変えてくれました。それ以外は、ともちゃんはおとなしくしていました。
ちょっと元気がないのかなと思われたともちゃんが、本領を発揮し出したのは注入が済んで2階に上がってからです。2階の展望バルコニーから改めて琵琶湖を眺めてみようと上がったのですが、バルコニーに出る前の無料休憩所のマルチビジョンで、ナマズのキャラクターが琵琶湖の紹介をしていました。休憩所内で写真を撮ったりしてゆっくりと過ごしているうちに、ともちゃんの目が活気を帯びて輝きだして、ギャハギャハとよく笑うし、両親の話しかけに対してもタイミングよく笑顔や声を返してくれるようになりました。「ともちゃん、琵琶湖のナマズが楽しかったん?」、ともちゃんはニコニコしています。
それからは、ともちゃんは館内の散歩を十分に楽しみました。琵琶湖を眺めた後、2階の吹抜けから稲の藁で作られた巨大な龍を発見して、1階のお米の展示館へ行ってみました。来館記念のスタンプを押すところがあって、ともちゃんもお父さんに手を添えてもらって、押してみることにしました。「力を入れない方がきれいに押せるよ。」と書かれていたので、お父さんが力を抜いて添えた手を押したら、かすれた薄いスタンプしか写りませんでした。「こんなにかすれてしもたわ。」と失敗作を見せると、ともちゃんはギャヒギャヒ大笑いをして喜んでいます。
「一人一枚ずつにして下さい。」と書かれていたスタンプ台紙ですが、「ごめんなさい」と言いながら特別にもう一枚もらって、ともちゃんは再度挑戦しました。今度はお父さんが力を入れて大成功、きれいに写りました。レストランの横のお土産コーナーに戻ってきて、お土産を選びます。これもまた、お出かけの大きな楽しみです。ともちゃんが喜びそうなおもちゃやキティちゃんグッズの並んでいる棚の間で品定めをしました。キティちゃんは根付しかなかったのですが、「暴れん坊将軍キティ」(京都太秦映画村のご当地キティ?)がありました。面白い商品でしたが、「これは今度映画村に行った時に買おか。」ということになりました。
その横で、お父さんが本物の魚を釣上げた時のように、バタバタと尻尾をはねる魚のおもちゃを見つけました。「ともちゃん、これどうや。」、口から出ている紐を引張ると、紐が縮んでいく間尻尾をバタバタと激しく振ります。ともちゃんよりも、お母さんが食いついてきました。「これ、おもしろいやん。これしようや。」、でも、ともちゃんの反応は今一つありません。お母さんが、「ほら、色が違うのがあるやろ。どの色が好きや。青?緑?金?銀?」と話しかけても、ともちゃんはボーッと他の所を眺めています。
「ともちゃんは、この近江商人キティの缶が気になるんやな。」と、お父さんが気付いてくれました。おもちゃの棚の向い側には、近江商人キティが描かれたトランク型の缶に入ったパイが置かれていて、通路に車椅子で乗入れたともちゃんには、左手におもちゃ、右手にキティの缶が見えていたのです。「ほんなら、中のパイはおネエにお土産にあげて、ともちゃんが缶をもろたらどうや。」、ともちゃんの膝の上にトランク型の缶を乗せると、うれしそうに笑っていました。近江商人キティに目を付けるとは、なかなかの目利きです。
琵琶湖鮎キティのタオルも買って、こちらも膝に乗せてレジまで持って行きました。ここ「米プラザ」では、当然近江米も売っています。ちょうど、買置きのお米が少なくなっていたので、お母さんはお米も買いました。駐車場の車の中で、止ったままの観覧車を眺めながら水分補給を行い、今度は湖西を通って帰ります。以前は有料道路だった湖西道路は無料になっていたし、名神高速も時間が早かったので混雑することもなく、スムーズに予定通りに帰ることができました。
ところが、ともちゃんは途中でしゃっくりが出てしまいました。桂川パーキングエリアで駐車して吸引して貰い、しゃっくりを止めた後今度はちゃんと昼寝をしながら帰りました。元気に早く家に帰り着いたともちゃんは、「やっぱりお出かけは楽しいよ。また連れてってや。」とニコニコご機嫌で、声をしてアピールしていました。