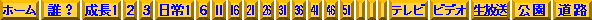ともちゃん
 の日常32
の日常32
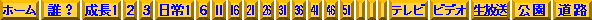
 の日常32
の日常32
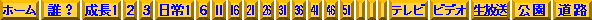
最初にタイトルの一覧があります。タイトルをクリックすると本文が読めます。
「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークをクリックするとそのタイトルに関する写真/動画/連組写真が見られます(「ビデオ」/「スライド」はファイルのダウンロードに1~2分かかります)。
本文の最初にも「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークがありますが、タイトル一覧と同じ写真/動画/連組写真です。
 27日(土)
27日(土)
 11日(日)
11日(日)
 18日(日)
18日(日)
「丹波自然運動公園」
 24日(土)
24日(土)
「福井県、敦賀」
 29日(木)
29日(木)
「マンボウとすずめの運動会」
 9日(日)
9日(日)
 16日(日)
16日(日)
「ラクセーヌ」
 10日(木)
10日(木)
 12日(土)
12日(土)
「交流のひろば」
 4日(水)
4日(水)
 今年は少し時間がかかったけれど、ともちゃんもようやく夏モードになり、体調は絶好調になりました。帰宅時間の都合から、お出かけ距離に制限があるともちゃんですが、体調が安定する夏休みは、四通八達の高速道路で最長不倒の記録更新をするチャンスです。夏休み最後の土曜日の今日は、ルドルフの故郷、岐阜を攻略します。ルドルフというのはお話に出てくる主役のネコです。ともちゃんが小さい頃、テレビ絵本という番組の中で「ルドルフといっぱいあってな」(作:斉藤洋)という作品をやっていました。それで、ともちゃんの家族にとっては、岐阜というと「ルドルフの故郷」ということになっているのです。
今年は少し時間がかかったけれど、ともちゃんもようやく夏モードになり、体調は絶好調になりました。帰宅時間の都合から、お出かけ距離に制限があるともちゃんですが、体調が安定する夏休みは、四通八達の高速道路で最長不倒の記録更新をするチャンスです。夏休み最後の土曜日の今日は、ルドルフの故郷、岐阜を攻略します。ルドルフというのはお話に出てくる主役のネコです。ともちゃんが小さい頃、テレビ絵本という番組の中で「ルドルフといっぱいあってな」(作:斉藤洋)という作品をやっていました。それで、ともちゃんの家族にとっては、岐阜というと「ルドルフの故郷」ということになっているのです。
ルドルフの故郷は厳密には岐阜市ということですが、ともちゃんは平成16年の11月にリニューアルオープンしたという名神高速の養老サービスエリアでミルクを注入して、次のインターチェンジで折返して帰ります。養老サービスエリアはお父さんやお母さんにとっては、関西から信州方面へ向かう夜行スキーバスの休憩所として、若い頃に馴染みのあった場所です。今はどんな風になっているのか、興味のあるところです。
ともちゃんの家から、上りの名神高速に入るルートとしてしっかり定着した京滋バイパス。入口は意味もなくぐるぐると右に左に曲がりくねって気持ち悪いのですが、本線に出てしまうといつも空いているので快適です。しかし、瀬田東ジャンクションから名神高速に入ると、トラックなどの働く車が結構たくさん走っていました。ともちゃんが、夏休みのお出かけで経験的に見出した法則「夏休み最後の休日の高速道路は空いている。」(子供が夏休みの宿題をするのに忙しいので、お出かけなどしている暇はないから)は、働く車で一杯の名神高速では通用しないようです。「大人は仕事を休んで、子供の宿題を手伝ってあげや。」などと、車の中では好き勝手なことを話していますが、ともちゃん自身もまだ宿題(絵日記)は終っていません。
これもすっかりおなじみになった近江米の実る水田地帯から、湖東の山の中に入りました。関ヶ原は湖東三山と伊吹山の山間にあるので、名神高速だけでなく、東海地方から関西へ至る経路としてJRの在来線も新幹線も通っています。この辺りで新幹線がよく雪のために遅れます。戦国時代の人も、山道を避けて、山の間のこの地方を馬で通ったと思うと、歴史を感じて壮大な気持ちになります。北陸道に行った時は、車中で寝られずに困ったともちゃんでしたが、今回はくたっと眠って、元気に目覚めてくれました。
養老SAの車椅子駐車スペースに車を入れて、びっくりしました。車椅子駐車スペースはサービスエリアの建物の前の歩道に直結して設けられているのですが、その歩道がトイレの順番待ちをしている女性であふれていました。トイレはきれいになったし、数も増えたのだろうけれど、20数年前のスキーバスで見た光景と同じだなあとお母さんは懐かしく思いました。大型車の駐車位置には観光バスがずらりと並んでいます。どうやら、朝、関西方面から愛・地球博に向った観光バスの休憩時間に重なったようです。
歩道の人ごみを縫って、ともちゃんの車椅子をレストランまで進めました。途中で覗いたスナックコーナーは混んでいましたが、レストランは空いていました。10時ちょっと前に着いたのですが、それまでの朝食バイキングのみのメニューが10時からは通常のメニューに変るという時間でした。ちょうどよいタイミングです。レストランの奥の席で、お父さんに抱っこされて、ともちゃんはミルクの注入を始めました。養老はもう名古屋文化圏に入っていて、メニューにも「きしめん」や「うなぎのひつまぶし」があります。せっかくなので、お父さんは「ひつまぶし」、お母さんは「きしめんとカツ丼のセット」を頼みました。
「ひつまぶし」は、お櫃に入ったご飯に1cmほどの短冊に切ったうなぎを乗せたもので、うな丼のようにそのまま食べても、わさびなどの薬味を載せて食べても、だし汁をかけてお茶付けにして食べても良いというものです。お父さんは、関西ではあまり食べないお茶付けが気に入ってムシャムシャ食べていました。「きしめん」はうどんを平べったくした麺で、鰹節もかかった鰹だしのよく効いた汁に入っています。カツ丼は卵のかかった普通のものでしたが、「これが味噌カツ丼やったら、名古屋名物そろい踏みやのになあ。」と学童期を名古屋で過したお父さんが言いました。
元気一杯のともちゃんは、ミルクの注入の間もご機嫌な笑顔で、お父さんの顔を覗きこんだり、周りをキョロキョロと見ていました。注入後はサービスエリア内を探索です。新しくなったということで、どんな構造かと両親は期待していましたが、レストラン、売店、スナックコーナーが並んでいる最近のサービスエリアの普通の造りでした。謳い文句の通り、売店には老舗の名店も入っています。お土産を買おうとしましたが、居たのは神戸キティちゃんや京都キティちゃんばかりでした。お土産に関して言うと、ここは関西方面に旅行してお土産を買い忘れた人が、最後に買物をする場所のようです。
それなら、下りのサービスエリアに行けば、今度は東海土産や名古屋土産があるはずです。ここでの買物は諦めて、帰りに水分補給がてら、下りの養老SAに寄ることにしましょう。そうと決まれば、急いで出発です。車が動き出すと、ともちゃんはさっさと眠って、次に備えていました。お父さんは次の大垣インターチェンジで上りの高速を降りて、地道に出るところで素早くUターンをし、下りの高速に乗るつもりでした。しかし、Uターンをして入った入口は、上りと下りの分岐があるはずなのに、ありません。お父さんの大失敗、このインターチェンジは上りと下りの入口が別になっているのでした。
仕方なく次の岐阜羽島ンターチェンジに向かいました。「もう、下りのサービスエリアに着いた?」と途中で目覚めたともちゃんですが、思いがけなく名神の到達点を延ばすことになったのなら、それもまたいいやと楽しげにしていました。岐阜羽島で無事にUターンして、下りの養老サービスエリアに到着しました。昼食時なので混んでいて、スナックコーナの席は取れず、屋外の日陰になっているベンチで蝉の声を聞きながら、水分補給をしました。
のんどりと注入をしながら、辺りを見回していると、ベンチのすぐ後側には低い柵と狭い溝を介しただけで一般道が通っていることが分かりました。「こんな柵やったらすぐに乗越えられるから、サービスエリアに車止めて一般道に出て、どこでもなんぼでも行けるやん。」、「そうや、2時間サスペンスとかの、アリバイ工作に使えそうや。なあ、ともちゃん。」、お父さんに抱っこされて、ホワーっとくつろいでいるともちゃんは、「そんなん、警察がアリバイの裏を取りに現場に来たら、ここから出られるの、すぐ分かるわ。」と思っていたかもしれません。
待望のお土産を買いに売店に行きました。ありました、ありました。予想通り、鯱の上に乗った名古屋キティちゃん。でも、もっと感激したのが、ここ養老の「養老の滝」の水をお酒に変えたという養老仙人キティちゃんです。せっかく養老に来たのだし、このキティちゃんは根付もタオルも迷わずに買いました。珍しい名古屋キティちゃんとしては、名古屋のカレールーメーカー、オリエンタルカレーとコラボのキティちゃんがいました。「そや、そや、オリエンタルカレーは名古屋のカレーやねん。」と懐かしむお父さん。
関西人のお母さんは「ふーん、知らんわ。」、「名古屋弁のCMやっててんで。」、「『ハヤシもあるでよオ。』っていうヤツ?」、「そう、そう。」、このCMなら、関西人もよく知っています。カレーのマスコットキャラとキティちゃんが仲良くカレーのお皿を持っているぬいぐるみが、そのコラボキティです。きっちりお買上げです。お姉ちゃんには、リクエストされていた「ひつまぶし」がなかったので、代わりに「きしめん」を買いました。ここにはきしめんだけでも、迷うくらいに何種類もありました。岐阜羽島まで行って、お土産も買って、ともちゃんの岐阜攻めは大成功、大満足で終りました。
 2学期が始まっても、うれしいことにともちゃんは絶好調の体調を維持しています。1日の始業式にも出席できたし、早速始まった運動会の練習にも、張切って参加しています。だからと言って、休日はおとなしくしているともちゃんではありません。今日は朝食も今年一番の早さで食べ終えて、8時過ぎから愛知県の尾張一宮を目指して出発しました。曇り空からは、雨がポツポツ降ったり止んだりの天気ですが、今日もともちゃんはサービスエリアで注入のために降りるだけなので、何とかなるでしょう。
2学期が始まっても、うれしいことにともちゃんは絶好調の体調を維持しています。1日の始業式にも出席できたし、早速始まった運動会の練習にも、張切って参加しています。だからと言って、休日はおとなしくしているともちゃんではありません。今日は朝食も今年一番の早さで食べ終えて、8時過ぎから愛知県の尾張一宮を目指して出発しました。曇り空からは、雨がポツポツ降ったり止んだりの天気ですが、今日もともちゃんはサービスエリアで注入のために降りるだけなので、何とかなるでしょう。
出がけに近くのガソリンスタンドに立寄ると、店の人がお父さんに「今日はどちらまで?」と話しかけてきました。「ちょっと、愛知県の方まで。」、後部座席に座っていたお母さんやともちゃんに気付かなかったのか「仕事ですか?」、「いや、遊びに。」、すかさずお母さんが後ろから「この子とお出かけなんです。」と言いました。それを聞いたともちゃんは「そうや、そうや。私のお出かけやねんで。」と言わんばかりに、ニコニコしながら「オーオーオー、グヒヒヒヒ。」と大きな声でおしゃべりしていました。
名神高速を尾張一宮へと向かいました。近くに見える山の中腹には雲がかかっています。張切っているともちゃんは全く寝る気配を見せず、ニコニコしておしゃべりをしていました。けれど、お母さんに抱っこされて、さらにその上からマジックテープのついたベルトでお母さんと一緒に縛られているともちゃんは、そのうち窮屈になってきました。そう言えば、今日はこのベルトをお母さんが一段ときっちりと締めています。ともちゃんにとって、このベルトがシートベルトなのです。
昨年の秋、お父さんは運転免許更新の講習でシートベルトの必要性を示すビデオを見てから、急に心配になってきました。高速で走っている時に衝突すると、シートベルトをしていないと、後部座席からでもいとも簡単にフロントガラスを破って車外に飛出してしまいます。今までも聞いてはいたことですが、改めて映像で見せられると、ともちゃんのお出かけの高速道路が心配になります。
お母さんがともちゃんを抱っこしたまま、2人一緒にシートベルトをしようとしましたが、ベルトの長さが足らずに断念。そこで、お母さん自身はシートベルトでシートに固定され、ともちゃんは別のベルトでお母さんに固定されるという、2段階式をとることにしました。ともちゃんとお母さんを結んでいるベルトはお祖母ちゃんに作ってもらいました。お母さんも、ともちゃんも姿勢の自由が制限されるので、高速道路を通行する時にだけ、このベルトを着用することにしています。今日は天下の名神高速道路を名古屋まで行くので、お母さんは気合を入れて一段としっかりと締めていたのです。
一方で、ともちゃんの側湾が進んできています。骨盤と肋骨がくっつくと痛みが出て、筋緊張がよけいに強くなって、さらに体がねじ曲がるという悪循環に陥ってしまいます。長時間同じ姿勢をとったり、ともちゃんが身体のどこに力を入れないといけない姿勢をとったりすると、痛みがでます。今回もシートベルトをきつく締めたので、上体がかなり起きた状態で同じ姿勢でずっと抱っこしていました。お母さんは、ベルトを少し緩めて、ともちゃんがベルトの中で上体を寝かせて、腰を伸ばせるようにしました。本当は、あまり緩くするとベルトの安全性は低くなるのですが、今回は仕方ありません。
腰を伸ばすように抱っこすると、ともちゃんの筋緊張は緩んできました。はしゃいだのと、その後の痛みや筋緊張の疲れが出て、ボーッとしています。「着くまでボーッとしときや。寝ててもええで。」、一宮まではもう少しです。愛・地球博へ行くと思われる観光バスを何台か追抜かしました。「一宮も(養老SAのように)観光バスで一杯とちゃうやろうな。」、「一宮は愛・地球博の近くやから、もうここで休憩することもないやろ。現地へ急ぐで。」と両親は話していたのですが、尾張一宮パーキングエリアに到着すると、観光バスも何台か止っていました。
尾張一宮はサービスエリアではなくてパーキングエリアなので、レストランはありません。ともちゃんのミルクの注入は、スナックコーナー(と言ってもセルフサービスなだけで、メニューは豊富です)で行います。お父さんとお母さんは、ここで名古屋名物を食べるのを楽しみにしてきました。お父さんは、養老SAで食べられなかった味噌カツ丼ときしめん、お母さんは前回ですっかりファンになったきしめんを注文しました。
ここのきしめんは、養老SAのものよりも出し汁の色が濃く、味もドジ辛く(でも鰹出しが効いていておいしい)、また一歩名古屋に近付いたなあと実感させるものでした。「そうそう、これが名古屋の味や。前の(養老SAの)味は、まだ関西文化圏の名残が残ってたんや。」とお父さんは懐かしそうです。「でも、昔名古屋でよう食べてたもんより、麺の幅がずっと広いで。」、麺は15mm位の幅があります。観光客向けにちょっと誇張した感のある麺も愛嬌です。ともちゃんも、そんな両親の会話をミルクを飲みながら、ボーッと聞いています。今はちょっと元気のないモードです。
お母さんの席からはお土産コーナーの一部が見えますが、ぞろぞろと団体客が何組も来ていました。スナックコーナーにまで溢れて来た人の話す言葉が聞こえてきて、海外からの団体さんも来ていることが分かりました。注入が済んだら、ともちゃんもお買物です。ボーッとしていたともちゃんは声を出し、笑顔を見せて「さあ、お買い物するぞ。」と、空元気を発揮し出しました。お目当ての名古屋鯱(しゃちほこ)キティは3種類もありました。鯱の被り物をしたもの、鯱に乗っているもの、鯱に乗ったバスガイドさんになっているものです。名古屋的なキラキラ装飾がついた、一番華やかな鯱に乗ったバスガイドキティを買いました。
さすがに愛知県、ここには養老よりもさらに名古屋土産が一杯です。お姉ちゃんの希望していたレトルトのひつまぶし茶漬けも見つけたし、名古屋限定バージョンのお菓子も何種類も出ていました。その中の、味噌カツ味のポテトチップス(味噌カツのソースに付けて食べる)をお姉ちゃんに買いました。愛・地球博のマスコット、キッコロとモリゾーのグッズもたくさんありました。養老でも見かけたのですが、今回は本当に地球博の愛知県までやって来たので、ともちゃんもキッコロとモリゾーのスタンプを買いました。遠くまでやって来たと思うと、ついついたくさん買物をしてしまうお母さんです。
ここからは、運転手のお父さんに頑張ってもらいました。もう少し名古屋に近付いて、小牧ICから名古屋高速、東名阪、名古屋高速と高速を乗継いで、一般道に下りることなくぐるりと一周して、名神高速の下り線に入って帰路に着きました。走っていると、「愛・地球博○○駐車場の空き状況」という標識をいくつも見かけました。名古屋の市街地の風景は見られませんでしたが、工場や倉庫などを見下ろしながら走っていると、山の中から都会に入ってきた感じです。
ともちゃんは、少しウトウト眠るとうれしそうにニコニコして起きてきて、声を出して笑うとまた疲れた様にボーッとするということを繰返していました。シートベルトも緩めにしています。水分補給は、下りの伊吹パーキングエリアで、車から降りずに行いました。そのお陰もあって、朝8時半出発で、午後2時までに家に帰り着くことができました。遠くまでお出かけしたのに、理想的なお出かけ時間でした。お姉ちゃんが模試から帰ってきた後、お土産を渡すと、ともちゃんは誇らしげに大きな声でニコニコしながら、アーアーギャハハハとお話していました。
 朝、窓を開けると、稲刈りが済んだ田んぼを越えて、ひんやりとした爽やかな風がリビングに入って来るようになりました。「(以前住んでいた大阪とは違って)この辺りでは、季節の移り変りを肌で感じられますね。」と言うお母さんに、先生が「お彼岸の頃になると真っ赤な彼岸花が見られるし、そのうちに気がつくと山全体が真っ赤に紅葉しているんですよ。」とおっしゃっていました。自然豊かな土地に引越してきただけでなく、マンション7階の住いから、戸建ての暮しに変ったので、季節のちょっとした変化が部屋の中にも届きます。
朝、窓を開けると、稲刈りが済んだ田んぼを越えて、ひんやりとした爽やかな風がリビングに入って来るようになりました。「(以前住んでいた大阪とは違って)この辺りでは、季節の移り変りを肌で感じられますね。」と言うお母さんに、先生が「お彼岸の頃になると真っ赤な彼岸花が見られるし、そのうちに気がつくと山全体が真っ赤に紅葉しているんですよ。」とおっしゃっていました。自然豊かな土地に引越してきただけでなく、マンション7階の住いから、戸建ての暮しに変ったので、季節のちょっとした変化が部屋の中にも届きます。
秋の気配は心地よく感じるものの、季節の変り目に弱いともちゃんの体調のことを思うと、お母さんはもっと残暑が厳しくてもいいと思っています。でも予想に反して、今年のともちゃんは秋の気配を感じるようになっても元気です。今年は、8月後半から、例年より遅れて絶好調の夏モードに入ったために、まだ夏の体力を維持できているのでしょうか。先週は、1学期からの念願だった週2回の登校を果しました。1週間に2度の登校で運動会の練習をして、1度の訪問学級ではリハビリの訓練をして頂きました。
運動会の練習と言えば、ともちゃんは演技で「すずめサンバ」(演技中「カラスサンバ」もあり)を踊ります。家でも、お姉ちゃんやお父さんが好き勝手に歌詞と振りをつけて、ともちゃんの前で踊っています。本物のスズメやカラスも、ともちゃんのごく身近な存在です。家の前の田んぼには、稲穂が実った頃からスズメが何十羽と大挙してやって来ました。稲穂が刈取られた今も時々来ていて、どっと一斉に飛立っていきます。カラスは家のベランダや電線を止り木にしていて、ともちゃんの家の車に糞を落す困り者です。
ともちゃんは、今日はいつもより朝寝坊(といっても、6時過ぎには起きているのですが)したので、朝食自体は早く食べたのですが、遠出は無理です。そこで、まだともちゃんが絶好調の夏モードになる前の7月に行ってみようと計画していた丹波自然運動公園に行くことにしました。7月の時は、「夏の国道9号線方面は、日本海への海水浴客で渋滞しますよ。」という先生のアドバイスを聞いて、お出かけは断念しました。9月になったので、もう海水浴客で渋滞することもないでしょう。
丹波自然運動公園へは9号線と並行して走っている京都縦貫自動車道を通って行きます。本当のところは、大阪に住んでいた頃は全く無縁だった京都縦貫自動車道を始点の沓掛インターチェンジから終点の丹波インターチェンジまで走破してみたいというのが先にあって、ともちゃんの散歩コースを探したところ、自然運動公園があったのです。丹波インターチェンジから運動公園まで行く途中に道の駅があるので、まずはそこでミルクの注入をする予定です。道路、公園、道の駅、ともちゃんのお出かけコースにぴったりです。
京都市西端のニュータウン内にあるともちゃんのかかりつけの病院の前を通り、9号線を少し通って京都縦貫に入るのですが、家を出てからずっと道はガラガラに空いていました。「(ニュータウンの人は」みんな、日曜の午前中は出かけへんのかなあ。それとも、もう出かけてしもて、この辺にはいいひんのかな。」と、ほとんど道路を独占状態で走っていたのに、病院の先の交差点で思わぬ渋滞に出くわしました。9号線に出るところの青信号の時間が短いために、この信号のところでだけ渋滞が生じているのでした。街に出ている車は少ないのに、出ている車のほとんどが9号線に集ってくるのですから、海水浴シーズンでなくても9号線は京都西部の基幹道路なんだと実感させられます。
京都縦貫には結構な台数の車が走っています。京都市西京区から、亀岡市、園部町を通って丹波町まで、山間を通る道路はすぐ近くに山また山が迫っているので、高架の下に見える平地の部分が狭くて、名神高速よりも高いところを走っているような気がします。初めて走る道は、見えるものがみな目新しく映ります。はしゃぎ疲れて眠っていたともちゃんも起きてきたので、景色についてあれこれ話しながら行きました。園部インターチェンジを過ぎると片側一車線になり、すぐに対面通行となりました。動物注意の標識には鹿の絵が描かれています。道路の脇の山肌にはススキがたくさん揺れていました。
京都縦貫が終って少し行くと道の駅「丹波マーケス」に到着しました。ともちゃんの車椅子を押して建物の中に入ると、すぐ横に洋品店があります。驚いてお母さんが辺りを覗うと、先には本屋さんやおもちゃ屋さん、食品スーパーもコンビニもありました。ここは確かに道の駅ですが、実際のところは地元の人のショッピングセンターのようです。和食のレストランでともちゃんのミルクの注入をしようとしたのですが、まだ朝早くて朝食メニューだけだったので、フードコートで注入することにしました。
ショッピングセンターに買物に来た人も休憩したり食事を摂ったりするフードコートですが、まだ空いていて、ともちゃんは明るい窓際に陣取りました。お父さんに抱っこされたともちゃんからは、フードコートの向うに買物をしている人たちが見えます。お母さんからはのどかな9号線沿いの呉服屋さんが見えています。ともちゃんは好奇心に満ちた顔でまわりを見回し、ケラケラよく笑っていました。ミルクの後は、道の駅の事務所でこの地域の観光パンフレットや地図をたくさん貰って、お土産屋さんを探しました。
「キティさんがおるで。」と近寄ってみると、そこは普通のおもちゃ屋さんで、ご当地キティちゃんではありませんでした。「ここはショッピングセンターやから、お土産屋さんはないんやわ。」と諦めて、ともちゃんとお父さんは屋外に出て行きました。お母さんは駐車場に着いた時から、入口で実演していたポン菓子が気になっていて、店内でも袋入りを売っているのを見かけて、買いに戻りました。運がいいとはこういうことでしょうか。お母さんがポン菓子を買ったのは、道の駅唯一の土産物屋さんでした。店の入口近くには黒豆製品が置かれていて気がつかなかったのですが、奥にはキティちゃん、なんと丹波黒豆キティちゃんがいました。お母さんが、ともちゃんを呼び戻したのは言うまでもありません。
丹波自然運動公園は、予想以上に自然豊かな中にありました。運動公園の名の通り、球技場、テニスコート、プールなどが備えられているのですが、それらが山の中(林の中ではなくて、高低差のある山の中)に点在していて、おまけに天文館もありました。ともちゃんは、パターゴルフ場の前の駐車場に車を止めて、花崗(はなおか)山を望む芝生広場の一番高くなっているところまで、お父さんに車椅子を押してもらって上りました。山の下には、稲を刈取った田んぼの茶色と、畑や畦の草や山の木々の微妙に異なった幾種類もの緑色で作った貼り絵のような美しい景色が広がっていました。
芝生広場の横の屋根のあるテーブルとベンチで、ともちゃんの水分補給を行いました。目に映る緑とさわやかな風に癒されます。プールはすでに閉鎖されていたし、球技場にも人はいなかったのですが、小さな子供のいる家族連れがピクニックにやってきていて、お弁当を広げたり、バッタを取ったりしていました。今までともちゃんには馴染みがなかった丹波地方ですが、比較的短時間で来ることができて、大自然に囲まれていて、とてもいいところでした。今日は水分補給を終えて帰りましたが、観光パンフレットもたくさん貰ったことだし、これからまた何度も訪ねることにしましょう。
 先々週、先週と2週続けて、週に3日の登校あるいは訪問学級、土日のどちらかにはお出かけをするという絶好調の日々も、少し疲れが出て一休みです。17(土)、18(日)、19(敬老の日)の3連休と、23(秋分の日)、24(土)、25(日)の3連休にはさまれた3日間の平日には、久しぶりにガクガク発作を起こして訪問学級をお休みしました。運動会に備えて様子を見ていましたが、昨日には復活して、元気に「ワァアーアー(お出かけしよー)」と大きな声を出して、訴えていました。
先々週、先週と2週続けて、週に3日の登校あるいは訪問学級、土日のどちらかにはお出かけをするという絶好調の日々も、少し疲れが出て一休みです。17(土)、18(日)、19(敬老の日)の3連休と、23(秋分の日)、24(土)、25(日)の3連休にはさまれた3日間の平日には、久しぶりにガクガク発作を起こして訪問学級をお休みしました。運動会に備えて様子を見ていましたが、昨日には復活して、元気に「ワァアーアー(お出かけしよー)」と大きな声を出して、訴えていました。
朝食時、ちょっと痰の絡みや咳込みもありましたが、それでも早く食べ終えて、今日は福井県敦賀市に向けて出発しました。ともちゃんのお出かけはともちゃんの体力に合せた帰宅時間に制限されるので、お出かけできる範囲は限られています。日帰りで、しかも午後2時か3時に帰宅するという条件なので、普段は近畿地方の中から出られません。でも、体調が安定する夏に早く朝食を終えた時には近畿圏外を目指します。現在近畿2府4県と、それに隣接する西側の岡山県、鳥取県、徳島県、香川県、東側の三重県、岐阜県、愛知県に到達しました。残る隣接県、福井県を今日は攻略します。
車が走出すと大はしゃぎで、ギャハギャハ笑っているともちゃんですが、笑い声に痰が絡んでゼロゼロしています。高速に入るまでに、路肩に車を止めて痰の吸引をしました。さあ、すっきりして再出発します。大山崎インターチェンジには、たくさんの車が連なって入っていきます。でも、前を行く車はどれも名神高速の方向へ流れて行き、京滋バイパスはすっきりと空いています。上りの名神高速は、片側3~4車線が2車線になる京都南と京都東の間がいつも混んでいるのですが、京滋バイパスを利用すれば渋滞区間を過ぎた瀬田ジャンクションに合流できます。「なんで、みんな名神に行くんやろ。」とお父さんは思っています。でも、京滋バイパスが混雑するようになると、それは、それで、またともちゃんにとっては大問題です。
大きな声を出して喜んでいたともちゃんも、吸引をきっかけにして、ちょっと疲れてきました。細くなった目の中に見える黒目が上のほうに行って、ウトウト寝かかっています。お父さんは、「激ミント」という名前の眠気覚しの大きな飴をなめながら、黙々と運転しています。ともちゃんの舌根が喉の奥の方へ沈下するとフガフガと息苦しくなるので、そうならないようにお母さんはともちゃんのあごの奥を押えたり、背中をトントンしたり、タオルケットをかけたりして、ともちゃんが気持よく眠れる環境を作っています。静かな車内に、ザーっという走行音だけが響いています。
しばらくして、ともちゃんがニコニコ笑顔を見せて起きてきました。ぐっすりと長時間眠ったわけではありませんが、短時間ウトウトするだけでも、うまく眠ると元気が回復するので、ともちゃんにとって昼寝は大切です。ともちゃんの笑い声に少し痰が絡んでいるようなのがお母さんは気になりますが、まだ吸引するほどでもないので、様子を見ながら行きます。ともちゃん自身はいたって元気です。
ともちゃんが目覚めると、お父さんもお母さんもワイワイとよく喋り出しました。「あの観光バスは明日閉会する愛・地球博に行くんかな。」とか、見慣れた道でも話題はつきません。「あっちの茶色のバス、後ろが妙に汚いで。変やな。」と言いながら追抜かすと、それは競走馬を運ぶバスで、後ろの汚れに見えたのは馬を乗せるためのドアでした。(競走馬のトレーニングセンターがある)栗東からやって来たのでしょうか。北陸道に分岐して、木之本インターチェンジを過ぎると、ともちゃんは初めて通る道になりました。高速の両脇にススキがたくさんなびいています。
県境の山をトンネルで越えると、いよいよ福井県に到達です。高速を降りた後、敦賀市内の混雑を迂回するために国道27号線のバイパスを通って「気比(けひ)の松原」を目指しました。今日のともちゃんのミルクの注入場所は気比の松原です。27号線には「かまぼこ工場」や「昆布館」など、観光客に向けた看板がたくさん出ていました。気比の松原の駐車場はシーズンオフでガラガラに空いていると思いきや、観光バスが2台の他、乗用車もたくさん止っていました。敦賀湾を見ながら注入できるように、端っこに残っていた海際の駐車区画に、後部が海に面するように車を止めました。
浜辺には、まだまだ人がたくさんいます。テントを張ったり、釣をしたり、浜辺で遊ぶ子供も、水着を着て海に入っている人までいました。松原の奥のほうの浜でブラブラしている団体さんは観光バスの一団でしょうか。久しぶりに、ともちゃんの得意技の後部座席を後向きにセットして、そこに座っての注入をしました。曇空の下、海から吹く強い風を両親は心地よく感じますが、ともちゃんにはちょっと冷たいかもしれません。タオルケットで包んで、お父さんに抱っこしてもらったら、寒くなんかないよというように、ケラケラ笑顔が返ってきました。
気比の松原からは敦賀半島と越前海岸の出張りに囲まれて、日本海の大海原の気配は全く感じられません。風は強いのに、穏やかな波が規則正しく打寄せています。ともちゃんは、近くのテントから流れてくるラテン音楽を聴きながら(ともちゃんの車の隣に陣取っていたのは、どうも日系ブラジル人の一団のようです)、行く夏を惜しむ浜辺の雰囲気を楽しんでいました。松原の向こう、半島の裾を車が走って行きます。のどかな光景ですが、この半島の先には原発があると思うとお母さんは本当は怖いのです。お姉ちゃんが生まれてすぐの頃、食品の安全性などに神経質になっている時に、旧ソ連のチェルノブイリ事故が起っているので、原発事故が起こらないことを願って止みません。
ともちゃんの注入が終ったら、来る時に前を通った「おさかな街(まち)」を訪ねます。事前に敦賀市内の地図を見ている時に、「きっと、ここはツアーの観光バスが着いて、お土産とかどんどん買いこむところやで。」とお父さんが目をつけていたところです。TVでそういう光景を見て、一度行って見たいと思っていたお母さんは楽しみにしていました。でも、それ以上に喜んだのが、ともちゃんでした。車椅子を降りた時から目が爛々と輝き、口元には笑みを浮かべて、わくわくしているのがよく分かります。活気あふれる市場の雰囲気が珍しく、楽しいのでしょう。
魚屋さんが主ですが、お土産物屋さんもあって、いました、いました、各地のキティちゃんがたくさん。京都キティから、富山ホタルイカキティ(ともちゃんはお父さんの出張土産でもう既に持っています)、輪島朝市キティまで。福井のキティちゃんは、勝山の恐竜キティ、永平寺の小坊主キティもありましたが、そこまでは到達していないので、福井らっきょうキティを買いました。お姉ちゃんにキティの箱に入ったカニせんべい、焼き鯖寿司や昆布のふりかけも買いました。行く先々のお店で試食を進めてくれるのですが、魚介類の食物アレルギーのあるともちゃんの世話があるので、気軽には手に取ることができず、お母さんはちょっと残念でした。
帰りには、敦賀からの帰路で唯一福井県内にあるパーキングエリア、刀根パーキングエリアで水分補給をしました。ここはトイレしかないパーキングエリアですが、トイレの横にちゃんと車椅子用の駐車スペースが設けられていました。車中で仮眠をとるために駐車している車が結構ありました。ここまで、家から持参した煎餅とダイエットコーラしか口にしていなかった両親は、2回に分けて行うともちゃんの水分補給の合間に、おさかな街で買ってきた串に刺した大きなさつまあげを食べました。食べ終った後、すぐ横で手も洗えて便利でした。
滋賀県との県境の山を越えると、曇り空が一転して青空になりました。そして、空の高いところには箒で掃いたような雲が浮かんでいます。すっかり秋の空です。ご機嫌で、元気にしているともちゃんですが、そろそろ体調に気をつけたほうがいいかもしれません。遠出するのは、今年は今日が最後になるかなと両親は思っています。冬籠りまではまだまだ間があるので、それまではまた近場にお出かけしましょう。
 雲一つない秋晴れ、運動会にぴったりの天候の下、ともちゃんの養護学校の運動会が行われました。このところ、ともちゃんは、いつもと違う雰囲気や知らない場所に反応して表情がこわばるので(それはそれで、ともちゃんの発達の証なので、みんな微笑ましく見ているのですが)、お母さんは緊張するかなあと思っていました。でも、訪問学級で初めて演技の内容を聞いて以来、競技も演技も2回ずつ練習に参加できたし、演技の曲のテープをお借りして家でも聴いて楽しんでいたので、楽しく参加することができました。今年のともちゃんの運動会のキーワードは「マンボウ」と「すずめ」です。
雲一つない秋晴れ、運動会にぴったりの天候の下、ともちゃんの養護学校の運動会が行われました。このところ、ともちゃんは、いつもと違う雰囲気や知らない場所に反応して表情がこわばるので(それはそれで、ともちゃんの発達の証なので、みんな微笑ましく見ているのですが)、お母さんは緊張するかなあと思っていました。でも、訪問学級で初めて演技の内容を聞いて以来、競技も演技も2回ずつ練習に参加できたし、演技の曲のテープをお借りして家でも聴いて楽しんでいたので、楽しく参加することができました。今年のともちゃんの運動会のキーワードは「マンボウ」と「すずめ」です。
「マンボウ」はともちゃんのクラスK1組が属する青チームのシンボルです。運動会はチーム対抗で行われていて、1学期のチーム活動の間にチームカラーをイメージするシンボルをそれぞれみんなで決めました。赤チームはスイカ、黄チームはトラです。高等部のチーム対抗の競技は「2人でドン・・・旅するシンボル」といい、ハリボテでできたシンボルを、2人で力を合わせて色々な方法で運んでいくというものです。もっと正確に言うと、2部構成になっていて、速さは競わず距離を競う「箱倒し」と、シンボルをバトンの代りにして速さを競う「ザルリレー」、「モッコリレー」、「輪つなぎリレー」から成っています。
ともちゃんたち重症心身障害児は、数字の大きいクラス(障害の軽いクラス)の友達とペアを組んで、「箱倒し」をします。前の選手が転がしたシンボルを友達が拾って来て、車椅子に座るともちゃんたちの膝に乗せてくれ、2人で一緒にチームカラーの箱がいくつも積上げられた場所まで行きます。トラックを一周使って4組が参加するのですが、速さの競争ではないので、落着いていきます。箱のところまで行くと、友達がシンボルをともちゃんたちの膝の上から取って、箱のてっぺんに置きます。そして、2人でダンボールの板の片方ずつを持って、タイミングを合せ、箱にぶち当てて箱を倒し、シンボルをいかに遠くまで転がすかを競います。
ゆったりとしたペースで「箱倒し」が終ると、今度はそのシンボルを使ってリレーが始ります。最初はザルの上にシンボルを乗せて、2人で引張って走ります。腰を落として低い位置でザルを引張らないと、シンボルがザルから転がり落ちてしまいます。ザルから落ちたシンボルは先生が拾って下さいます。次は板で作ったお神輿の台の様なモッコの上にシンボルを乗せて、前と後を2人で持って運びます。こちらもシンボルが落ちないように注意しなければなりません。最後の輪つなぎリレーになると、シンボルの両脇からでている紐をそれぞれが持って2人で全力疾走し、白熱した競走になります。勝敗は、リレーの得点に「箱倒し」4組の得点を合計して決められます。
「すすめ」というのは、ともちゃんのいる高等部重症心身障害児グループの演技「すすめサンバ」でともちゃんたちが演じる「すずめ」です。演技はストーリー仕立てになっていて、1、2年生はすずめで、3年生が主役のカラスです。すずめ達が仲良く遊んでいるところにいたずらカラスが来て、すずめを追払ってしまいます。カラスがサンバを踊っていると、そこへネコがやって来て、今度はカラスが追いかけられてくたくたになってしまうのですが、やさしいスズメが出て来て「一緒に遊ぼう。」と言って、一緒にすずめサンバを踊るという筋書きです。ともちゃんは、やさしいすずめのうちの1羽です。
すずめサンバでは、音楽を聞いて楽しく踊ろうというのはもちろんですが、他にも仕掛けがあります。すずめやカラスは遊ぶときに「ガッタン橋」を渡ります。ガッタン橋は幅の広い低いシーソーのような構造で、車椅子に乗って進んで行って真ん中を過ぎると、ガッタンと下に下がります。また、カラスを追いかけるネコは、カラーのナイロンゴミ袋で作られた巨大な旗に描かれていて、黒い地色に黄色い目鼻が光を通してくっきりと輝いています。カラスだけではなく、すずめもフワリフワリと頭の上に覆い被さってくるネコバルーンの色や感触を味わうことになっています。
プログラムを見て、ともちゃんの登校時間やミルクの注入時間を検討した結果、今年の運動会はこの2つの種目だけに参加することにしました。9月、体調が良かったともちゃんは、何度も運動会の練習に参加できました。最初の練習は、雨天のために先生に訪問していただいた日でした。訪問学級の時には、先生はいつもカセットデッキやリコーダ、絵本、人形など、たくさんの教材を車に積んで来て下さるのですが、この日は目新しいバランスボードを持ってきていただきました。
ともちゃんは、すずめサンバのカセットをかけて歌を歌ってもらい、ミニ版のネコの旗を目の上でフワリフワリとしてもらいました。最後に、先生がバランスボードの上にともちゃんを抱っこして座って、左右に体重をかけてユラユラとゆれました。バランスボードの上で抱っこしてもらったともちゃんは、何かが始まるという期待感で、目を輝かせてキョロキョロしていましたが、ユラユラ揺れ始めると、予想していたことと違ったのか、はたまた予想通りだったためか、おとなしくしていました。
登校して、みんなと一緒に体育館や運動場で練習もしました。新しい学校の運動場には、ともちゃんもお母さんも初めて出ました。竹薮に面した広い運動場は、トラックから外れたところには雑草が生え、トンボが乱れ飛んでいました。今までは、高い塀とネットに囲まれた狭い(だからこそきれいに整備されている)都会の運動場しか知らなかったので、お母さんはこの田舎の分教場のような運動場に感激してしまいました。ともちゃんは、慣れてくるに従って、練習もどんどん楽しむようになりました。
「2人でドン」は、積上げた箱に板をぶつける位置によってはシンボルが逆方向に転がり落ちて、車椅子に乗っている友達のおでこにゴチンなどということもあります。ともちゃんのペアは、相棒のK君がシンボルぎりぎりのところを狙うという作戦を立てていて、それが功を奏してマンボウはいつもスイカよりもトラよりも一番遠くまで転がっていきます。K君が照れながら、横から声をかけてくれた時、ともちゃんは笑って答えていました。
「すずめサンバ」では、ガッタン橋は表情が硬いのですが、最後にみんなでサンバを踊るところではパアッと笑顔を見せてくれます。演技の練習の後、みんなでネコバルーンの下に入った時は、上を見上げて笑っていました。ストーリー通りにナレーションと音楽が入ったテープもお借りして、学校を休んでいる間に聞きました。最初は、「すずめサンバ」の曲よりも1学期に学校でよく聞いた「世界の約束」(ハウルの動く城の主題曲)の方に反応していました。でも、「すずめサンバ」を学校でも練習し、家でも家族が適当な歌詞をつけて適当に踊りながら歌っているのを聞いていたおかげで、昨日は優しいすずめの「すずめサンバ」でよく笑っていました。
さて、本番です。開会式の間に登校したともちゃんは、出番まで教室でゆっくりと過ごしました。今日は暑いので、出場前に水分補給もしました。まずは「マンボウ」に出場です。第一組が競技をしていて、K君と先生と一緒にスタート位置で待っている間、ともちゃんは余裕でよく笑っていました。K君がともちゃんの膝にマンボウを乗せてくれました。ともちゃんは前の学校の校内服の青いジャージのズボンを履いて出場したのですが、マンボウの鮮やかな青色とともちゃんのジャージの青色が妙に合っています。正面から見ると、ともちゃんの顔や体がマンボウで隠れて、マンボウから足が出ているようです。
マンボウを箱の上に乗せてもらうと、ともちゃんも板の端に付けられた輪っかをしっかりと持たせてもらって、エイッと箱にぶつけました。今回も作戦大成功、1等賞です。「完璧!フォー!」とK君の勝利の声が響いています。ともちゃんは、マンボウを運んでいる間はよそ見をしていましたが、箱に板をぶつけた後はにこやかな表情でしっかりと箱の方を見ていました。いつもと違って、友達のお父さんやお母さんが出入りする教室に戻ると、ともちゃんは緊張していました。お母さんが「ともちゃんのお父ちゃんもおるやんか。」と言うとキョロキョロ見渡して、お父さんの気配を感じるとギャハハハと笑っていました。
今度は「すずめ」です。すずめの衣装の黄色のチェックのスカーフを首と手に巻いてもらい、ともちゃんはやる気満々の表情で先生と一緒に自分の持ち場に出て行きました。ちょうど後ろには竹藪が広がっていて、すずめのお宿にはぴったりです。待っている時はホーっとしていたのに、「すずめサンバ」の曲がかかると、ともちゃんは「これこれ、これに出るねん。」と言わんばかりにパッと笑顔になりました。「こっち見て、こっち見て。」とカメラを構えて心の中で叫ぶお母さんとは反対の方を向いて笑っているともちゃん。後で先生が声を出して笑っていましたよと教えて下さいました。
ネコバルーンは、カラスを追いかける前に、待機している優しいすずめたちの上にもやって来ましたが、ともちゃんはゆったりと眺めていました。いよいよ出番となって、優しいすずめはガッタン橋を渡りましたが、これはやっぱりちょっと苦手です。最後に踊る場面になってみんなで踊り出すと、ともちゃんはじわじわと楽しさが湧いてきて、うれしそうな笑顔を浮かべていました。演技終了後、引き上げて来たともちゃんに、看護師さんや先生が「よう、がんばったね。上手やったわ。」と声をかけて下さると、ともちゃんは満面の笑顔で「そうやろ。私、頑張ってんもん。」と、とても満足そうでした。
 先日、学校の散歩で秋を探しに行きました。学校の花壇でコスモスの花を眺めてから、春にも行った光明寺までの農道を行くと、黄色くなった稲穂が首を垂れていたり、柿がたわわに実っていたり、農家の人が落ちたイガ栗を踏んで栗の実を出して拾っていたりと、いたる所に秋を見つけました。農道では、通りがかった同じグループの3年生のU君と糸電話をして、耳に当ててもらった紙コップから聞こえる声にキョロキョロと不思議そうに辺りをうかがっていたともちゃんでした。
先日、学校の散歩で秋を探しに行きました。学校の花壇でコスモスの花を眺めてから、春にも行った光明寺までの農道を行くと、黄色くなった稲穂が首を垂れていたり、柿がたわわに実っていたり、農家の人が落ちたイガ栗を踏んで栗の実を出して拾っていたりと、いたる所に秋を見つけました。農道では、通りがかった同じグループの3年生のU君と糸電話をして、耳に当ててもらった紙コップから聞こえる声にキョロキョロと不思議そうに辺りをうかがっていたともちゃんでした。
ミルクの注入の時に、先生から亀岡のコスモス畑のことを教えてもらいました。亀岡なら家から近いので、ともちゃんの朝食終了の時刻が遅くなっても出かけることができます。昨年7月のひまわり畑、今年5月のバラ園に続いて、一面の満開の花の中でのともちゃんの笑顔の写真が撮れたらいいなとお母さんは思いました。亀岡には、道の駅「ガレリアかめおか」もあります。そこで先にミルクの注入を済ませ、両親は腹ごしらえをしてから、コスモス畑を訪ねましょう。
この頃、以前にも増してお出かけに執着しているともちゃんは、昨日から「ワーワーオーオー(お出かけに連れて行ってえー)」と騒いでいて、夜の眠りも浅かったのに、今日は朝からうれしくて仕方のない様子でした。車の中でもギャハギャハしていたのに、ガレリア亀岡に着くころには、疲れてきてボーッとしていました。そういうところが、いかにも子供らしいともちゃんです。ともちゃんのお姉ちゃんも、ともちゃんが生まれる前に両親と初めて海に行った時、行く前からはしゃぎすぎて、特急電車に乗継いだ途端にしんどくなるということがありました。そんな訳で、ともちゃんのことを両親は「子供の中の子供やなあ。」とほほえましく見ているのですが、お姉ちゃんの幼少期とは違って体力が無いので、その分注意が必要です。
ガレリアかめおかには早い時間に着いたのに、駐車場は車で一杯でした。まだレストランは開いていなくて、そんなに大きくはない物産販売のお店が開いているだけです。ガレリアかめおかは道の駅とともに生涯学習センターが併設されているのですが、特別なイベントは催されていないようです。車の主はみんなどこに行ってしまったのかなあと両親は話していましたが、後で調べると庭園や大浴場など他にも色々施設があるので、それぞれに行先があったのでしょう。物産館で両親の食事にするおにぎりを買って、ベンチでミルクの注入をしました。
最初は、今までの習慣で日陰に陣取っていましたが、ともちゃんには少し寒いかなと思ったので途中で日向に出ました。そろそろ、日だまりが恋しい季節になりました。注入が終ると、物産館でお買物です。残念ながら、さすがに亀岡キティちゃんはいなかったのですが、ちりめん布地で作られた招き猫が各種いて、その中に、たくさんの小判の上に乗って小判をかかえた、お父さん流に言うと「成金招き猫」がいて、おもしろいので買いました。物産館には亀岡牛の肉屋さんも入っていて、亀岡牛コロッケも売っていたので、帰ってからお姉ちゃんと一緒に食べようと買いました。物産館の前では野菜の朝市をやっていて、一角には丹波栗も販売されていました。
ともちゃんも両親もお腹が一杯になって、これからゆっくりとコスモス観賞をします。コスモス畑は亀岡市体育館の横、京都縦貫道の西側ですが、道の駅は東側にあります。道の駅から京都縦貫を越えてコスモス畑に行く時に、お父さんが道を一筋間違えてしまったので、本来ならコスモス畑に東側から入るところを、西側から入る格好になりました。でも、人生何が幸いするか分りません。コスモス畑の東側の駐車場に入るには車が渋滞しているようですが、ここ西側の駐車場にはすぐに入れました。それでも、もうかなり奥の方しか駐車スペースは空いていませんでした。
目の前にコスモス畑が広がっていて、心が躍ります。青空の下に広がる緑の葉っぱの中にピンクやエンジ色の花が点々と散らばり、風にそよいでいる風景は、大輪のひまわりの畑とはまた違った優しげな魅力があります。朝、恋しかった日向は、お昼近くなると強烈になり、日傘が不可欠となりました。畑のあぜ道には木の板が敷かれていて、車いすでも通行できます。コスモス畑の西側の入口から、中に入りました。あぜ道の両脇からは、葉や花を付けた細い枝がはみ出てきていて、車いすを擦るコスモスを間近に見ながら進みました。
コスモスの色はピンクやエンジだけでなく、白や黄色、ピンクの花びらの縁だけ濃いものなど、様々な色があることが分りました。一人ずつしか行けないあぜ道を、ゾロゾロとたくさんの人たちが連なって行くので、所々で人の渋滞も起っています。そんな訳で、あぜ道の幹線から外れたところで、ゆっくりと写真撮影をしました。この頃にはともちゃんの笑顔も復活して、いい写真が撮れました。昨年はひまわり娘のともちゃんでしたが、今年はコスモスっ子のともちゃんです。
余談になりますが、ともちゃんが生まれてすぐの頃、公立保育所に通う前、ともちゃんの障害の程度や状態が両親にはまだどうなるか全く分らなかった頃に通っていた保育所がコスモス共同保育所という名前でした。普通赤ちゃんは眠る時には両腕をW字の形に布団の上に投げ出して眠りますが、筋緊張の強いともちゃんは、腕を布団の上には置かず、両肘を曲げたままで両腕を空中に突き出したまま眠っていました。コスモスの先生がそれでは腕がだるいだろうと、タオルを当てがって下さっていたことを思い出します。通い始めてすぐに入退院を繰返すようになったので、たくさんは通えなかったのですが、ともちゃんは正真正銘コスモスっ子なのです。
広大なコスモス畑の中には櫓もあって、上に上がって畑を一望できるようになっていました。入園者は、決まった本数のコスモスを(専用の別の畑で)自分で切取って持帰ることもできます。自分で切らない人には、おみやげの花束がもらえます。お母さんは、できるだけ色々な色が混ざった花束を3束選びました。入ってきたのとは反対側の東の端まで行きました。こちら側がメインの入口で、付近には屋台が出ていて、コスモス畑には不似合いなブルースの生演奏をやっており、ベンチやテーブルもありました。ちょうどお昼時で屋台は混雑していましたが、それでもベンチに席を見つけて、ともちゃんは水分補給、両親は屋台の点心を食べました。
帰りは別のあぜ道を通りました。このコスモス畑では、創作かかしのコンクールもやっていて、帰り道はかかしの前を通りました。招き猫かかしや、中の詰め物が無くなってしまいペタンコになってお辞儀をしているキティちゃんかかしもいました。今年の流行、キッコロとモリゾーのかかしやマツケンサンバのかかしもいました。広大なコスモス畑の中の散歩に満足して家に帰ったともちゃんは、お姉ちゃんから「ともちゃん、今日、えらい日焼けしたんとちゃうか。いつも色が白いのに、今日は精悍な感じやで。」と言われていました。
 すっかり秋らしくなり、学校でもお隣の家の庭でも、金木犀のオレンジ色の小さな花がいい香りを漂わせています。学校では、11月にある文化祭の準備が始りました。詳しいことは今後のお楽しみですが、ともちゃんたち1組は「しずく」になります。ともちゃんの役柄を聞いてから、家では某エアコンのCMキャラクターから「ともちゃんは『ぴちょんくん』の役やるねんなあ。」と言われています。お姉ちゃんは、さっそく水色の水滴のようなガラス玉の付いた髪止めゴムを買ってきてくれて、ともちゃんの役作りに協力的です。
すっかり秋らしくなり、学校でもお隣の家の庭でも、金木犀のオレンジ色の小さな花がいい香りを漂わせています。学校では、11月にある文化祭の準備が始りました。詳しいことは今後のお楽しみですが、ともちゃんたち1組は「しずく」になります。ともちゃんの役柄を聞いてから、家では某エアコンのCMキャラクターから「ともちゃんは『ぴちょんくん』の役やるねんなあ。」と言われています。お姉ちゃんは、さっそく水色の水滴のようなガラス玉の付いた髪止めゴムを買ってきてくれて、ともちゃんの役作りに協力的です。
金曜日に登校したともちゃんは、1組の友達みんなで背景の「海」を描きました。実際に描く前に、大きな模造紙に先生が青い絵具をボトボトボトと音をたてて落し、しずくの音を聞きました。その後、こぼれた絵具の水たまりの上に、小さなボールを転がしたり、大きなボールをボンボン突いたりしてもらいました。ともちゃんは、大きなボールが最初に弾んだ時は音に驚いて、ビクッとしていましたが、次からはギャハギャハ笑っていました。海を描くのは、青い絵具を混ぜて泡立てた石鹸を指に付けてもらって、模造紙に塗りたくりました。文化祭が楽しみです。
今日は、ともちゃんのかかりつけの病院の近くにあるショッピングセンター、ラクセーヌにお出かけしました。いつも、病院へ行く時に前を通るので、どんなところかなと思っていたのですが、ラクセーヌの中核店舗である高島屋でやっている北海道物産展の折込みチラシが入っていたので、行ってみることにしました。駐車場の障害者スペースに車を止めてドアを開けると、ヒューとひんやりとした風が吹込んできました。歩道の並木の葉っぱの先が少し赤く見えます。視界のその先には竹林があって、風でユサユサ揺れています。ニュータウンの中ののどかなショッピングセンターです。
いつも通り、まずはフードコートでともちゃんのミルクの注入をして、その後お母さんの用事に付合って郵便局に向いました。この一角には、ショッピングセンターの他に郵便局や銀行、そしてホテルも、おまけに温泉も揃っています。少し散策して、ホテル前の大階段に設えられていた結婚式用の赤絨毯の前で写真を撮ったりして、再びショッピングセンターに戻りました。専門店街を、おもちゃ屋さんを覗いたり、キティちゃんのプリント生地のたくさん並んでいる手芸店に入ったり、お姉ちゃんが欲しがっていたブーツを靴屋さんで探したり、フラリフラリと見て回りながら、高島屋まで行きました。
高島屋は、京都の四条河原町に大きな店を構えている伝統ある百貨店ですが、ここにあるのはごく小さい高島屋です。1階で北海道物産展をやっていましたが、こちらもぐるりと一区画を回ると通路の両側にお店が並んでいるというだけのかわいらしい規模です。それでも、しっかりと名物は押えられていて、目当てのコロッケと海鮮弁当を買いました。一通り見て回ったお母さんは、ともちゃんと一緒のために、並べられた海産物の試食に手を出せなかったことが心残りでした。
ともちゃんは、お姉ちゃんに誕生日プレゼントとしてもらったキティちゃんの首から下げる財布を持ってきていて、自分でお買物するのを楽しみにしていました。そこで、1階にあるスーパーマーケットのような食品売場でともちゃんのお買回り、食玩を探してみました。でも、そこにはともちゃんの気に入るような食玩はなくて、2階のおもちゃ売場に行ってみました。小さい売場ですが、サンリオ商品も置かれていて、棚の隅におもしろいキティちゃんを見つけました。
手足が長く、すらりとした体にファッショナブルなドレスを着た、お父さんに言わせると、「リカちゃん人形がキティちゃんのかぶり物を着ているような」キティちゃんです。素材は布、ぬいぐるみです。プラスチックのケースには、「高島屋オリジナル マンスリードール」と書かれています。ラベルなどを見ると、どうやら2000年のキティちゃんブームの時に、毎月ドレス違いで発売されたものが、郊外の小さな百貨店であることが幸いして、4体だけ今まで残っていたようです。なんかおかしな感じがするのは、リカちゃん体型なのに、本来のキティちゃんのように首がないからです。でも、そこがまた愛嬌です。
「これはレアやなあ。押さえとこ。」、お父さんは、ともちゃんに4体のキティちゃんを見せて、どれにしようか相談しました。さんざん迷って、白いロングドレス、白い帽子のキティちゃんにしました。ミニスカートの方がひょろりと足が出ていて面白いのですが、このドレスが一番上品な感じなので、こっちにしました。ともちゃんの首にかけた財布の中の小銭では買えないので、お母さんがこっそりと千円札を財布に入れてから、ともちゃんにしっかりと見えるように、「お金を払うわ。ほら、お金を出したで。ハイって払うよ。」と、ともちゃんと一緒に支払いをしました。
店員さんは、包装したキティちゃんをカウンター越しにお母さんに渡すのではなく、カウンターを出てともちゃんの正面まで来て、ともちゃんに手渡して膝に置いてくれました。それまですました顔をしていたともちゃんは、キティちゃんを受取った途端、パアッと満面の笑顔を見せてくれました。お母さんは、ともちゃんのあまりにタイミングのよい笑顔にびっくりしました。気分が高揚していて、箸が転んでも笑い転げるというような笑いではありません。「店員さん、ありがとう。これ、私が自分の財布からお金を出して買ったキティちゃんやで。うれしいなあ。」という気持を表しているようです。ともちゃんが笑った時、この場の空気が暖かく幸せに満ちているような気がしました。
お父さんは、この後ともちゃんの水分補給をしに、近くの小畑川公園に行ってもいいかなと思っていました。けれど、お母さんが「2階に入っている100円ショップに行きたい。」だの「駐車場から入る入口にあった食品スーパーで卵を買いたい。」だの言うので、水分補給は100円ショップの横のベンチで行いました。ともちゃんがお父さんとこのベンチで待っている間に、お母さんは走って買物を済ませました。ラクセーヌでのお買物は想像以上に楽しいものでした。近くて、色々な専門店も入っているので、これから何度も来ることになるでしょう。お父さんは「そのうち、なんやかやと言って、残っているレアキティ3体も、次々にともちゃんが買占めてしまうのとちゃうか。」と笑っていました。
 今日はともちゃんの養護学校の文化祭です。文化祭では中学部と高等部の舞台発表を行います。小学部は別の日に秋祭りという行事があるので、文化祭ではオープニングで少し秋祭りの紹介があるだけで、舞台発表を見学します。舞台発表は、今日と明日の2日間、午前中だけを使って同じような障害の子供達で構成された中学部3グループと高等部4グループで行われます。ともちゃんは、初日の今日、高等部1組から3組の重症心身障害児のグループで演じる劇「うたがみえるきこえるよ」(原作:エリック・カールの絵本)に「しずく」の役で出演します。
今日はともちゃんの養護学校の文化祭です。文化祭では中学部と高等部の舞台発表を行います。小学部は別の日に秋祭りという行事があるので、文化祭ではオープニングで少し秋祭りの紹介があるだけで、舞台発表を見学します。舞台発表は、今日と明日の2日間、午前中だけを使って同じような障害の子供達で構成された中学部3グループと高等部4グループで行われます。ともちゃんは、初日の今日、高等部1組から3組の重症心身障害児のグループで演じる劇「うたがみえるきこえるよ」(原作:エリック・カールの絵本)に「しずく」の役で出演します。
重症心身障害児ばかりの劇なので、役を演じるというより音や音楽を聞いたり、たくさんのシャボン玉を見たり、フワフワの感触を感じたり、その中でも比較的軽度の子供は自分でボタンを押して仕掛けを動かしたりと、練習の過程でも本番でも自分達も楽しもうという趣向のものです。ともちゃんは、訪問学級でも学校でも楽しく練習をしてきました。そんな中で、新しい発見がありました。この劇の中には様々な音楽や音が出てくるのですが、その中でともちゃんは明らかに「花祭り」の歌が好きだということです。
劇の流れに沿って順に音楽の入ったテープを先生からお借りして、ともちゃんが学校を休んでいる間も何度も聞きました。その時から、ともちゃんは自分の出番の曲(これも好きで、「私これに出るんやで。」とばかりににっこりと笑顔が出ます)もさることながら、いつも「花祭り」で一番楽しそうに笑っていることにお母さんは気が付きました。先生に伝えると、学校でも「やっぱり、花祭りは好きですね。イントロが聞こえると、よく分っていて、パアッと笑顔が出ます。」と教えて頂きました。
この話を聞いたお姉ちゃんは「ともちゃん、おネエも小さい頃、小学校で習う歌の中で、花祭りが一番好きやってんで。一緒やなあ。この曲は他の曲と違って、子供心にもエキゾチックな感じがするもんなあ。」と共感しています。好きな曲があるのはともちゃんに限ったことではないそうです。友達のKzちゃんは優しくて優雅な曲がかかると穏やかに微笑みをたたえた顔を持上げて、声が出ます。Ktちゃんは、コンと堅い激しい音がすると、ケラケラ笑い出します。音だけではありません。柔らかい感触が好きだったり、シャボン玉の虹色を不思議そうに眺めたりと、みんなそれぞれに好きなもの、興味のあるものがあるようです。
ともちゃんのように重い障害があっても、それぞれに好きな音楽が違うこと(健常者なら当り前のことなのですが)が改めて分ったことにお母さんは感激しています。「障害も個性のうち」という人がいますが、ともちゃんの両親は命に関わる重い障害をそんな風に簡単に片付けて欲しくなと思っています。その時、「『障害も個性のうち』とは思わんけど、『障害者もそれぞれ個性的』やと思うわ。」とお父さんが言っていたことを思出しました。そして、笑顔だけでは表現しきれないかもしれない、もっと細かなともちゃんの好みを今後もたくさん見つけられたらいいなと思っています。
さて、いつもの暖色系とは違って水色のズボンと白の上着で登校したともちゃんは、お揃いの水色のロングエプロンとスカーフの衣装を着けて、しずくに変身します。髪飾りは、ともちゃんの意見を採用(?)して頂いて、キラキラ光るブルー系のものをいくつも付けます。ともちゃんは、お姉ちゃんにもらった髪飾りも一緒に付けています。ともちゃんの車椅子の赤いシートベルトは、ロングエプロンとスカーフの下にうまい具合に隠れて、水色の「しずく」になりました。仕上げに、教育実習の先生のお手製のプレゼントのしずくのマスコットを揃って車椅子に取付けました。
ともちゃん達、しずくが舞台の幕の後ろにスタンバイして、劇が始りました。「私には歌が見えます。音楽が描けます。」と主役のバイオリニストが登場しましたが、演じる3年生のU君がお休みなので、代役の先生です。ちょっと拍子抜けした感じで残念です。バイオリンの音楽が流れる中、U君が押しやすいように工夫された大きなボタンスイッチでスクリーンの画面を変えたり、(シャボン玉を作る機械のスイッチを入れて)シャボン玉をたくさん吹出したりします。お日様が黒い雲に隠れて、やがてポトンポトンと音がして雨が降り出しました。
幕が上がって、しずくの場面です。ともちゃんは、練習の時にこのドングリを金だらいの中にポトンポトンと落とす音に過敏に反応して、音が響くたびにビクっとなりました。それで「この時だけは、舞台の袖で耳を塞いでいて、刺激が強くならないようにします。」ということで、この後のザラザラザラとビーズが落ちる音(この音は好き)のところで舞台に顔を出すことになっています。今、ともちゃんは舞台の袖に隠れていますが、ウィーンとハウリングを起すマイクの中で、「ウフフフーウーフフフ」とともちゃんの笑い声が響き渡りました。
実は、衣装の上に、ともちゃんはピンマイクを付けていました。「ともちゃん、よく笑うから、声をみんなに聞かせてや。」ということと、隣で生演奏して下さる先生のクラリネットの音を拾うためです。ともちゃんは、ドングリを落す音にはやはりビクっとするものの、その後おかしくなって大きな声を出して笑っているのでした。姿を出さずに、思いがけない声だけの登場に、お母さんは「ともちゃん、今度は声優さんやな。」ととても愉快になりました。文化祭の劇の女優さん、補装具や車椅子を作った時の記録写真のモデルさん、そして今度は声優さんです。
マイクの調子が悪い(ハウリングを起す)ので、その後スイッチを切られてしまったのは残念でしたが、ともちゃんも笑顔を振りまきながら舞台に上がってきました。でも、今度は残念な出来事が起りました。車椅子に座っているともちゃんは、側湾の強い足腰が痛くなったのです。側湾が強くなってから、微妙な車椅子のセッティングの具合や座り具合、長時間座っている時など、時々足腰が痛くなることがありました。今回は笑うことで筋肉に力が入って、体のゆがみがよけいに強くなって、痛みが起っているようです。
しずくの歌も、真横で演奏してもらうクラリネットの音色も、練習の時はニコニコ楽しんでいたのに、笑うと痛くなって顔をしかめてしまいます。先生が車椅子の上からともちゃんの肩をゆるやかに押えてくれるので筋緊張は一旦は治りますが、ともちゃんはもうそれどころではありません。しずくが集ってできた海で、巨大なビニール袋に風船をたくさん詰めたフワフワの鯨に触れた時も、落着かないままともちゃんは舞台を降りました。
舞台の下に降りてきたともちゃんは、車椅子から降りて先生に抱っこしてもらって、ほっとうれしそうです。ともちゃんが抱っこでリラックスしている間、舞台の上では深海の場面があり、水が吸収された大地からは友達がボタンを押して草の芽が芽吹きました。芽はどんどん成長して、別の友達が吊下げられたザルを揺らして花びらを散らすと、一面に花が咲きました。そう、ともちゃんの好きな花祭りの歌の場面です。
ギターの伴奏でジャカジャカと演奏が始まると、ともちゃんは大喜びしています。抱っこしてもらって、足腰の痛みを全く気にしなくていいので、屈託のない満面の笑顔を見せています。舞台の下の暗がりの中での笑顔なのですが、お父さんもお母さんもちゃんと見ていました。お母さんは、暗がりの中写らなくてもいいからとカメラのシャッターを切ろうとしましたが、オートフォーカスのカメラなのでシャッターが下りず断念。お父さんのビデオには、花祭りの音楽とともに真っ暗な客席が映っていました。
アンコールにゆずの「スマイル」の曲がかかって、ともちゃんは再び車椅子で舞台に上がりました。そして、今度はニッコリと微笑んで、舞台を降りてきました。毎日ともちゃんと生活していて、ともちゃんのことは何でも知っているつもりの両親ですが、年中行事の度に改めてともちゃんの新しい表情や成長を目の当りにします。去年は舞台の上での緊張した表情でした。今年は大好きな歌があることを教えてくれました。
「ロックバンドのライブなんかやったら、ともちゃんには刺激が強すぎますよね。」と先生がともちゃんがどの場面で参加できるかを考えて下さっています。お姉ちゃんの好きなバンド系の曲には馴染みがあるものの、大きな音量で激しく響くライブでは、ともちゃんはビクビクするでしょう。それで、全体会は様子を見てということにして、分科会を中心に参加することにしました。一昨日頑張って舞台に出た後、1日休養を取ったともちゃんは、また張切っています。
お父さんの車でいつもの時間に登校したともちゃんは、まずは教室に入ってゆっくりと水分補給をしました。友達はみんな全体会に参加していて、静かです。「さっきまでは韓国舞踊をやっていたんですよ。今は何をやっているかな。」と言う先生の言葉に惹かれ、お母さんは一人で体育館に様子を見に行きました。各高校を代表して、様々な課外クラブが参加して舞台発表をしています。ダンスあり、バンド演奏あり、高校の文化祭独特のパワーの炸裂する舞台に、養護学校の友達も楽しそうです。やはり同年代の舞台には響くものがあるようです。
「一応バンド演奏は済んだので、ちょっと様子を見に行ってみてもいいかもしれません。」、ちょうど水分補給も済んだので、ともちゃんは体育館に向かいました。体育館ではどこかの高校の吹奏楽部が「タッチ」を演奏していました。他の車椅子の友達は、舞台が見やすいように前の方に陣取っているのですが、ともちゃんは、刺激が強すぎないように、もしびっくりするようなら、こっそりと出て行けるようにと、そっと一番後の席に着きました。ともちゃんは、慣れない雰囲気に最初は緊張した表情をしています。でも、吹奏楽の生演奏は刺激が強すぎてイヤということは全くありませんでした。
客席ではニワトリの着ぐるみを着た生徒がインタビューに回って、愉快な気分を盛上げています。ともちゃんなりの場の雰囲気をつかむ時間を経て、ともちゃんの顔に笑顔が浮かびました。大丈夫、もう心配はありません。本来お祭大好きのともちゃんなので、楽しい雰囲気はしっかりと感じ取れたのでしょう。全体会のプログラムは最終へと進み、養護学校の高等部11組から15組のグループによる劇になりました。ともちゃんはすっかり盛上がって、ギャハハギャハハと楽しそうに笑っていました。
分科会に分かれるために音楽室に移動しても、ともちゃんはご機嫌でニコニコしています。分科会では、それぞれの障害に合せて無理なく一緒に楽しく交流が出来るようなプログラムが(実行委員会により)用意されていて、ともちゃん達重症心身障害児のグループは「音楽遊び」です。「音楽遊び」の分科会をさらにA、Bの2つに分けて、ともちゃんは「A:シャボン玉」の方に参加します。この分科会はともちゃんの教室、1組で行われ、ミルクの注入の時間になるともちゃんは、注入をしながらというスペシャルコースです。
最初は様々な音楽を聴いて楽しみました。本当はともちゃんの先生が演奏するはずのクラリネットの曲を初見で演奏して下さったのは、さすがの現役吹奏楽部生。ギターの弾き語りで熱唱して下さった生徒会長さん。ともちゃんは先生に抱っこしてもらって、いつものようにリラックスして生の演奏を楽しみました。養護学校からは、2組の先生のギター伴奏で30年前の歌をみんなで歌いました。体育館の全体会でさえ、雰囲気にのまれることなくノリノリだったともちゃんは、教室では初めて会う高校生にも緊張することなく、とても楽しそうです。
次は文化祭の劇にも出てきたシャボン玉のコンテストです。養護学校の生徒と、交流に来てくれた高校生がペアになって、実行委員が作った様々な型枠を使ってシャボン玉作りに挑戦しました。ともちゃんとペアになってくれたのは、K高校のTさん、女の子です。1回目は「大きかったで賞」、大きいシャボン玉を作ることを競います。Tさんが目の前で作ってくれるシャボン玉を先生に抱っこしてもらっているともちゃんが見ています。でも、大きく作るのは難しく、審査員の看護師さんが選んだのはMちゃんチームでした。
2回目の「たくさん出たで賞」の審査員はともちゃんのお母さん。今度は小さいシャボン玉がいくつも出ます。お母さんの審査結果に、ともちゃんは真剣に耳を傾けています。けれども、馴染みのある声で発せられたのはY君チーム。ともちゃんは、思わずお母さんがいる後を振返り、目で訴えていました。「なんで私のチームと違うん。たくさんシャボン玉出たやん。私のお母さんやねんから、私のチームを選んでくれな。」、「ごめんなー。もうちょっとの差やねんけど、Y君とこの方がたくさん出てん。」、今回のコンテストはみんな僅差でしたが、身内だからと言って贔屓はできません。
最後のコンテストは「スマイル賞」。ペアの高校生に作ってもらったシャボン玉を見て、ニッコリと笑顔が出ると優勝。ペアのコミュニケーションが重要な賞です。これは、ともちゃんにも勝算があります。シャボン玉を作るTさんは、先生の「名前を呼んであげて」というアドバイスに応えて、やさしく「ともちゃん、見て」と何度も声をかけてくれました。声をかけてもらったともちゃんは、うれしくて楽しくて、タイミングよくパアッと笑顔を見せてくれました。養訓担当の先生の審査で、ともちゃんの「スマイル賞」が決定しました。ともちゃんは表彰状とチョコレートでできた(ともちゃんは食べられないけれど)メダルをもらいました。
初めて参加した「交流のひろば」、ともちゃんはたくさん楽しむことができました。また一つ新しい経験が増えました。健常児との交流行事というと、ともちゃんにとっては経管栄養、在宅酸素になる前に行っていた地域の小学校(お姉ちゃんの小学校)との交流学習以来のことです。幼いと思っていたともちゃんが、高校生の舞台発表の雰囲気の中に溶け込んで笑っているのを見ると、お母さんは改めて「ともちゃんも高校生なんだ。」と元気で成長したことを嬉しく思いました。
年齢がいくに従ってそれぞれに活動の場が異っていくので、ともちゃんも同年代の健常児と出会う機会が少なくなっていました。けれど、このような機会が持てるのは、ともちゃんにとってもいつもとは違った楽しい刺激になるし、養護学校に来て下さった高校生にはともちゃん達のような重症心身障害児の存在を知って、重症心身障害児もまた同じ高校生として人生を楽しんでいるのだということを知ってもらえることになるので、とてもありがたい機会だとお母さんは感謝しています。
ともちゃん、元気に過ごしていると色んな行事に参加できて、どんどん世界が広がるね。2学期も、幸いにしてたくさんの行事に参加できました。さあ、次はどんな体験ができるかな。楽しみだね。
 ともちゃんは、京都に引越してきて初めての冬を迎えています。家の外は、京都西山からの冷たい風が枯れた田畑に吹付けてきます。この冬は昨年末から記録的な寒さで、ともちゃんは窓越しに激しい吹雪や一面の雪景色も経験しました。でも、ともちゃんは新しいお家の中で、床暖の上にともちゃんの定位置である布団を敷いて、ぬくぬくで過ごしています。
ともちゃんは、京都に引越してきて初めての冬を迎えています。家の外は、京都西山からの冷たい風が枯れた田畑に吹付けてきます。この冬は昨年末から記録的な寒さで、ともちゃんは窓越しに激しい吹雪や一面の雪景色も経験しました。でも、ともちゃんは新しいお家の中で、床暖の上にともちゃんの定位置である布団を敷いて、ぬくぬくで過ごしています。
「交流のひろば」までは、順調に行事に参加できたともちゃんでしたが、この後すっかり冬籠りモードに入ってしまいました。ともちゃんの冬籠りモードは、特にどこかが悪いというわけではないのですが、身体の活動性が低下しているという感じで、ボーッとしていることが多くなり、ウトウトと何度も昼寝をする状態なのです。お粥ペーストを口に入れてもモグモグごっくんをしてくれないので、なかなか食事が進みません。一日かけて、食べること、寝ること、体を清潔にすること、排泄することなど生きていくための基本的なことだけを行い、ゆっくりと過ごしています。
冬籠りモードに入ってしまうと、お出かけや登校をする時間が物理的にも体力的にも無くなります。ともちゃんにとっては例年のことで、ここでドカンと大きく体調を崩すことがないように、体調に注意をして春になるのを待つのです。しかし、今年度はともちゃんは訪問学級に在籍しています。体調が比較的よい日には、ともちゃんの遅い朝食が終った頃に訪問学級の先生に来て頂きました。訪問学級のありがたさを一番実感する季節です。担任の先生と一緒に養生・訓練の先生が来てくださる日もあって、リハビリの訓練もしてもらいました。
ともちゃんの体調によっては、先生に来て頂いても、ボーッとしている時もありますが、先生に抱っこしてもらい、声をかけてもらって、文化祭で馴染んだ音楽を聞くと何度も笑顔が出てきます。ともちゃんにとって、とても楽しいひとときです。授業中たくさん笑っていて、「あれっ、元気やん。」とお母さんが思っていたら、先生が帰られた途端、クターッと寝入ってしまったこともありました。ついつい、張切ってしまうともちゃんです。この冬の訪問学級の授業では、文化祭の劇をイメージして、指に絵具を塗って絵を描きました。それが年賀状にも、3学期に行われる作品展に出品される作品にもなります。
終業式も訪問学級で行ってもらいました。冬籠りモードに入ってからは週1回程度の訪問学級で、2学期の出席日数は26日でした。ともちゃんが絵具をぬたくって作った年賀状葉書も完成して、2枚頂きました。ともちゃんは、お母さんと一緒にその葉書を使って、お姉ちゃんとお父さんに年賀状を書きました。年賀状を書く時も、ともちゃんは嬉しそうに張切っていて、たくさん声が出ていました。お母さんが、書く文章を読み上げて、「これでいいか。」とともちゃんに尋ねるのですが、文章によって、知らん顔をしているものも、「ハハーン」とニコニコするものもありました。お母さんに一緒にサインペンを持ってもらって、ともちゃんが選んだ文章を書きました。
年が明けても、ともちゃんは家の中でマイペースで過ごしていますが、お正月は両親と囲碁をしました。お父さんもお母さんも囲碁は全くの素人で、小学生のようにアニメの影響で囲碁を始めました。家の中に籠っていることが多いともちゃんの家庭では、スカイパーフェクトTVと契約をしてCS放送を見られるようにしています。その中にアニメ番組ばかりを放映しているキッズステーションというチャンネルがあるのですが、たまたまそこにチャンネルを合せた時に「ヒカルの碁」というアニメを再放送していました。
夕方の6時半、夕食時に放映しているので、ともちゃんが冬籠りに入った頃から、よくチャンネルを合せていました。ちょうどお姉ちゃんが予備校から帰って来る頃で、仕事が早く終った時にはお父さんも帰って来て(引越してお父さんの職場が近くなったからこそ、この時間に帰れるようになったのですが)、家族で賑やかに食事をしながら、みんなで見ているためもあってか、ともちゃんは「ヒカルの碁」が他のアニメよりも好きなようです。始まるとニコニコと明らかに嬉しそうにして見ていました。
そんな折、年末に買物に行ったお母さんが、通常の盤面の4分の1のサイズの初心者用(子供用?)の囲碁セットを買ってきました。子供向けの入門書も付いているものです。例年、お母さんは、ともちゃんが冬籠りでも家の中で楽しめるようにと、ボードゲームなどをよく買って来ていましたが、それが今年は「ともちゃんが喜ぶかな。」と囲碁セットにしたのです。ともちゃんが囲碁をするには、まず両親が入門書を読んでルールを知らなければなりません。とりあえず、お父さんもお母さんも、初心者の小学生が休み時間に遊ぶ程度には、囲碁のルールが分るようになりました。
両親のどちらかがともちゃんを抱っこして、ともちゃん連合として何度も対局しました。ともちゃんは、最初に先手後手を決める時に碁石を握らせてもらって「握り」をしたり、碁石を持たせてもらったり、「ともちゃんが言うところに打つで。」と打ってもらったりして、一緒に雰囲気を味わいました。定石も何も知らないヘボ碁ですが、両親は結構面白がって何度も対局していました。ともちゃんは「ともちゃん、囲碁してるねんなー。」と声をかけてもらうと嬉しそうです。結果はお父さんの圧勝でした。ともちゃんは、ずっとお父さんに抱っこされていたわけではないので、内心悔しい思いをしていたかもしれません。
その夜、ともちゃんは、大きな声で笑ったり、抱っこしているお母さんの顔をのぞき込むようにして「アーアー」と大声で話しかけたりして、興奮して上機嫌です。両親から「早く寝な、あかんよ。」と言われても、遅くまで眠りませんでした。こんなことは珍しいことで、昼間によほど刺激の強いイベントやお出かけでもない限り、滅多に起こりません。この日の昼間は、いたって普段通りに過ごしていて、いつもと違うことは碁を打ったことくらいでした。でも、囲碁の最中は興奮した様子は特にありませんでした。ともちゃんの興奮は本当に囲碁が原因だったのでしょうか。「ともちゃん、TV見ながら、ずっと碁がしたかったんか。」、「碁が打ててよっぽど嬉しかったんか。」、ともちゃんがお正月に投げかけた大きな謎です。