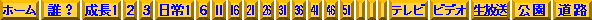ともちゃん
 の日常33
の日常33
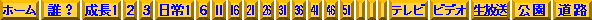
 の日常33
の日常33
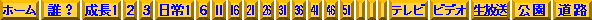
最初にタイトルの一覧があります。タイトルをクリックすると本文が読めます。
「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークをクリックするとそのタイトルに関する写真/動画/連組写真が見られます(「ビデオ」/「スライド」はファイルのダウンロードに1~2分かかります)。
本文の最初にも「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークがありますが、タイトル一覧と同じ写真/動画/連組写真です。
 25日(水)
25日(水)
 13日(月)
13日(月)
 20日(月)
20日(月)
「3学期終業式」
 1日(月)
1日(月)
 6日(土)
6日(土)
「小畑川散歩」
 12日(金)
12日(金)
「2006年度の初登校」
 14日(日)
14日(日)
「おうちの南方面を攻略」
 21日(日)
21日(日)
「バラ園にお出かけ」
 10日(土)
10日(土)
 16日(金)
16日(金)
「体験実習」
当日先生方が来られた時、ともちゃんは最初は硬い表情で、訪問学級が始ったという実感はわかないようでした。抱っこしてもらい、校歌を歌って学校の様子を伝えていただきました。「3学期の授業は、サツマイモの授業とサルカニ合戦の授業をします。」ということで、サルカニ合戦の絵本を読んでもらいました。先生が絵本を読み始めると、ともちゃんも目をキラキラと輝かせて、先生の声に合せて「おっ、おっ」と声を出し始めました。ともちゃんは、じわじわと訪問学級のことを思い出したようです。
ともちゃんは、すっかりいつものペースを取戻して、先生の読み聞かせを聞いていました。そして、お話の最後のサルがみんなにやっつけられるところで、先生の感情のこもったサルのセリフにケラケラと大笑いしていました。その後、リハビリの先生に少し訓練をしていただいて、「身体の緊張も強くなくて、いいですよ。」と言ってもらいました。順調な3学期のスタートです。夕方、お姉ちゃんやお父さんが帰ってくると、ともちゃんはとても饒舌になり、大きな声で嬉しそうに「あーあーあー」とおしゃべりをしていました。「私もな、学校が始ってんで。先生が来てくれはってんで。それでな! それでな・・・」
通常の訪問授業も始りました。始りの会(訪問学級でも、登校した時と同じように最初に歌を歌って、名前を呼んでもらいます)で名前を呼ばれると、ともちゃんは「フン」と返事をしていたそうです。今回もはりきっています。新年なので、まずは縁起物の獅子舞から始りました。色々な楽しいものが詰っている先生の教材荷物の中からマペットの獅子舞いが現れて、ともちゃんの頭をカブカブしてくれました。ともちゃんは「こいつ何やろ。」と不思議そうな顔をしていました。
今回もともちゃんが好きなサルカニ合戦の授業がありましたが、ここでまた、新しい発見がありました。サルカニ合戦のテーマソングはTVドラマ「水戸黄門」の歌の替歌なのですが、ともちゃんは、この歌が大好きなのです。タンバリンを木琴のバチで叩いてリズムを取りながら歌を歌ってもらうと、嬉しそうにギャハギャハ笑っています。先生から「ともちゃんは水戸黄門を見ているのかな。」と尋ねられたのですが、養護学校に入学して以来夜は7時に寝室に行くことを目標としているともちゃんは、夜のTVは見たことがありません。
ただ、ともちゃんが赤ちゃんだった頃、幼かったお姉ちゃんは時代劇が大好きで、「水戸黄門」も「大岡越前」も「暴れん坊将軍」もみんな見ていました。そのころの記憶が心の奥底に残っていたのでしょうか。それよりも、黄門さんの歌と言えば、お父さんが「マンマシ(ご飯を食べること)の歌」と称して、ともちゃんが小さい頃から「人生楽ありゃ苦も(雲)あるさ、雲があるから雨が降る、あーめがふーるうから米でーきーる、こーめができるから飯食える。」と変な替歌を歌ってくれるので、ともちゃんは「あっお父さんのおかしな歌や。」と思ったのかもしれません。いずれにせよ、ともちゃんの好きな歌がまた一つ分かったことは嬉しいことです。
最後は書初めです。「ともちゃんに漢字一字で書初めをしてもらうのですが、何という漢字がいいでしょう?」とお母さんは先生に相談されました。クラスメイト達はそれぞれに思いを込めて、「笑」「輪」「穏」と書くそうです。「ちょっと、画数は多いのですが、『楽しい』の『楽』がええかなと思うのですけど。」、ともちゃんの座右の銘は「人生を楽しく」。「今年も楽しいことがいっぱいありますように。」、先生に腕を持ってもらい、手を動かしてもらって「楽」と書きました。字を書いている間、ともちゃんは楽しそうに大笑いしていました。年末に、お姉ちゃんに年賀状を書いた時も笑い転げていたので、最近字を書かせてもらうのが楽しいようです。
3学期は、未だ登校はせず、ともちゃんの体調に合せて週1~2回、こんな調子でずっと訪問学級を受けています。朝食がスムーズに食べられるということを先生に来ていただく条件にしているので、「今日はご飯食べられへんから、ゆっくりしようか。」とお母さんに言われて、ともちゃんがつまらなさそうな顔をしている日もあります。逆に、「今日は訪問に来て下さい。」とお母さんが先生に電話している声を聞いて、うれしそうに声を出していることもあります。ともちゃんは、やはり黄門さんの歌が大好き。サルカニ合戦の授業の中では、他にもトライアングルの音やウッドブロックの音で笑顔を見せてくれたり、「臼」の場面で鳴らしてもらう不気味な音には不安な顔をしたりと、世界が広がっています。
 ともちゃんは相変らずの冬モードで、冬籠り生活が続いています。ボーッとして朝食のお粥を食べるのに時間がかかるので予定がずれ込んでくる上に、昼食のお粥もゆっくりペースなので、1日分の食事が全部食べられる日は時々しかありません。ともちゃんの栄養摂取手段は、鼻腔からの経管栄養と経口でのお粥ペーストの2本立てなので、こういう時には経管栄養の有り難さを身にしみて感じながら、マイペースで過ごすことにしています。
ともちゃんは相変らずの冬モードで、冬籠り生活が続いています。ボーッとして朝食のお粥を食べるのに時間がかかるので予定がずれ込んでくる上に、昼食のお粥もゆっくりペースなので、1日分の食事が全部食べられる日は時々しかありません。ともちゃんの栄養摂取手段は、鼻腔からの経管栄養と経口でのお粥ペーストの2本立てなので、こういう時には経管栄養の有り難さを身にしみて感じながら、マイペースで過ごすことにしています。
冬籠り自体は例年のことなのですが、今年特に気になることは、体の変形が痛くて夜の眠りが浅くなったことです。夜中に眠りが浅くなって、ンーッと痛そうに顔をしかめて、身体を周期的にビクッビクッとさせることがよくありました。ともちゃんには側湾があって右側の脇が縮んでいて、その上さらに骨盤が右側が後ろ、左側が前にねじれています。低反撥素材で体の形に合せて作った詰め物を使って横向きに寝ているのですが、どうも寝ている間に体がずれてきて、床からの圧迫で体の歪が強くなるようです。
ともちゃんの三次元的にねじれている体は、うまく抱っこすると圧迫されずにリラックスできて、ともちゃん自身が楽になるようなので、こういう時は抱っこして寝かせることにしていました。最近は、幸いにも体が痛くて眠りが浅くなることは少なくなりましたが、ともちゃんの成長と共に体の歪みが進んできていることは避けようのない事実です。関節が硬く固まってしまわないように、少しでも動かせる範囲が広くなるように、リハビリの訓練で関節を伸ばしていこうと思います。それとともに、特定の部位が圧迫されないように、体の大きくなってきたともちゃんの夜間の体位変換(寝返り)も考えてなくてはなりません。
訪問学級では、サルカニ話の黄門さんの歌に相変らずニコニコ笑顔で「この歌好きやねん」と表現してくれます。それを見た先生が「今、水戸黄門をTVでやっていますよ。」と教えて下さいました。お母さんは、ともちゃんがTVの水戸黄門の歌にどんな反応をするか見てみたくなりました。早速録画して、ともちゃんと一緒に見たのですが、なかなかオープニングが始りません。「黄門さんの歌はエンディングやったっけ?」と今度は最後から戻ってみました。それでもなかなか出てこなくて、始まってから10分後くらいにかかる黄門さんの歌を見つけた時には、間の悪いことにちょうどともちゃんが硬直の発作を起こしてしまいました。
硬直しているともちゃんにとっては、テレビで鳴っている曲なんて、もうどうでもよくなっていました。硬直発作の方はいつも通りのもので、すぐに治まったのですが、最初の印象が良くなかったのかともちゃんはTVの歌には特別な興味を示すことはありませんでした。お母さんが「ほら、黄門さんの歌やで。」と声をかけると、その声に反応してニコニコと笑いかけてきますが、TVの音に反応している様子はありませんでした。やはり、肉声(生の迫力)に勝るものはないのでしょう。授業で歌ってもらう先生の歌は、タンバリンの音と先生の声で、ともちゃんにとって独特の魅力と楽しい雰囲気があるようです。
サルカニ話の授業で臼のテーマ曲になっている不思議な楽器から奏でられる怖い音の正体が明らかになりました。お母さんもずっと不思議に思っていたので、次の訪問授業までその楽器をお借りしました。先生がバリ島で買求めた楽器(名前は不明)で、糸電話の様に筒の片方の底面に樹脂の板が張付けてあって、樹脂板の真ん中に針金を直径1cm弱のコイル状にした長さ30cmくらいの「しっぽ」が付いています。楽器を軽く振ると、コイルの「しっぽ」が波打って揺れて樹脂板を複雑に振動させるので、ポワヮヮヮンと不安げな音が鳴るのでした。お父さんとお姉ちゃんも珍しがって何度も鳴らしているうちに、ともちゃんはこの音にも慣れてきて、全く平気になりました。笑って聞いています。
2月16日、17日はともちゃんの養護学校の高等部の作品展が市の産業文化会館でありました。ともちゃんもたくさん出品してもらいました。文化祭で演じた「うたがみえる、きこえるよ」から大地や花祭りをイメージして、絵具をともちゃんの指につけて塗りたくって描いた絵や、それを布に転写してウォールポケットに仕上げてもらった作品、ともちゃんは日帰りで参加した宿泊学習で作った陶芸の箸置きやお皿、1学期に母の日に向けてこちらも指で塗りたくって描いたピンクのカーネーションを張った鉛筆立て、どれも力作です。
友達は学校から見学に行くのですが、冬籠りのともちゃんは残念ながら不参加です。作品展は一般の人の参加も歓迎していて、初日は夜の7時まで開催していますし、文化産業会館はお父さんの通勤経路にあります。それで、ともちゃんに代ってお父さんに写真を撮ってきてもらいました。思えば前の学校も3学期に作品展があったのですが、ともちゃんが冬籠りモードに入るようになってからは全く参加できませんでした。作品展が終って、返却してもらった作品を家族で鑑賞しました。中学、高校と美術部で過ごしたお姉ちゃんに「この微妙なマーブル模様の形がええわ。」、「このお皿には和菓子を置いたら、ちょうどええなあ。」とたくさん褒めてもらって、ともちゃんは得意そうでした。
ともちゃんが冬籠りをしている間に、窓の外は雪がちらついたり、菜の花畑の菜の花がほころんだりと三寒四温を繰り返し、3月13日を迎えました。ともちゃんが、この京都の地に引越して1年が経ったことになります。この1年大きく体調を崩すこともなく、新しい学校にもすんなりと慣れて、驚くほど順調に色々な行事に参加できたし、冬籠りの間は訪問学級を楽しみに過ごすことができました。ともちゃんの学校生活がスムーズに引継げるようにご尽力下さった先生方、健康管理していただいた病院の先生やスタッフの方々に感謝しつつ、成長したともちゃんの適応力をうれしく思う毎日です。
3学期はずっと訪問学級で過ごしてきたのですが、3月も半ばになると、ともちゃんも冬籠りからそろそろ目覚める時期になります。それで、昼食会に参加することを目標に、生活のリズムを整えるようにしてきました。今年の春は、少し日差しが春めいてきたかなと思ったら、雪が降ったり、風が強かったりと、なかなか思うように暖かくなってくれません。あまりに寒い日なら、それまでずっと家の中で過ごしてきたともちゃんをいきなり屋外に出して、体調を崩させはしないかと、お母さんは心配していました。
ともちゃんの方は、天気も気候も関係ありません。先生とお母さんが話していた時から目を輝かせて、笑っていました。その上「元気にしていたら、終業式には学校に行くよ。」とみんなに話してもらっていたことが、だんだんとしみてきて、意欲満々です。昨日も、お姉ちゃんから「明日は、ともちゃんが学校に行って、おネエがお家に居るねん。(ともちゃんが留守番で、おネエが学校に行っている)いつもとは反対やろ。ええなぁー。」と何度も聞かされて、夜にお父さんと寝室に行っても興奮してギャハギャハ笑っていました。
お姉ちゃんはともちゃんの春のおしゃれに気を配ってくれています。自分も服が欲しいお姉ちゃんは、ともちゃんにも「いつもは実用的なズボンやフリースでも、お出かけ用にこじゃれた服も欲しいやんな。」と話しかけています。ともちゃんもニコニコして、「はん」と答えていました。先日、お姉ちゃんがお母さんと梅田に出かけた時、きれいなピンク色のワンピースを見つけて、「ともちゃんは、こういうワンピースをズボンの上から着たらかわいいと思うねん。」、ともちゃんへのおみやげになりました。その後、お祖母ちゃんと買物に行ったお姉ちゃんは、この洋服に似合う、桜の花のついた髪くくりゴムを買ってきてくれました。
昨夜はギャハギャハしていて、いつもより1時間も遅く眠ったともちゃんは、少しゆっくりめに目覚めました。食事もマイペースでしたが、全部食べました。終業式には間に合いませんが、その後の昼食会なら、十分に間に合います。今日は少し寒いという天気予報を心配して、ワンピースの下には白いフリースの上下を着て、その上にはキティちゃんのワッペンの付いたパーカーを羽織りました。もちろん、前髪は桜の花のゴムで、お姉ちゃんに束ねてもらいました。久しぶりの登校なので、お母さんはミルクの注入の用意など、ともちゃんの登校時の持物を忘れないように準備しました。
いつも登校の時にするようにタクシーを呼んで、ともちゃんとお母さんが乗込みました。お母さんが車椅子を折りたたんでタクシーのトランクに乗せる間、お姉ちゃんが座席でともちゃんを抱っこしていてくれたので、こちらも久しぶりのお母さんは、落着いて行うことができて、助かりましたました。タクシーを待っている間は風が冷たく感じられたのですが、タクシーの中にさす日差しはすっかり春の光で、冬籠りからの目覚めの季節であることを教えていました。
教室には、友達も、お母さん達も揃っていて、豚汁を作ったり、リンゴを剥いたりと準備を進めていました。ともちゃんは教室の雰囲気をつぶさに感じて、ごきげんでハハアーと声を出して笑っていました。やっぱり学校は大好きです。寄宿舎の入所を体験してきたNちゃんの元気な顔、顔を持ち上げてウフーンと声を出して笑ったKzちゃん、いつもはボーイッシュなのに今日はスカートでおしゃれしているKtちゃん、女の子が4人揃った教室は華やかです。おしゃべりはしなくても、友達の気配は十分に感じ取ることができて、賑やかなことが好きなともちゃんにとって、嬉しい時間です。
ともちゃんは、みんなの居る教室で先生に抱っこされて、一足先にミルクの注入を始めました。口から食事がとれる友達は、お母さん達と同じようにお弁当を頼んでいます(お子様仕様ですが)。ともちゃんのお母さんは、みんなの邪魔をしないように一応手伝いながら、友達のお母さん達の雑談に加わっていました。京都に引越してきて、新しい学校の友達のお母さん達とも、たくさん知合いになりたいと思っていました。けれど、なかなかお母さん達の輪の中に出かけていく機会がありませんでした。お母さんは、これからもこんな形でぼちぼちと仲良くなっていけたらいいなあと嬉しく思っていました。
みんなのお弁当も届き、食事をしながら、今年度の感想と来年度の抱負を述べる段になりました。ともちゃんの場合は「こちらに引越して来て1年、元気に無事に楽しい学校生活ができて良かったです。春から秋の登校と、冬の訪問で、ともちゃんにはちょうどいい『訪問』学級でした。春から秋にかけては、行事にもたくさん参加できたし、来年度もこの調子で勉強したいです。それから、修学旅行には、特別に日帰りですけれど、是非参加したいですね。」とお母さんが言いました。本当にこの通りです。
ともちゃんの今年度の出席日数は、登校が23日、訪問が39日の合計62日でした。訪問のお陰で3学期も14日も授業に出席できました。一方、一足先に家に届けてもらったともちゃんの高等部1年次のアルバムには、入学式から始って、春の散歩、イチゴの学習、チームデビュー、宿泊学習に日帰りで参加した陶芸のお皿作りなど順調に行事に参加し、運動会、文化祭の練習から本番、日頃の授業風景や朝の会まで、2学期にはすっかりクラスの友達の中に馴染んでいるともちゃんの姿があります。3学期は訪問学級で勉強している様子が写っています。訪問で行って頂いた機能訓練の写真もあります。
改めて1年を振返ってみると、新しい学校で、思っていたよりもたくさんの新しい経験を積重ねることができて、嬉しい限りです。アルバムの最初のページの大きな写真「2005年度のとっておき」は秋の散歩で学校の花壇のコスモスの中で笑うともちゃん。ともちゃんの健康管理をきちんと行って、気候のいい間は来年度もたくさん登校させてあげられるようにしようと、お母さんも決意を新たにしています。帰りのタクシーの中から見ると、学校の周りも菜の花が満開でした。タクシーが家の前に止り、留守番をしていたお姉ちゃんに手伝ってもらって、車椅子に乗って家の中に入りました。いつもはお姉ちゃんの帰るのを待っているともちゃんは、登校したことをお姉ちゃんに自慢するかのように、とてもごきげんでした。
春めいてくるのに従って、季節の変り目のけいれん発作はあるものの、お粥を食べ終るのに必要な時間がはっきりと短くなっています。冬の間は、口から食べるお粥を全部食べられる日はあまりなかったのに、この頃は当り前のように全部食べています。冬の間、食べられない日が続くと心配になる時がありますが、春が来るとちゃんと復活するのがともちゃんの冬籠りです。
先生に来ていただいて、待ちに待ったともちゃんは嬉しそうに笑っています。「今まで先生が来てくれたはったのに、この頃来てくれはらへんようになってしもた。でも、また来てくれた。嬉しいわ。」と訪問学級の楽しさを思い出しているのかもしれません。高等部2年生になったともちゃんのクラスは2組。1年生の女の子、2年生の女の子と男の子、3年生の男の子、そしてともちゃんの5人のクラスです。みんな昨年度は2組か3組だった人達で、ともちゃんは初めて同じクラスになります。
養護学校は小学部から高等部まであるので、転校しなかったら12年間を共に過ごすことになります。けれども、高等部から転入してきたともちゃんは3年間しか一緒に学校生活を送ることができません。卒業後もずっとこの場所で生活していくわけですから、この3年間の中で、できるだけたくさんの友達にともちゃんもこの学校に在籍していること、この地域で生活していることを知ってもらい、顔や名前を覚えて欲しいとお母さんは願っていました。ですから、新しいクラスメイトができることは、うれしいことです。
新しいクラスメイトは、ゆっくりと歩くことができたり、自分で車椅子を動かすことができたりと活動的な人が多いので、去年のように周りの雰囲気を感じながら一緒に寝転がったり、一緒に注入したりというのとは、また違った関わりが持てるかもしれません。ともちゃんのお母さんも、こちらに引越してきて、たくさんの障害児のお母さん達と知合いになりたいと願っています。昨年度の昼食会のように、新しいクラスメイトのお母さん達と自然に知合える機会があるかも知れません。
始業式から1日おいて、ともちゃんは訪問の機能訓練を行いました。訓練の方も順調なスタートでした。2年生になったので、朝の始りの歌も、終りの歌も変りました。訪問学級でも、始りと終りの時に先生に歌ってもらいます。どちらも、good morningとかsee you tomorrowとか、英語が歌詞に入っているところが、ちょっと上級生になった気分にさせてくれる歌です。さっそく新しい朝の歌を聴いて、ともちゃんはうれしそうにしていました。リハビリの先生に訓練をしてもらいながら、お母さんと担任の先生が修学旅行の話をしていると、しっかりと聞き耳を立てていて、「私も楽しみやねん。」と言うように「アハハン。」と笑っていました。
そろそろ登校したいなと思っていた頃、体は丈夫なはずのお母さんが珍しく風邪を引いてしまいました。そうなると、いつもお母さんに抱っこしてもらっているともちゃんに感染しないはずはありません。5月の連休を前にして、ともちゃんは熱を出してしまいました。登校どころではなくなり、連休も病院に日帰りで点滴に通いました。この4月から、ともちゃんのかかりつけの病院がまた変っていて、新しい病院に通っていました。京都に引越した時から、こちらでお世話になっていた先生が東京の病院に転勤になられて、新しい先生を紹介して頂いたのです。
新しい病院に行く時には、様子が分らずに段取りが悪かったりすることがあるのですが、今回お父さんの車で何度も来ることになったので、今度ともちゃんとお母さんが2人で神経外来に来ても迷わずにスムーズに受診できる自信がつきました。ここは新しく受診する病院であることを忘れて、診察の時にともちゃんの平熱が高いことや、普段の様子を言忘れて病状を説明してしまって、翌日もう一度ともちゃんのことを説明し直すなどの失敗もありました。何人もの先生にお会いして、看護師さんやスタッフの方にも顔や名前を覚えて頂きました。今回の風邪のおかげで、新しい病院に馴染むことができました。
今日は熱も下がったのですが、この状態でもう一度診て頂いて、とどめの抗生剤をもらうために4度目の受診です。元気になってきたともちゃんは、いい天気が恨しそうです。薬が出来上がるのを待つ間に、少しだけ病院の近くの駅前商店街を散歩しました。この街にはお父さんの会社の一拠点もあって、お父さんは以前はここに通勤していたし、今もしょっちゅう来ています。お父さんにとっても、買物でよく来るお母さんにとっても、お馴染みの商店街です。お母さんが自分の買物に100円ショップに立寄ったので、ともちゃんもここでキティちゃんの巾着を買いました。
 熱が引いた後も痰が増えているともちゃんは、無理をせず連休中もずっと家で静養していました。窓から差込む5月の日差しと、連日TVで放映される連休の交通機関の混雑状況から、ともちゃんは「私もお出かけしたかったのに。」と風邪の元凶であるお母さんを恨んでいるかも知れません。連休も明日で終り。その上明日の天気予報は雨だというので、今日は少しだけ家の近くを散歩してみることにしました。
熱が引いた後も痰が増えているともちゃんは、無理をせず連休中もずっと家で静養していました。窓から差込む5月の日差しと、連日TVで放映される連休の交通機関の混雑状況から、ともちゃんは「私もお出かけしたかったのに。」と風邪の元凶であるお母さんを恨んでいるかも知れません。連休も明日で終り。その上明日の天気予報は雨だというので、今日は少しだけ家の近くを散歩してみることにしました。
ともちゃんの家の東側と南側に向う方向には急な坂道があって、その上坂の最大傾斜が進行方向に向いていない箇所もあるので、車椅子でお出かけするのは危険な気がして避けていました。養護学校がある北西方面には坂道はないので、すでに何度も散歩に出かけています。今日は両親がしっかりと車椅子をガードしながら坂道を上ることにして、家の東方向に出かけてみました。東側には小畑川というちょっとした川が流れていて、その堤防のところが高くなっているために、坂道を上らなくてはなりません。最近一人で買物に出たお母さんが、小畑川に鷺のような鳥がやって来て魚を捕ってところを見かけました。ともちゃんも一度川までいってみましょう。
堤防に上がる道はいくつもあるのですが、お父さんが愛用している堤防に対して直角に上がる坂道を利用することにしました。歩道のない住宅地の中の道ですが、車通りが少なくて、最大傾斜が進行方向であるというところが選択理由です。車椅子で散歩していると、たとえ歩道があっても幅が狭く、車道方向にも傾斜していると、逆にとても怖いことがよく分るのです。まずは、お母さんの用事で家の近所の郵便局に向かいましたが、ともちゃんは久しぶりのお出かけに、大喜びでニコニコしています。ともちゃんの笑顔に、両親もワクワクします。郵便局には、「たけのこは、ゆうパックで」という幟が上がっていました。竹の子が名産のご当地ならではの宣伝に、早速記念撮影です。
堤防に上がる時は、いつも別の道を自転車で立漕ぎしながら上がっていたお母さんは、お父さんの押す車椅子が横転しないように介添えしなければと気負っていたのですが、危ない目に遭うことなく意外にすんなりと堤防に上がれました。堤防沿いには小さな児童公園があって、その横にお母さんがいつも買物に行く時に渡る人道橋があります。「ともちゃん、橋渡ってみようか。鳥さんがおるかもしれへんで。」、川は橋の上流側で堰になっていて、その下流は浅いので、鳥が中洲の浅瀬に止って魚を捕っていたり、子供達が川辺に降りて遊んでいたりするのですが、今日は誰もいません。
向う岸を見ると、いつもは気が付かなかった川沿いの小道が続いています。川の反対側は竹林になっています。「きっと、私鉄の線路のとこで行止りやと思うけど、行けるとこまで行ってみよか。」とお父さん。竹林には、採る時期を逃してしまって大きく成長した竹の子がニョキニョキと生えていました。ともちゃんの街は竹の子の名産地で、連休になると駅前をはじめ街のあちこちで「朝堀り竹の子販売所」ができます。先程の郵便局の幟と、竹林の竹の子という取り合せに、思わず笑ってしまいます。
舗装されていない道をガタガタと、両脇に竹の子と川面を見ながら、犬を連れた人や自転車で通る人達と何度かすれ違い、私鉄の高架の下までやって来ました。高架下で記念写真を撮ろうとした時、ちょうど電車が通りかかりました。すると、それまでは機嫌良くしていたともちゃんの表情が、恐怖で凍付いて固まってしまいました。お母さんはあわてて駆寄って、ともちゃんを車椅子に座ったまま抱きしめたのですが、ともちゃんの表情はしばらく変りませんでした。思えば、電車が頭上を通る時の近付いて遠ざかる騒音はドキリとする怖さがあります。状況を理解できないともちゃんには可哀想なことをしてしまいました。
十分に抱きしめた後、ともちゃんに電車が通ったことを話して謝りました。表情も戻って、さあ散歩を続けます。お父さんの予想は大外れで、高架下を越えても道は続いています。バスが通る大きな通りまで、繋がっているようです。「この道がずっと繋がっているなんて、知らんかったなあ。」、ともちゃんと散歩すると何かしら新しい発見があります。大通りの近くになると、小畑川の川底もコンクリートで階段状に塗固められて、流れが浅くしてありました。これも新しい発見です。機嫌を取戻したともちゃんは、満足げにしています。帰りは大通りの狭い歩道を注意深く帰ってきました。ともちゃんの連休唯一のお出かけ、竹の子の里、小畑川散歩。1時間足らずのコースはおしまいです。楽しかったね。
天気予報では、晴天なので暖かくなるとのことでしたが、空は曇ったままです。肌寒いので、ともちゃんは起きた時に着込んだフリースをそのまま着ていきます。タクシーを呼んで乗込みました。学校の先生に「今、タクシーに乗りました。」と携帯電話で電話をして、運転手さんに「ガソリンスタンドのところで左折して下さい。」と通い慣れた道を案内しながら行くと、またともちゃんの登校シーズンが開幕したことが実感されて、ともちゃんもお母さんも嬉しくなります。
出迎えていただいた先生と一緒に新しい教室に向かいます。ともちゃんの新しいクラス、高等部2組は、去年のクラス1組の隣にできていました(教室の配置は、その年のクラス編成で変更されます)。友達が揃った教室に入ったともちゃんは、学校の空気を感じて笑顔を浮かべています。朝の歌の後、友達が一人ずつともちゃんのところに握手をしに来てくれました。一番に握手に来てくれて、ともちゃんの顔を下からのぞき込んで、はにかんで微笑んでくれたAちゃん。張切って握手してくれたM君。笑顔で歓迎してくれたKちゃん。いつもは積極的なのに、ともちゃんが新しい友達だと分っていて、自分で車椅子を動かすことができないくらいに恥ずかしがっていたI君。
ともちゃんは友達とのかかわりが大好きなので、嬉しくてしようがありません。ギャハハハ、ギャハハハと何度も何度も笑っていました。先生方にも一人ずつ目の前に来てもらい、自己紹介をしてもらうと、ともちゃんはご機嫌ですっかり新しいクラスに馴染んでいます。次はともちゃんが好きな「花祭り」の曲をかけながら、友達から一人ずつ造花をもらいました。昨年の文化祭でともちゃんが「花祭り」が大好きだったこと、このクラスには実際に花祭りの場面に登場して花を配っていた友達がいたことから、訪問学級のともちゃんが初登校してきた時の歓迎イベントとして、用意して下さったのです。
ともちゃんの喜ぶことをと考えて下さったことに、お母さんはすごく感激しました。でも、肝心のともちゃんは、友達との握手の時にギャハギャハ大喜びしすぎて疲れたのか、今はちょっと休憩時間といった風で、花祭りの曲がかかってもきょとんとした様子でした。色んなことがよく分っているようでも、いつもちゃんと反応が返ってくるとは限らないのがともちゃんです。いずれにしても、ともちゃんがすんなりと2組の一員になれたことが何よりでした。
今日は金曜日なので、チーム活動の日です。チームとは、高等部のクラスを障害の種類や程度の違うクラスを混ぜて、3つに分けたもので、運動会もここに小中学部が加わって、チーム対抗で行います。チーム活動は生徒の自主性を重んじた活動で、色々なことを生徒が決めて行きます。ともちゃんの2組は黄チームです。今日は司会の生徒が前に出て、チームの歌を決めました。それぞれのクラスから出された候補曲を検討していくのですが、「2組の人の意見も聞いてみましょう。」ということで、ともちゃんの好みも聞かれました。候補曲は「青春アミーゴ」、「手のひらに太陽を」、(忍たま乱太郎のエンディング曲)「桜援歌」の3曲です。
ともちゃんを抱っこして下さっている先生によると、「ともちゃんは青春アミーゴが好きみたいです。これを推薦している時に笑っていましたよ。」とのことでした。でも、ともちゃんのお母さんもお姉ちゃんも、もちろんお父さんも、ジャニーズはあまり聴かないので、ともちゃんには馴染みのある曲ではありません。むしろ、曲調の明るい「手のひらを太陽に」や、時々アニメを見ている忍たまの曲の方が好みかなあとお母さんは思っていました。結局、桜援歌を知らない人が多いので、今度実際に曲のテープを持ってくるというところで議論は終りました。
みんなはこの後、来週行われる保護者と共に行う「高等部のつどい」のゲームの練習をしていたそうですが、ともちゃんはミルクの注入の時間になったので、教室に戻りました。新しい教室でミルクの注入です。これから1年間は、この場所でミルクの注入をすることになります。ともちゃんが注入をしていると、昨年一緒に注入をしていたNちゃん先輩が先生に抱っこしてもらって、会いに来てくれました。注入が終ると、ともちゃんはタクシーを呼んで下校します。ともちゃんの体調に合わせた短時間の登校ですが、2年目の学校では友達も増えて、またさらに楽しい経験がたくさん待っていそうです。
 連休中は風邪をひいて、近所に一度しかお出かけすることができなかったともちゃん。「来週の土日は、一般の人は連休のお出かけ疲れで(家にいるから)道が空くやろ。その時にお出かけしよな。」と言われていました。しかし、夜、肌寒い気候のためか痰も多く、喘息も出てきているので、遠出は避けて今回も家の近くの散歩をしました。今回は、家の四方で唯一残っていた南方面に出かけてみました。
連休中は風邪をひいて、近所に一度しかお出かけすることができなかったともちゃん。「来週の土日は、一般の人は連休のお出かけ疲れで(家にいるから)道が空くやろ。その時にお出かけしよな。」と言われていました。しかし、夜、肌寒い気候のためか痰も多く、喘息も出てきているので、遠出は避けて今回も家の近くの散歩をしました。今回は、家の四方で唯一残っていた南方面に出かけてみました。
ともちゃんの家の南方面には私鉄の駅があるので、(ともちゃん以外の)家族はいつもよく通ります。しかし、駅前からの商店街が続いている道に出るまでの間、公園の横からお寺の前にかけて、車椅子には危険な複雑に傾いた坂道があります。その坂は車もよく通るので絶対に避けることにして、近くのスーパーまで行ってみます。昨夜、両親は登攀ルートを検討しました。往路はお母さんが担当し、西回りでアタック。復路はお父さんの担当で東回りルートをとります。細い道まで載っている地図も印字して、準備は万端です。
家族みんなで張切っていたのに、今朝は珍しく、一家全員が7時20分まで寝ているという朝寝坊でした。朝の準備に時間のかかるともちゃんは、早起きしてこそ、学校にもお出かけにも行けるのです。「こんなに朝寝坊して、お散歩に行く時間がとれるかなあ。」というお母さんのちょっと意地悪な質問に、「片道2時間かかって車で遠出することを考えたら、全然大丈夫やわ。」とお父さんが助け船を出してくれました。
お昼頃からお散歩に出発。暑くも寒くもなく、ちょうど良い散歩日和です。まずは大通りを東に向いながら、長い距離をかけてゆるやかな坂道を登ります。この道には広い平坦な歩道があって、車椅子にはありがたい道です。ここから南に折れるのですが、車が通る広い道は避けて、東西方向にはスーパーを少し通り過ぎた辺りで細い道に曲がりました。少し上り坂です。地図を見ながら、住宅地の中の狭い道をカクカクと行くと、鯉のぼりや神社の祭りののぼりに出くわしました。家の近くなのに、全く知らない町並でした。
「あの屋根はきっとスーパーやで。」と通りを抜けると大正解。ともちゃんはお買物を楽しみます。「レジの前に、キティちゃんの形のマグカップにお菓子が詰まったのを売ってたで。」と言うお姉ちゃん情報に従い、まずはキティちゃんマグカップをカゴに入れました。ともちゃんはお菓子は全く食べられませんが、こういう場合は中味のお菓子だけを家族に売って、ともちゃんはお小遣いを稼ぎます。キティちゃんの貯金箱が置いてあって、食べた人はそこにお金を入れることになっているのです。
店内を回っていると、通常の棚の外れに商品を積上げた島ができていて、そこには「あっ、キティのドロップ!」、「弁当箱もテッシュもあるで。」。お菓子から文房具、日用品までキティちゃんグッズの特設コーナが設けられていました。今日、ともちゃんがお散歩で来るということが知られていたかのような企画に感激して、キティちゃんのドロップもカゴに入れることにしました。もちろん、これも、中味は(酸っぱいアメが好きな)お父さんに売るのです。お母さんの買物にも少し付合って、今度は東回りで帰ります。
駅前から続く商店街の道路を横切って、公園の横を行きます。お父さんは地図もなしで、ともちゃんの知らない道を案内してくれます。私鉄の線路に当たる手前で北に曲がって、両脇に住宅の並ぶ狭い道を行くと、塀で囲まれたお屋敷や、絵画教室などがあって、ここも近いのに全く知らない町並でした。少し広い、まっすぐな坂道で傾斜を下り、道沿いの狭い川の横に出て、カクカクっと保育所の横を抜けると、大通りに戻ってきました。ほら、右側を見ると、ともちゃんも行ったことがあるドラッグストアでした。これで、ともちゃんはお家の近くは東西南北全て行ってみたことになりました。
 ともちゃんの家の前の畑も、いつの間にか耕され、水がはられて水田になりました。そして、水田には鷺の仲間の渡り鳥が今年もやって来ていて、タニシやカエルを食べています。今年は5月だというのに雨がよく降ります。どうやらそのせいで、ともちゃんは喘息の発作が出て、なかなか思うように登校できません。夜中に息苦しくなって抱っこしたり、痰が多く粘っこくなって、何度も吸引したりしています。けれど良い天気になると痰も切れて、吸引することもなく機嫌良く元気に過ごしている日もあります。
ともちゃんの家の前の畑も、いつの間にか耕され、水がはられて水田になりました。そして、水田には鷺の仲間の渡り鳥が今年もやって来ていて、タニシやカエルを食べています。今年は5月だというのに雨がよく降ります。どうやらそのせいで、ともちゃんは喘息の発作が出て、なかなか思うように登校できません。夜中に息苦しくなって抱っこしたり、痰が多く粘っこくなって、何度も吸引したりしています。けれど良い天気になると痰も切れて、吸引することもなく機嫌良く元気に過ごしている日もあります。
久しぶりにすっきりと晴れた今日、元気にしているともちゃんは植物園に出かけました。例年ならともちゃんのお出かけシーズンはもうとうに始まっていますが、今年はゆっくりと、まずは近場に短時間のお出かけからスタートします。京都府立植物園ではバラが咲き始めたとのことです。ちょうどともちゃんには負担にならない距離なので、昨年に続いて今年も出かけることにしました。今年はお姉ちゃんも一緒というところが、去年とは違います。疲れないように、車の中では「寝ときや」と言われたともちゃんですが、お姉ちゃんの声がすると嬉しくて仕方ありません。ニコニコしながら、声を出してたくさんお話ししていました。
植物園に着いた時には、ともちゃんはボーッと元気がありません。「そやから、寝ときって言うたのに。」、はしゃぎ過ぎて、今は休憩モードに入っているのでしょう。とは言っても、このまま車の中にいることもないので、とりあえずは車椅子に乗換えて、ミルクの注入をするレストランへ向かうことにしました。車外は暑いし、太陽の光がまぶしいし、車椅子のともちゃんはよけい目を細めて、しおれています。そこで、ともちゃんのキティちゃん日傘の登場です。今年初めて使う日傘ですが、ともちゃんが家で静養している間に、すっかり日傘の季節になっていました。
レストランはまだ空いていて、禁煙席の窓際に陣取りました。思えば、去年もここの席に座りました。ともちゃんは、お父さんに抱っこされ、窓を背にして座りました。ミルクを経管栄養剤用の袋(イルリガートル)に入れ、車椅子にセットされている点滴棒の上に吊し、イルリガートルに付いたチューブの先をともちゃんの鼻腔から胃まで通されているチューブに挿入して準備完了。ともちゃんは鼻のチューブからミルクを飲み始めました。でも、ともちゃんはお父さんの肩越しに見える後ろの窓の外が気になるようで、体を反らして見ています。
「これで、どうや。」、お父さんが90°向きを変えてくれました。これで、ともちゃんも窓の外の美しい花壇や鮮やかな木々、そしてついさっきまで写生をしていた人が残していった(どこへ行ったのかな?)スケッチブックやパレットまでが見えます。ともちゃんは、満足そうに景色を見ながら注入をしています。お腹も減っていたようで、ミルクを飲んでいるうちにともちゃんは元気を回復して、豊かな表情と目の輝きが戻ってきました。「ハハン」と笑顔も見せ、早くミルクを飲み終って活動開始するぞ、とはりきっています。
食事が終ると、レストランの下の1階にあるお土産屋さんに寄りました。近くのお出かけでもお土産を買う、思い立ったら着いてすぐでもお土産を買う、というのがともちゃん流です。去年は、ともちゃんがお姉ちゃんにお土産を買いましたが、今年はお姉ちゃんも一緒に選びました。お姉ちゃんとお揃いで買ったのは、魚の形をした色違いのお手玉。ともちゃんのは、頭とひれがピンク色で胴体が赤色、お姉ちゃんのは、頭とひれが赤色で胴体は黄色っぽい柄です。他にもともちゃんは、バラのストラップを買いました(去年はバラのキーホルダーを買いました)。バラ園のお散歩の記念です。
さて、ようやく目的のバラ園に向かいました。まだ、咲き始めで、去年のようにたくさんのバラが一度に咲いていることはありませんが、色々なバラが少しずつ咲いています。今年はバラの名前の名札を見ながら一本ずつ観賞しました。「嵐山」とか「高雄」とか京都の地名の名前のついたバラがたくさんあるので、お姉ちゃんもお母さんもびっくりでした。ともちゃんはお父さんに車椅子を押してもらって、バラ園の中をギャハギャハ笑いながら、楽しそうに巡っています。でも、美しいバラの花をバックに写真撮影しようと立止まると、笑顔も止めてしまいます。
形も色も違うたくさんの種類の中から、お姉ちゃんは「黒みがかった深紅のバラが一番ええわ。ともちゃんはどの花が好きや?」と話しかけています。「あのピンクの大きな花が似合うかな。」、ともちゃんは話しかけてもらうと笑顔を返してくれるのですが、そのうちにまた疲れて来て、反応が鈍くなって来ました。噴水の花壇を最後にして、お散歩もおしまい。無理せずに、疲れたらさっと引き上げるというのも、ともちゃん流です。車の中で水分補給をして帰路につきました。ともちゃんは帰りの車の中ではぐっすりと眠って、家に着く頃にはまた元気になっていました。今年もぼちぼちお出かけシーズンの開幕です。
ともちゃんは、虫さされなどかゆいところがあると、体をギュッと縮めて固ります。体のあちこちを調べると、左の肘にブツブツが出ていました。お姉ちゃんも「体調が悪くなると、肘にブツブツが出る」と言っていたことがあるので、お母さんは納得しました。ともちゃんの舌根沈下を防ぐためにあごの下(舌の付け根)を押えながら、お父さんにかゆみ止めの薬を塗ってもらいました。かゆみ止めが効けば、そのうちにともちゃんの緊張も治まるだろうと、お父さんもお母さんも最初は軽く考えていました。
ところが、ブツブツは左肘、右肘、左膝、右膝、背中と次々に現れて、ともちゃんは腕を縮め、首をすくめて、泣きそうな顔でか細い声をあげながら、力を入れて一生懸命呼吸をしています。酸素吸入を5リットルにして、首の位置を空気が通りやすいようにお母さんの腕でコントロールして、緊迫した時を過ごしました。蕁麻疹だけなら、かゆいだけで済みます。でも、ともちゃんは、食物アレルギーの発作で気道が腫れてチアノーゼが出たことがあるので、お母さんもお父さんも何事もなく治まることを祈りながら、いざという時には救急車を呼ぼうと心の準備をしていました。
肘や膝に現れた蕁麻疹はだんだん大きくなって繋がり、そのうちに皮膚の表面がちりめんのようにボコボコになって行きました。その間に、腕や太ももやすねにも蕁麻疹がどんどん現れてきます。食物アレルギーは、アレルギー反応が終ってしまえば、それで終りなのです。「もうちょっとやでー。ほら、ブツブツが繋がってきたからな。」と、ともちゃんを励ましながら、時計とブツブツを見比べていました。
酸素を5リットル投与していても、気道が腫れたのか、それに加えてともちゃんの過度の筋緊張が生じたためか、一時的には動脈血中の飽和酸素濃度が89%まで低下しました。でも、それも首の位置をコントロールしているうちに回復して、ほっとしました。蕁麻疹が現れて1時間30分位経つと、酸素5リットルで飽和酸素濃度は大体98%、心拍数が一分間に130~140回になりました。この頃、蕁麻疹は大きい物は残っていますが、多くは皮膚の表面がちりめんのようになってきていました。
その後は酸素を3.5リットルにしても心拍数は120台に下がり、発症から2時間位で、蕁麻疹はほとんど治りました。大事に至らなくて本当に良かったです。午後9時、いつもならもうとっくに眠っている時間なので、酸素を2リットルに下げて寝室に向かうと、ともちゃんはすぐに眠りにつきました。
さて、今回の食物アレルギーの原因は何だったのでしょう。今日、いつもの食事以外で食べたものはアイスクリームだけです。このアイスクリームは、原材料に卵や大豆由来成分などともちゃんのアレルゲンが入っていない物を探し求めたものです。今までに何度も食べているし、蕁麻疹が出たのは食べ終ってから1時間半ほど経ってからです。蕁麻疹が出る直前まで飲んでいたのは、いつものミルクです。調乳の時に何か混ざったのでしょうか。いつも通りの調乳で、思い当たることはありません。
アレルゲンについて、あれこれ考えるのですが、結論は出ていません。ただ、同じアレルギー体質のお父さんが「普段は何ともなくても、体調の悪い時にだけ発作が出ることもあるし、アイスクリームの製造ラインでは別の製品も作っているやろうから、何かが混入していたのかもしれへん。体調が悪かったので、それに反応したんかもしれん。」と言ったので、確かに一番考えられそうな気がしています。いずれにしても、しばらくはともちゃんは珍しい食べ物は控えることになり、お母さんは家族の食べ物が混入しないかをよりいっそう厳しくチェックすることになります。
高等部では1年生から実習があるのですが、1年生の実習時期は3月だったため、冬籠り中のともちゃんは不参加でした。その時は「2年生の実習は6月にあるから、その時に参加しよう。」と思っていました。ところが、今年は5月が梅雨のようで喘息が出て、ともちゃんの体調はすっきりしません。先週も実習の予定があったのですが、体調不良で行くことができませんでした。今日は3度目の実習予定日です。
昨日のともちゃんの体調から、「明日は参加できるかも、でも微妙。」とお母さんは今朝まで最終判断を延してきました。でも、今朝のともちゃんの期待に満ちた目の輝きを信じて「行ってみます。」と学校の先生に電話をかけました。昨日から「明日元気やったら、H園で実習やで。」と言うお母さんの話しかけや、お母さんが実習に行く用意をしている姿を雰囲気で感じ取って、ともちゃんは楽しいことがあると期待しているのでしょう。
家族のみんなはいつも不思議に思うのですが、ともちゃんは(行事などがあって)ここ一番という時に、まるでそれをちゃんと知っているかのように朝から張切っています。そういう場合は、体調が許す限り、ともちゃんの希望を叶えてあげるようにしています。また、経験的に、ともちゃんが目を輝かせている時は、意欲的に取組めるくらいに体調も良いという証であるように思われるのです。
10時にタクシーを呼んで、先生には9時45分に家に来て頂きました。3人でタクシーに乗ってH園に向かいます。いつも、ともちゃんと2人でタクシーに乗っているお母さんにとって、先生がいて下さると、ともちゃん一人を後部シートに寝転がせて車椅子を折りたたむということがなくて、嬉しいことです。今回は、ともちゃんは先生に抱っこしてもらって、タクシーに乗りました。
H園に着いてすぐ、お母さんが車椅子を降ろしている間に、先生に抱っこされたともちゃんは硬直の発作(よくあるてんかん発作)を起こしてしまいました。でも、そんな発作はもろともせず、「こんにちは。体験実習に来ました。」と玄関をくぐる時には、思いっきり張切った満面の笑顔を浮かべていました。「おお、張切っとるな、ともちゃん。体験実習に来るの楽しみにしていたな。」、お母さんは、初めての場所、初めて会う先輩達なのに、積極的にかかわろうとしているともちゃんに感心しました。
ともちゃんが一緒に参加させていただく、重症心身障害児のグループの部屋に入っていく時も、ニコニコと愛嬌を振りまいていました。けれど、先輩達が一人ずつともちゃんに自己紹介をしてくれる場面では、ちょっと恥ずかしい様子でおとなしくなってしまいました。握手をしてもらった時も、硬い表情で緊張していました。どうやら、ともちゃんは、自分から攻込んでアピールできる場面では張切ってはしゃいでいますが、相手の方からともちゃんに向って来ると、ちょっと引込み思案になってしまうようです。
それを証明するように、自己紹介の時に、車椅子に乗ったまま眠っている先輩がいて、指導員さんに「この人は寝たはります。」と紹介してもらうと、ともちゃんは大きな声でギャハハハと笑っていました。本当に子供らしい、面白いともちゃんです。ちょっと話はそれますが、お母さんがともちゃんを抱っこして携帯電話で話している時は、一緒ににアーアーと大きな声を出しているのに、それなら「しゃべってみ。」と電話機をともちゃんの耳と口に当てると、神妙な顔で黙ってしまうことがよくあります。今回もそれと似ているような感じがします。
床の上に特別に畳のスペースを作ってもらっていて、ともちゃんはそこで車椅子を降りて、先生に抱っこしてもらいます。ともちゃんの前では、先輩がリハビリの訓練をしてもらっています。ともちゃんは訓練の様子を見ながら、ゆったりと休憩し、ここの雰囲気に馴染んでいました。すると、「ちょうど今日、おしゃれクラブがあるんですよ。よかったら、参加しませんか。」と声をかけてもらいました。女の子が3人食堂に集って、なにやら楽しそうです。
ともちゃんも行ってみました。食堂のみんなの中に入っていく時には、ともちゃんはやはりとびきりの笑顔を振りまいています。みんなは髪の毛を巻いたり、お化粧をしたり、マニキュアを塗ったりときれいにしてもらって、おしゃれを楽しんでいます。ともちゃんもマニキュアを先生に塗ってもらいました。お母さんがH園の方と入園についての話をしている間に、左手は親指だけ赤色(これだけお母さんが塗りました)で、後は微妙に色違いのピンク色、右手は水色とカラフルに仕上げてもらっていました。これは是非お姉ちゃんに見せびらかして、自慢しないといけません。
ミルクの注入の時間になったので、また畳の上に戻って、先生に抱っこしてもらって注入しました。その間に登園してきた養護学校のN先輩のお姉ちゃんにも会いました。H園は授産施設も併せ持っているので、2階にある喫茶室では先輩達の作ったパンを販売しています。お母さんは、お姉ちゃんへのお土産に色々な種類のパンを買いました。ミルクの注入が終ると、ともちゃんのペースに合せて頂いた体験実習も終りで、家に帰ります。ともちゃんの卒業後は、H園で、今日のようにみんなと一緒にゆったりと活動させてあげたいと、お母さんは強く思いました。ともちゃんも、その表情から、きっとそう思っているに違いありません。