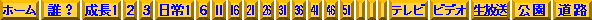ともちゃん
 の日常34
の日常34
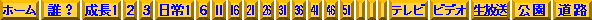
 の日常34
の日常34
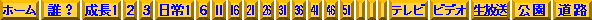
最初にタイトルの一覧があります。タイトルをクリックすると本文が読めます。
「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークをクリックするとそのタイトルに関する写真/動画/連組写真が見られます(「ビデオ」/「スライド」はファイルのダウンロードに1~2分かかります)。
本文の最初にも「写真」/「ビデオ」/「スライド」マークがありますが、タイトル一覧と同じ写真/動画/連組写真です。
 20日(火)
20日(火)
 25日(日)
25日(日)
「家族でも京都駅」
 16日(日)
16日(日)
 11日(金)
11日(金)
 13日(日)
13日(日)
「桂坂野鳥遊園」
 16日(水)
16日(水)
「杉津(すいづ)PA」
 27日(日)
27日(日)
「花空間けいはんな」
 3日(日)
3日(日)
 30日(土)
30日(土)
「コックさんの運動会」
 9日(月)
9日(月)
京都駅は十年程前に駅ビルが建替えられたので、エレベータが設置されたバリアフリーの構造になっています。中学部の時に修学旅行に出発した新大阪駅は新幹線開業以来の古い建物で、特別に荷物搬送用のエレベータを使わせて貰ってホームに上がりました。それを考えると、バリアフリーの思想が最近急速に広まったことを有難いと思います。ともちゃん達は京都駅で新幹線のホームに上がり、修学旅行で乗る新幹線を見学した後、駅に直結しているシティホテルのロビーにあるレストランで食事をして、またJRに乗って帰ります。
朝、今回も先生にともちゃんの家まで来て頂いて、お母さんと3人でタクシーに乗ってJRの最寄りの駅に向いました。乗込む電車の時間が決っているので、タクシーの乗降に思わぬ時間がかかったりして時間の読めないともちゃんは、乗遅れないように早めに家を出て、みんなの到着を待ちます。他の友達は、スクールバスとして借上げている大型タクシー2台に分乗して、学校から駅までやって来ました。
最寄りの駅も、ともちゃんが引越してくる少し前に建替えられたところなので、駅前ロータリーから改札の前まで上がるエレベーターがあります。小さなエレベータで車椅子は一台しか入れないので、順番にエレベータに乗ってホームの前に集合しました。ともちゃんは、学校の先生や友達と会うのは1ヶ月ぶりです。友達の気配を感じ、先生に声をかけてもらって、うれしくてニコニコしています。数日前、H園のおしゃれクラブで塗ってもらい、みんなに見せようと敢てそのままにしておいたマニキュアも見てもらいました。
最寄りの駅のホームで電車を待っている間もニコニコしていたともちゃんですが、反対側の線路を通過電車が通った時は、その迫力にびっくりして表情が凍りついていました。顔の平べったい白い特急列車は、関西空港からやってきた「はるか」です。次に別の列車が通過した時には、ちょっとびっくりした表情をした後で、声をかけてもらうと照れ隠しのようにギャハハハと笑っていました。その後は、列車の発着は全く平気で、出発の警笛や走り出す車輪の音を聞いて笑っていました。
7台の車椅子なので、3つのドアに分かれて予定していた快速電車に乗込みます。駅員さんにホームと列車の段差を解消するスロープをかけてもらって、ともちゃんも乗込みました。京都駅まで10分程度の列車の旅、ともちゃんはボーッとして、ちょっと休憩モードに入っていました。京都駅に着いたら、また小さいエレベータでゾロゾロと上がったり下がったりして、迷路を進むように新幹線のホームに出ました。途中で西口の改札を出た時には、ともちゃんは人混みに圧倒されて、緊張した顔つきをしていました。
オムツをしている子供達がほとんどの重症心身障害児クラスでは、外出時には軽量の折りたたみ式のベッドを持ち運んでいて、障害者用のトイレで広げて、順番にオムツ交換をします。新幹線コンコースでのトイレ休憩では、ともちゃんはおしっこをしていなかったので、トイレの近くの売店に寄ってキティちゃんを見つけました。京都キティだけではなく、関西一円のご当地キティがありましたが、今日は学校から来ているので買えません。「おうちでまた来た時に買おな」とお母さんに約束してもらいました。
新幹線のホームでは止っている新幹線を見て、ちょっと疲れてきたともちゃんは待合室で車椅子を降りて、先生に抱っこしてもらいました。止っている新幹線には、修学旅行の団体が乗込んでいきます。他の友達は待合室で水分補給をしますが、ともちゃんはミルクの注入をしに一足先にホテルに向かいました。来た経路を逆に戻りましたが、元気を回復したともちゃんは、たくさんの人が行き交う南北自由通路でも気後れすることなく笑顔を浮かべ、好奇心に輝く目で周りを見回していました。
ホテルに入るにはエスカレータに乗らなければなりません。インターホンで連絡をするとホテルの方が出てこられて、車椅子用にエスカレータの階段の2段分を平らにして、車椅子で乗込めるスペースを作るという操作を行って下さいました。最近のエスカレータではこのような機能を備えたものも見かけますが、実際にともちゃんが乗るのは初めてです。ともちゃんの車椅子は通常の座位がとれる人の物より長いので、このスペースに収まるか心配したのですが、ぴったりと収りました。
ホテル内に出店している有名な料亭の横の厚い絨毯を敷いた通路を通って、ロビーのレストランまでホテルの方に案内してもらいました。しーんと静かな高級感あふれる空間です。このホテルは駅の上に建っており、通路の一部がガラス張りになっていて、そこから右手には北陸線の0番線が、左手には改札口が見下ろせます。案内の方に「ここから駅が見えるんです。」と言われて、それまでもワクワクした気持ちを笑顔で表していたともちゃんは、嬉しそうに大きく口を開けて笑っていました。
ロビーの賑いを経て、レストランに到着しました。京都の表玄関のこういう華やかなところに、車椅子の子供達が団体でゾロゾロとやって来るのは愉快な気持ちがします。レストランは養護学校で予約していて、隅の一角を確保してもらっていました。空きテーブルを使って準備ができたので、落着いて注入することができました。ミルクを飲みながら、ともちゃんは先生に抱っこされて、休憩モードに入っていました。みんなが昼食のオムライスを食べにレストランにやってきた頃、ともちゃんの注入も終りました。ともちゃんの元気も回復して、先生とお母さんと3人で帰路につきました。
「ホテルのレストランで注入したって、お父さんやお姉ちゃんに自慢しよな。」と話しながら、絨毯の通路を戻りました。先生が「高級感があって静かやね。」と話しかけると、ともちゃんは超高級なお寿司屋さんの前で、ギャハハハハと声高らかに大笑い、なかなかの大物です。帰りのJRは車椅子で乗車することを連絡していなかったので、スロープをかけてもらうことなく、先生とお母さんが力を合せて一気に乗込み、一気にホームに降りました。ともちゃん大満足のお出かけでした。修学旅行までに、また家族でも京都駅に行ってみようと思います。
 学校から行った京都駅が気に入ったともちゃん、今日はお家からお父さんの運転する車で京都駅に行きました。修学旅行は京都駅に集合なので、ともちゃんはお父さんの車で京都駅まで行く予定にしています。京都市内を通るので、道路の混雑具合や所要時間を計るのも目的の一つでしたが、日曜の朝は道路が空いていて、一番の幹線道路を走っても30分ぐらいで着きました。
学校から行った京都駅が気に入ったともちゃん、今日はお家からお父さんの運転する車で京都駅に行きました。修学旅行は京都駅に集合なので、ともちゃんはお父さんの車で京都駅まで行く予定にしています。京都市内を通るので、道路の混雑具合や所要時間を計るのも目的の一つでしたが、日曜の朝は道路が空いていて、一番の幹線道路を走っても30分ぐらいで着きました。
もう一つの目的は、ともちゃんが自分の食べないお菓子を両親に売って貯めたお小遣で京都キティちゃんを買うことです。ともちゃんは、お姉ちゃんに買ってもらった、首から下げるキティちゃんの財布に全財産を持参しています。ともちゃんは、お菓子を売った小銭を貯金箱に入れていますが、両親は小銭が急に必要になった時にともちゃんの貯金箱から借用して、少し、いやかなり多めに返してくれるので、長年ため込んだお小遣は千円札何枚かになっているのです。
予め調べた通り、西第一駐車場の3階の車椅子用駐車スペースに車を止めました。この階からは隣の百貨店に渡り廊下で繋がっていて、百貨店のエレベータで階下に降りることができます。ともちゃんは、百貨店に入ると大喜びでニコニコしています。百貨店の明るい照明と、それにキラキラと映える商品のディスプレイが、楽しい雰囲気を煽ったのでしょうか。この百貨店では、何台もあるエレベータの中に車椅子専用エレベータがあって、(満員だと途中の階から車椅子がエレベータに乗込めないことがよくあるので)バリアフリーがここまで進んでいるんだと嬉しくなりました。
地下に降りて、そこから京都駅の地下街「ポルタ」のお土産屋さんに行きました。ここには、京都キティちゃんが小さい物から大きな人形までたくさん揃っています。お父さん、お母さんも一緒になって、ワイワイと色々何度も手にとって選びました。まずは、ぬいぐるみ。キティちゃん柄の着物を着たキティちゃんは、いつものリボンが凝った髪飾りになっています。さすが京都は観光地なので、タオルもたくさんの種類があります。その中から、おかっぱのキティちゃんと鞍馬山のカラス天狗キティを選びました。
ともちゃんをだしにして、両親も自分の好みを主張しています。学校の連絡帳を入れるビニールケースにつける着物キティキーホルダーを買って、買物はおしまい。たくさんの買物をして、ともちゃんの財布は空っぽになりました。なのに、お母さんは「ほら、京野菜キティの根付けもあるで。オネエの好きな九条ネギもあるで。ともちゃんは(食べたことがある)聖護院大根にする?」と、まだまだ買物に未練を残しています。お父さんの「今日はおしまい。また今度や。」の一言で、お土産屋さんを離れました。
今日のともちゃんの注入は、ポルタにあるトンカツ屋さんで行う予定です。でも、地下街のレストランの開店は11時なので、開店までにはまだ少し時間があります。実際の修学旅行では京都駅八条口の「祭り時計広場」に集合なので、祭り時計広場まで行ってみることにしました。京都駅の東側には、北側の地下街から南側の八条口まで地下通路が通っています。地下鉄の駅を横に見ながら、地下通路をどんどん進みました。八条口のエレベータで1階に上がると、そこは屋外でした。パラパラと弱い雨が降っていたので、目の前の駅ビルに走込みました。
こちらのレストラン街は、駅中ということでもう営業しています。でも、既にかなりのお客さんで混雑しているので、車椅子でも気楽に入れるよう、やはり開店直後のポルタのお店をねらうことにしました。物珍しげにキョロキョロしながら西に向うと、祭り時計広場はすぐに分りました。でも、広場の前は工事中で狭くなっていて、「ここに養護学校のみんなが集まれるのかぁ?」とお父さん。工事はいつまで続くのかわかりませんが、このままでは集合するのにちょっと狭過ぎます。
集合場所も確認できたので、今度は駐車場からここまで来る道を意識しながら、ポルタまで戻りました。新幹線中央口の前に出るエレベータで2階に上がり、そこからは学校で来た時にも使った上下差の短いエレベータに乗り、架線橋になっている南北自由通路に上がりました。自由通路で駅の北側に出て、駐車場に直結している百貨店に入って、車椅子専用エレベータで地下に下りました。もうここからは一度来たルートです。これで、駐車場から百貨店を通って時計広場まで、百貨店が開いている時間なら、車椅子でも問題なく行くことができます。
今日は雨が降ってきたので諦めたのですが、百貨店が閉っている時間帯のルート(駐車場から屋外に出て、駅の中央口のエレベータを使う)の方も、後日確認しに来ましょう。ポルタのトンカツ屋さんはちょうど開店直後に入ることができました。ともちゃんは、隅っこのゆったりした席で注入を済ませ、帰りには百貨店でお姉ちゃんへのお土産にケーキを買って帰りました。ともちゃんは、やはり百貨店のキラキラした照明がお気に入りらしく、応対してくれた店員さんの顔も思わずほころぶくらいに、ニコニコとした笑顔で買物をしていました。
 今年はまだ、すっきりと「夏モードだ絶好調!」とは言い難いともちゃんですが、ようやく登校できるようになってきました。夏休み前の3連休の中日の今日は、今年のお出かけシーズン開幕戦として、少し遠くまでお出かけしました。すっかり暑くなったので、海水浴客が通る京都縦貫や琵琶湖、北陸方面は混合っていることでしょう。ということで、お父さんが昨日一日かけて探した行先は、滋賀県にある道の駅「あいの土山」です。
今年はまだ、すっきりと「夏モードだ絶好調!」とは言い難いともちゃんですが、ようやく登校できるようになってきました。夏休み前の3連休の中日の今日は、今年のお出かけシーズン開幕戦として、少し遠くまでお出かけしました。すっかり暑くなったので、海水浴客が通る京都縦貫や琵琶湖、北陸方面は混合っていることでしょう。ということで、お父さんが昨日一日かけて探した行先は、滋賀県にある道の駅「あいの土山」です。
「あいの土山」は名神高速を栗東で降りて、国道1号線を1時間ほど走った、鈴鹿山脈の麓にあり、近畿地方で一番最初にできた道の駅です。国道1号線といえば昔の東海道ですから、第1号の道の駅というのも納得です。「道の駅」ファンのともちゃんですから、是非押さえておきたいお出かけ先です。
「名神の栗東までは、何度も通ったよう知った道やから、寝ときや。」と言われていましたが、久しぶりの遠出で張切っているともちゃんは、寝そうでいて、寝てくれません。朝、短いけいれん発作があったものの、ともちゃんは朝食をとても早く食べ終えたので(朝食の食べっぷりは、ともちゃんの体調の目安です)お出かけした両親は、ともちゃんの体調が気になっています。国道1号線に入っても、「知らん道やけど、いままで寝んかったから、寝とき。」、でも、神経はちょっとピリピリして寝られません。
1号線沿いには、郊外型のショッピングセンターやパチンコ店、カー用品店などが並んでいますが、そのすぐ後ろは田園風景で、少し先には山々が迫ってきています。奥行が薄くて横に長い映画のセットのような町並みが続いています。1号線の一筋南側に旧東海道があるのでしょうか、南側を指して「旧街道松並木」という標識を見かけました。水田がお茶畑に変って、目的地はもうすぐです。土山はお茶の産地です。お茶畑には畑の端々に扇風機の様なファンが取付けられていて、上から畑の中に風を送るようになっていたのが、お母さんにはちょっと不思議でした。後で調べて、防霜ファンと知りました。
標識に導かれて入った道の駅は小じんまりしたところでした。第1号なので、バリアフリーが導入されていないのではないかと心配しましたが、ちゃんと車椅子駐車スペースもありました。レストランに入ると、それまではボーッと元気がなかったともちゃんが、ギャハハハハと声を上げて嬉しそうに笑出しました。「わーい、遠くまで来たで。うれしいなー。」とはしゃいでいるようでしたが、その直後にまた短いけいれんの発作がありました。
今シーズン最初のお出かけなので、無理せず、あまり長居せずに、ミルクの注入を済ませたら帰ります。注入をしているレストランからは旧東海道の案内板と杉林の中に続く道が見えています。注入が終ったら、ここだけ見て帰りましょう。実際に案内板の前まで行ってみると、旧街道は住宅地の中に続くカラー舗装された道の方で、情緒溢れる杉林の中の道は東海道とは関係がありませんでした。見てみないと分からないものです。でも、こちらの方が風情があるので、杉林を背景にした写真も撮りました。
お土産を買うのも忘れてはいけません。レストランの隣のお土産コーナーもそんなに広くはありませんが、ご当地キティちゃんもあります。遠くまで来たつもりですが、ここはまだ滋賀県なので琵琶湖の鮎キティやなまずキティ、鳥人間キティなどになります。その中にたった一つ、三重限定の伊勢神宮の齋王キティがありました。「伊勢まではまだ3分の1くらいやで。ちょっと早すぎやなあ。」とお父さんは言いますが、伊勢にも琵琶湖にも半分ずつということで、なまずキティのタオルと齋王キティの根付けを買いました。
齋宮キティと言えば、お母さんは、帰りに「齋王行列」と書いてある看板を見つけました。どうやら、土山のある甲賀市は、齋王が京都から伊勢神宮に向う時に、輿に乗って行列して行った通り道のようです。土山の近くの垂水というところには、頓宮という斎王一行が宿泊するために造られた宿舎まであったのだそうです。それで、伊勢まではまだまだの道のりだけれど、齋王キティがいたことに納得がいきました。
ともちゃんの今シーズン開幕のお出かけは、このまま帰路につき、草津PAで水分補給をして早めに帰りました。ともちゃんの体調も順調に夏モードに入って、これからどんどん遠くにお出かけできるようになればいいですね。伊勢といえば、今日のお出かけの途中、1号線沿いに第二名神のための橋脚らしきものを見かけました。第二名神が繋がれば、ともちゃんも伊勢にまで足を伸ばすことができるでしょう。
 今年のともちゃんは、なかなかすっきりとした夏モードに入れなかったので、あまり登校できていません。訪問学級のおかげで充実した日々を送っていたものの、7月に入ったら、本格的に夏が来たら、今までの登校日数の遅れを取戻そうと思っていました。けれども、梅雨が7月末まで長引いたのと、ともちゃんの呼吸の状態がフガフガとしんどくなって夜の酸素量が増え、昼間でも酸素吸入が外せない状態が続くので、なかなか登校できませんでした。終業式も、先生に来てもらうことになりました。
今年のともちゃんは、なかなかすっきりとした夏モードに入れなかったので、あまり登校できていません。訪問学級のおかげで充実した日々を送っていたものの、7月に入ったら、本格的に夏が来たら、今までの登校日数の遅れを取戻そうと思っていました。けれども、梅雨が7月末まで長引いたのと、ともちゃんの呼吸の状態がフガフガとしんどくなって夜の酸素量が増え、昼間でも酸素吸入が外せない状態が続くので、なかなか登校できませんでした。終業式も、先生に来てもらうことになりました。
今年は、天候不順もあってともちゃんの体調が安定せず、1学期の出席日数は20日でした。このうち、実際に登校したのは、ぐんと少なくなって5日でした。それでも、修学旅行の事前学習である京都駅への校外学習、H園での体験実習、宿泊学習の翌日の学校での活動としてあった記念品製作(陶芸のお皿への模様付け)はしっかりと参加しました。雨の少なかった6月に、ともちゃんの体調が一番落着いていたように思います。今年は梅雨明けが遅かったので本格的な夏の到来が遅れたのですが、それなら、その分厳しい残暑で、なかなか秋にならなければいいなと願っています。そうすれば、ともちゃんの冬籠りの開始も遅くなり、2学期も長く登校できるかなと思うからです。
ともちゃんの「フガフガ」というのは、太りすぎの人が喉の脂肪が厚くなり、寝ている間に気道が塞がれて無呼吸状態を起こす、いわゆる睡眠時無呼吸症候群のような感じなのです。ともちゃんは元々扁桃腺が肥大しているのですが、それがさらに腫れているようで、気道を塞いでいるような音がしています。息がしにくいので、一生懸命呼吸しようとして舌根沈下を起こし、よけいに空気の通りが悪くなってフンガーフンガーという苦しそうな音を立てています。夜の眠りは浅くなって、色々向きを変えたり、首の位置をコントロールしたり、抱っこしたまま寝る時もあります。
「フガフガ」がどんどん強くなってきていると思っていたら、7月27日の夜にガタガタ震える悪寒の後、ともちゃんは39.4度の熱を出しました。翌日通院したところ、「喉にばい菌が付いている。」とのことで抗生剤の点滴をしてもらい、大事に至らずに熱は下がりました。熱が下がってからは、フガフガは少しマシになりました。このところの強い「フガフガ」は、やはり喉の腫れによるものによるものだったようです。
一日でともちゃんの熱が下がって、両親はホッとしました。というのも、お父さんが8月2日から4日間ですがアメリカに出張するからです。過去にも、お父さんが海外出張中にともちゃんが肺炎で入院したり、一番最近では、ともちゃんが経管栄養になって助かった入院の時に、お父さんは岡山の工場へ連日出張だったりしました。お父さんの仕事が忙しくて家にいない時に、ともちゃんの体調の危機が訪れるみたいで、両親は心配していました。
それからしばらくの間、ともちゃんは家で静かに過ごしました。再び熱がぶり返したりしないように、守りに徹した生活です。ともちゃんが家から一歩も出ない生活をしている間、お姉ちゃんは函館に旅行に出かけ、お姉ちゃんの帰る日に入違いにお父さんが海外出張に出かけてしまいました。お父さんが出張に出かけている間は、お祖母ちゃんが家事を手伝いに来てくれました。夏休み中の養護学校の訓練の予定もちょうどこの間に入って、学校のリハビリの先生と担任の先生も、ともちゃんの家を訪ねてくれました。色んな人が家に来てくれると、ともちゃんの気持ちもちょっと晴れやかになります。
留守番をしていたともちゃんは、お姉ちゃんとお父さんからたくさんのお土産をもらいました。お姉ちゃんは、北海道キティグッズをたくさん買ってきてくれました。お姉ちゃんは1学期にバイト三昧でしっかり稼いだので、この旅行の時は裕福だったのです。毬藻キティ、函館イカキティ、ラベンダーキティ、函館夜景キティ、イクラ丼キティのタオルや根付け、どんどん出てくるお土産にともちゃんもびっくり。極めつけは、毛むくじゃらの毬藻のぬいぐるみ。「おっ、毬藻やん。」と思っていると、パカンと割れて、中から毬藻の着ぐるみをかぶったキティちゃんが出てきました。
お土産の数ではお姉ちゃんには及びませんが、レア度ではお父さんも負けていません。先生がリハビリの訓練に来て下さった時、先生と「アメリカにもご当地キティちゃんがあるんやろか。」と話していたのですが、本当にサンフランシスコキティがありました。カニの絵が描かれた舵を操作するキティちゃんとゴールデンゲートブリッジ、それにケーブルカーが描かれたメモパッドです。それに、弾みを付けて手を離すと、チンチンと鐘を鳴らしながら走る赤いおもちゃのケーブルカー。お母さんとお揃いのサンフランシスコTシャツ(お姉ちゃんは同じ柄で色違い)もあります。Tシャツは、お母さんと二人で行った病院の定期受診に早速着て行きました。
たくさんのお土産も、家族が帰ってきて賑やかになるのもうれしいともちゃんですが、夏休みと言えば、やっぱり自分でお出かけして、お土産も自分で買いたいともちゃんです。待ちに待ったお父さんの夏休み初日の今日は、道の駅「和(なごみ)」に行きました。京都縦貫自動車道を終点まで行き、そこから国道27号線を走り、JR和知(わち)駅の近くにある道の駅です。養護学校で、N先輩がおうちからよく行く道の駅だと教えてもらったところです。和知町の和ですが、「なごみ」と言うのが和みキャラのともちゃんらしくていい感じです。
ともちゃんにはすっかりお馴染みの京都縦貫ですが、お姉ちゃんと一緒にドライブするのは初めてです。家族揃ってのお出かけに、ともちゃんはうれしくて寝ていられません。地道に降りてからは、ずんずん山の中に入っていきます。山陰線の鉄橋の下も通りました。途中で川沿いに出ましたが、川の流れる方向が車の進行方向と同じです。つまり、日本海に向って川が流れています。ということは、丹波山地の分水嶺を越えたのだということが分かって、感激です。
この由良川の畔に建つ道の駅「和」は、産直の野菜やこの地域の特産品、お菓子、お弁当類、お土産類、おもちゃが所狭しと一杯に積上げられた販売コーナーがあり、その奥にレストランがありました。レストランの開店までに時間があったので、ともちゃんは先にお土産を選びます。ご当地キティちゃんコーナーもあります。ここ丹波の黒豆キティ(黒豆キティは昨年道の駅「丹波マーケス」でも買いましたが、それより少し派手な黒豆付きの根付け)と、由良川ではなくて、なぜかレアな京都の保津川キティタオルがあったので、川つながりということでこれも買いました。帰りに買うつもりのお弁当や、野菜にも目をつけておきます。
レストランでは、ともちゃんはもちろんミルクの注入をしていますが、お父さんは鮎天丼を、お姉ちゃんは五穀丼を、お母さんは日替り定食を頼んで、お姉ちゃんとお母さんは半分づつ食べていました。「五穀丼におろしショウガが入っているわ。」とお姉ちゃんが生姜を話題にした時、ともちゃんは突然声を出して大笑い。そのタイミングの良さに家族はみんな感心しながら、一緒に大笑い。実はお父さんの土産話にこんな話があったのです。「アメリカのシアトルにあるシーフードレストランでTombo Tunaというのを頼んだら、なんと鰹のたたきが出てきてんで。ほんまもんの鰹のたたきやねんけど、それに載ってる生姜が、おろし生姜と違て、お寿司についてる紅生姜やってんで。」(大笑い)
 世間がお盆休みに入ってしまったので、道路の混雑を避けて、ともちゃんのお出かけは近場になります。今日の行先は、京都市内(といっても西京区のはずれの郊外)にある桂坂です。桂坂の「ふれあい会館」は、京都市社会福祉協議会が運営する保養研修センターで、6月に行われたともちゃんの養護学校の宿泊学習での宿泊先でした。宿泊学習の時は、ともちゃんは翌日養護学校に戻ってからの活動に少しだけ参加しただけで、みんなと一緒に宿泊はしていません。
世間がお盆休みに入ってしまったので、道路の混雑を避けて、ともちゃんのお出かけは近場になります。今日の行先は、京都市内(といっても西京区のはずれの郊外)にある桂坂です。桂坂の「ふれあい会館」は、京都市社会福祉協議会が運営する保養研修センターで、6月に行われたともちゃんの養護学校の宿泊学習での宿泊先でした。宿泊学習の時は、ともちゃんは翌日養護学校に戻ってからの活動に少しだけ参加しただけで、みんなと一緒に宿泊はしていません。
ふれあい会館は、レストランで昼食だけでもとれるということなので、一度どんなところか行ってみたいと思っていました。ともちゃんの家から30分程度で、幹線道路を通らずに行くことができます。近くには野鳥遊園があって、散歩もできます。それに、この辺り一帯は京都市西部の養護学校、障害者の授産施設や更生施設が集っている地域なので、車椅子にもやさしい街並みのような気がします。
レストランは11時から営業なので、先に野鳥遊園に向いました。それでも時間があるので、西行きが渋滞している国道9号線を少し東に進んだ後、北側の急な坂道を上ります。少し遠回りをして、京都大学桂キャンパスを抜けて桂坂に行くのです。桂坂は山間の新しい住宅地で、傾斜地に大きな住宅がゆったりと並んで建っています。とてもここが京都だとは思えません。どんどん奥に入って行って、野鳥遊園に着きました。「鳥の声は聞こえんと、蝉の声ばっかりやなあ。」と言いながら、小さな園内を散歩しました。
野鳥遊園は広大な山を後ろに控えた池の周りを木の塀で囲んで、塀に開けたのぞき穴から、池にやって来る鳥の様子をこっそりと見られるようになっています。残念ながら、ともちゃんの車椅子の高さにぴったりののぞき穴はありませんでした。家族が覗いてみましたが、特に鳥の姿は見当りませんでした。「残念やなあ。鳥はおらんで。」と言いながら、見学用の建物の中に入ってみると、池に面したガラス張りの窓の前に備えられた椅子には何人もの人が腰を下ろして、池の方を見ていました。双眼鏡も用意されています。
ともちゃんの車椅子も窓際に付けて双眼鏡を覗かせてあげようとしましたが、鎖の長さが足りません。それを見ていた案内の人(野鳥の会のボランティアさん?)が、「今まで青鷺がいたんやけどね。これやったら、大きいから双眼鏡がなくても良く見えるのに。青鷺は背中が灰色っぽい(青っぽい)鷺、鶴みたいな形をした鳥で、鷺の中でも大きいんですよ。」と教えて下さいました。あっ、それそれ、ともちゃんの家の前の田圃に6月頃に来ている鳥(鷺)の中にも、背中の青い大きいものがいます。
青鷺はいなくても、池から上がって木陰で休むカモや、飛交うツバメを見ることができました。ツバメは池に急降下して、アメンボを捕っているということでした。ともちゃんの家の近くにも色々な名前を知らない鳥がやってきますが、ここに来れば大概同じ鳥が来ていて、鳥の名前を教えてもらえそうな気がします。ともちゃんは、野鳥遊園を出て、再び車に乗込み、さらに住宅地の奥の方に進みました。
住宅地の突当り、障害者の通所施設と養護学校がある一角に、ふれあい会館もありました。レストランは少し前に開いたところですが、車椅子に乗った障害児を含む家族が先客で席についていました。とはいえ、お盆の今日は会館自体もひっそりとしていて、レストランも空いていて静かでした。ともちゃんがミルクの注入を済ませて帰ろうとした頃に来られたもう一組の家族連れも、車椅子のお年寄りがおられて、みんな車椅子やなあと愉快な気持ちになりました。もちろん、レストランもバリアフリーです。
会館の売店には、京都市内の障害者の授産施設や作業所で作られた手芸、工芸品がショーケースの中に並べられて売られていました。ちょっと興味のある商品があったのですが、声をかけようとしたフロント係の人がずっと電話応対中だったので、今回は諦めました。近いところなので、また今度来たときに見てみようと思います。ふれあい会館の隣はふれあい広場という芝生の公園で、暑い日差しの中、日傘を差して車椅子で散歩しました。
帰りには、9号線の渋滞はびっくりするほど長く繋がっていました。今度は西行きも東行きも渋滞していましたが、帰りは9号線には入らず横切るだけです。9号線へ出る北向きの道、ともちゃんの進行方向とは反対車線も大渋滞、洛西ニュータウンの中まで渋滞しています。ともちゃんが以前に通っていた病院を越えて、ショッピングセンター「ラクセーヌ」の辺りまで混雑していました。お盆の日曜日ですから、高速道路の渋滞は承知の上、9号線の渋滞も予想はしていましたが、普通の道まで混んでいるとはびっくりです。でもお父さんの選んだ道は時間と方向で渋滞なし、混雑していないお出かけコース選びの先見の明に感謝です。
 今日はスイス、いや、福井県のすいづ(杉津と書きます)パーキングエリアまでお出かけしました。今年の夏一番の遠出です。今年は夏休みになっても、まだ痰の吸引が多く、酸素の吸入カニューラが外せないともちゃんですが、それ以外は機嫌も良く、お出かけを楽しみにしています。携帯用の酸素ボンベと吸引器を持って、無理しないようにしてお出かけしています。
今日はスイス、いや、福井県のすいづ(杉津と書きます)パーキングエリアまでお出かけしました。今年の夏一番の遠出です。今年は夏休みになっても、まだ痰の吸引が多く、酸素の吸入カニューラが外せないともちゃんですが、それ以外は機嫌も良く、お出かけを楽しみにしています。携帯用の酸素ボンベと吸引器を持って、無理しないようにしてお出かけしています。
京都に引越してからは、すっかりお馴染みになった北陸自動車道を(ともちゃんが無理なく帰ってこられる程度に)行けるところまで行くとすると、だいたい杉津PAくらいまでかなあと、お父さんは以前から考えていました。杉津PAは敦賀から福井へ向かう山中にあって、標高180mから敦賀湾が一望できるというパーキングエリアです。敦賀湾を眺めながらミルクの注入ができたら、きっと楽しいでしょう。
朝食を早く食べ終えて張切って出発したともちゃんですが、出発してすぐに痰がゼロゼロと沸いてきました。ともちゃんを抱っこしているお母さんには、隣の席で朝ご飯代りのスナック菓子を食べているお姉ちゃんのたてるボリボリという音にも負けないような喘鳴を感じます。路肩に車を止め、痰の吸引をして、また出発しました。朝から頑張ったともちゃんは、すっきりして、くたっと眠ってしまいました。
今日、杉津PAに行くことにしたのは、台風が近づいていて、明日以降天気が悪くなりそうだということと、お盆なのに昨日から道路が空いているようだということからです。確かに道路は空いていて、見慣れた近江米の田園地帯をどんどん走って行きます。家を出る時には曇っていた空も、トンネルを抜けるごとに微妙に変って、夏休みのギラギラした太陽が照りつけています。機嫌良く目覚めたともちゃんは、「ハーン、ハーン」とにこやかにお話ししてくれました。
「敦賀は去年来たやろ。覚えてるか。お魚市場に行ったやろ。」、敦賀を過ぎれば、杉津までもう少しです。「ここから山道」の表示がありましたが、JRの路線なら北陸トンネルに入る辺りですから、それも納得です。短いトンネルを抜けて、杉津PAに着きました。予想していたよりも小さなところでした。まずは「夕日のアトリエ」という真西に敦賀湾を望む展望台で、記念写真を撮りました。本来なら、湾の向こうに敦賀半島が見えるはずですが、あいにくその辺りは煙っています。モデルのともちゃんは日差しのまぶしさに目を細めていました。
次々に撮影にやって来る観光客に突出されるように、狭い展望台を後にして軽食コーナーに入りました。PAの建物自体も小さいので、軽食コーナーのスペースも狭く、車椅子では入りにくいところだったのですが、一番奥にうまく入り込みました。カウンター席が主でテーブルも椅子も高く、椅子は固定なのでともちゃんを抱っこしてミルクを注入するには不向きだったのですが、一番奥にある窓の下に設えられたテーブルは位置も低くて幸いでした。隅っこのイスが動かせたので、そこに車椅子を置き、車椅子に備付けの点滴棒にイルリガートルを釣下げました。
ここは店一番の席でもあって、敦賀湾を眼前に見下ろせます。ゆっくりと目を凝らして見ていると、ぼんやりと敦賀半島のシルエットが現れました。半島の先端付近、向かって右端に白い建物らしきものが光っていますが、これが原子力発電所でしょう。原発事故に恐怖心を抱くお母さんは、対岸に原発が見える光景に、ともちゃんがここにいる間はもちろん、未来永劫事故のないことを心の中で祈りました。窓の直下には、山の斜面中腹を走る道路が見えています。「あれは、北陸道の上り車線やねんで。この辺では上り下りで道路が分かれている上に、クロスして右側通行になってるねんで。」とお父さんがミニ知識を披露します。
お母さんが、自分が食べ終ったうどんの鉢を返却しに行って戻ってくると、お父さんとお姉ちゃんが騒いでいます。蜂が一匹、テーブルの上に止っています。「早よ、ともちゃん逃げぇや。」、「こんな狭いところで、(蜂に気づかれないようにドタバタせずに)移動するのは無理や。こいつ、弱ってるねん。動かへん。一発必中やで。」、強力なプレッシャーを背負ってのお母さんの一撃に、蜂はあえなく昇天。本当に弱っていたようです。よく見ると、他にも小さな虫が窓ガラスに張付いています。やはり、山の中のPAです。
注入の後は、杉津のお土産を探します。キティコーナーには、福井の恐竜キティと越前竹人形キティの根付けがあったのでともちゃんに見せると、竹人形キティを見せた時にギャハハハと大笑い。お父さんは「大魔神みたいやなあ。」と言うのですが、ともちゃんはおかっぱ頭の竹人形キティちゃんを気に入ったようです。遠くまで来たので気持ちが大きくなって、他にも福井キティちゃんのタオルやボールペンセットも買いました。
車に乗込み、次の今庄インターチェンジを目指します。敦賀トンネルを越え、スーパー戦隊ものに出てくる秘密要塞のような面構えの今庄トンネルを抜けると、今庄ICがあります。今庄まで来るともう福井平野で、敦賀と福井の間の峠を越えたことになります。今庄ICで北陸道を降り、地道をちょっと走ってすぐにUターン。反対向きに再び北陸道に乗り、家へ帰ります。上りの北陸道は、さっきの軽食コーナーで山の下に見えていた道です。上りにも杉津PAがあるので、そこで水分補給をしました。
標識の誘導に従って、一般の駐車場を右横に見て坂道を上り、車椅子駐車スペースに入りました。ここは山の斜面に建っているので、建物は正面にある駐車場より一段高いところにあり、駐車場から建物へは階段を上って行くような構造になっていました。車椅子駐車スペースからなら、平面を移動するだけで建物に入れます。上りは山の低いところを通っているので、絶景ポイントが売物ではありません。その代りという訳ではないのでしょうが、思いがけず「レア・メロンパンキティちゃん」という張紙がしてありました。
これに反応しない訳はありません。上りの杉津PAでは、ここともう一カ所のSA限定のメロンパンを販売していて、それと一緒にメロンパンキティちゃんも販売しているということでした。メロン色のドレスを着て、マスクメロンの網目柄のリボンをしたキティちゃんが、メロンパンを持っています。これも、是非ゲットしたいお土産です。福井キティちゃんをたくさん買ったともちゃんですが、メロンパンキティちゃんも連れて帰ることにしました。メロンパンの方は最後の1個が残っていて、お姉ちゃんが買って、車の中で「おいしいわ。」とムシャムシャ食べていました。
 今日は珍しく朝寝坊をしたともちゃんですが、マイペースで朝の予定を済ませてから、「花空間けいはんな」に出かけました。本来なら、夏休み最後の日曜日は「子供は夏休みの宿題で忙しいから、お出かけはしない。だから、道路は空いている。」というお父さんの夏休み「道」理論に従って、遠くまでドライブする予定でした。昨晩眠りの浅かったともちゃんが寝坊をしてしまったので、急遽行先を変更したのです。ともちゃんのお出かけ先は、常に遠近色々ととり揃えてあります。
今日は珍しく朝寝坊をしたともちゃんですが、マイペースで朝の予定を済ませてから、「花空間けいはんな」に出かけました。本来なら、夏休み最後の日曜日は「子供は夏休みの宿題で忙しいから、お出かけはしない。だから、道路は空いている。」というお父さんの夏休み「道」理論に従って、遠くまでドライブする予定でした。昨晩眠りの浅かったともちゃんが寝坊をしてしまったので、急遽行先を変更したのです。ともちゃんのお出かけ先は、常に遠近色々ととり揃えてあります。
「花空間けいはんな」は京奈和自動車道の精華下狛インターチェンジを降りて、すぐの所にあります。ともちゃんの家からは、京滋バイパスから第二京阪道路に入り、第二京阪の終点から一般道を経由して京奈和道に乗継ぐのですが、いずれの道も空いていて、楽々走ることができました。この道中の間ともちゃんは眠っていて、機嫌良く起きてきた頃、目的地に着きました。駐車場に止めてある車は少なくて、真夏の園内が空いていることが分かります。
「車椅子駐車スペースのマークは無いなあ。」、「これだけ空いてたら、どこでもともちゃん降りられるわ。入口の近くも空いてるし。」、車を降りて花時計の横のスロープを上がり、入場ゲートに向かいました。花時計の形が京都府のマークになっているところが印象的です。お母さんは、ここは最近できたところかと思っていましたが、旧名称の京都フラワーセンターの頃から数えると今年で開園20周年だということでした。ゲートの横を見ると、ゲートと同じ高さの一段高くなった駐車列のゲートに一番近いところに、車椅子駐車スペースがありました。次からはここを利用しましょう。
まずは、カフェテリアでともちゃんのミルクの注入をします。店内は、思っていたよりもお客さんがたくさんいました。みんな灼熱の園内散策で暑くなって、ここに逃込んだのだと思うと納得です。注入をしながら、眩しい園内の様子を観察していると、職員と思われる方から熱心に植物の育て方を学んでいるグループもあります。カフェテリアなので店の外にもテーブルが出ていて、季候の良い時ならそこで注入をしてもいいなと思いました。
日傘を差して、蝉の賑やかな園内を散歩しました。ここは、農業公園とも植物園ともちょっと違います。京都にある種苗メーカーやガーデニング用品メーカーなどが、それぞれに花壇や庭の展示を行っていて、ガーデニング用のミニチュアの家や塀、白雪姫と7人の小人の人形を並べた展示もあります。「まあ、いうたら、ガーデニング公園やなあ。」とお父さんは話していましたが、帰って「花空間けいはんな」のパンフレットを見ると、英語でちゃんと「gardening space in kyoto」と添書きされていました。
もちろん植物も充実しています。ともちゃんは温室を少し覗いて、涼しげな水生花園を見に行きました。外気温が十分高いので、温室は全開放になっていました。入口のハイビスカスに惹かれて中に入ってみたものの、暑がりのお父さんが「温室は冬にしよ。」とともちゃんの車椅子を押して、さっさと出て行ってしまいました。蓮池は花も豪華でしたが、それ以上に、夏の終りの今の時期だからこそ見られる、花が散った後の蜂の巣の形をした実の部分がたくさん葉っぱの中から突き出ていて、迫力がありました。睡蓮池では、色とりどりの睡蓮がきれいです。
ともちゃんは、水辺よりも風の吹く木陰がお気に入りで、ホッとした笑顔を見せてくれます。炎天下の散歩の必需品、車椅子の枕の下に敷く保冷剤を忘れてきました。「展望台」という案内板が出ていますが、こちらもまた涼しくなってから登ってみることにしましょう。ともちゃん一家も、再びカフェテリアに逃込みました。ここで、ともちゃんの水分補給をしました。お父さんもコーラ、お母さんもソフトクリームで喉を潤しました。生返ったところで、帰路に着きます。
来る時は京奈和道に一駅(ひとIC?)だけ乗ったのですが、「帰りは、地道で第二京阪の終点まで行ってみるわ。」とお父さん。迷わずに順調に帰れたものの、竹林の中の曲りくねった山道を通る羽目になりました。お父さんは、ともちゃんが山道で車酔いしたことを思出して心配したのですが、適度に疲れて満足したともちゃんは、ぐっすり眠っていて大丈夫でした。
 9月になって新学期が始りました。お父さんの会社の夏休みが終り、お姉ちゃんの大学が一足早く始り、またお母さんと2人で家で1週間過ごしていたともちゃんは、自分だけお留守番をしていることが気に入りませんでした。今年は訪問学級で始業式を迎えることになって、先生が家を訪ねて下さると、ともちゃんはニコニコして「私にも学校があったんや。先生が来てくれはって、うれしいわ!」という気持ちを表していました。そして、2学期の予定として修学旅行の話が出ると、また目を輝かせていました。
9月になって新学期が始りました。お父さんの会社の夏休みが終り、お姉ちゃんの大学が一足早く始り、またお母さんと2人で家で1週間過ごしていたともちゃんは、自分だけお留守番をしていることが気に入りませんでした。今年は訪問学級で始業式を迎えることになって、先生が家を訪ねて下さると、ともちゃんはニコニコして「私にも学校があったんや。先生が来てくれはって、うれしいわ!」という気持ちを表していました。そして、2学期の予定として修学旅行の話が出ると、また目を輝かせていました。
学校が始っても、お出かけもします。今年はともちゃんの夏モード突入が遅かったので、夏休みが終っても、まだまだ遊び足りません。いまだに酸素カニューラが外せませんが、それでもフガフガという呼吸は大分落着いて、お出かけを楽しんでいます。今日も、今夏のお出かけ最長距離の記録更新を目指します。先日は北陸自動車道の最長距離「杉津SA」まで行ったのですが、今度は名神高速の一宮ジャンクションから、ともちゃんが初めて通る東海北陸自動車道に入って「長良川SA」まで行ってみます。
先週から、今日のお出かけを約束していたので、ともちゃんは朝から絶好調で張切っています。おかげで、9時前に出発することができました。ともちゃんは、車に乗ってしまうと一安心とばかりに、ウトウトし始めました。ともちゃんにとっては残暑大歓迎なのですが、窓の外は空が高く、高速道路に降注ぐ日差しが明るくて、やはり季節は秋に移りつつあることを示しています。そのうち、ともちゃんはにこやかに起きて来ました。お父さんとお母さんが、道路沿いの建物や、隣を走る高速バスの行先など、勝手にとりとめのない話をしていると、そこにともちゃんも寄ってきて、お話していました。
名神高速の米原までは近江米の田園風景が続き、米原からは山岳地帯に入ります。それが、一宮ジャンクションに近付くと、高速道路から人家や工場の屋根が密集して見えるようになり、もうすぐ名古屋であることが分りました。でも、ここからは名神を外れて、東海北陸自動車道に入ります。ともちゃんも、両親も初めて通る道です。景色に注目していると、木曽川の堤防にタワーが出現、その先には観覧車も見えてきました。道路は再び市街地を離れて、山岳地帯に向かいます。
長良川SAの車椅子駐車スペースは1つしかないのですが、その1つが埋まっていたので、近くの通常スペースに車を止めました。区画の幅が狭く、隣の車との隙間が狭いので、後部ドアから降した車椅子を車の横に付けて、ともちゃんを乗せて前に抜け出るのは大変でした。途中で、隣の車の人たちが乗込みに来たので待ってもらうことになり、あせりました。ともちゃんが建物前の歩道に上がった時に車椅子スペースの車が出ていったので、お父さんがその後に車を入れに行って、帰りは楽に乗込むことができました。
でも、それで良しという訳ではありません。ともちゃんとお出かけしていると、同じように車椅子でお出かけしている人をよく見かるようになりました。特に最近は、車椅子のお年寄りの姿が増えてきたと思います。車椅子でも、普通に気軽に誰でもお出かけを楽しめる社会になることを望んでいるのですが、それにしては、SAやPAの車椅子駐車スペースが少ないと感じます。複数あるところもあるのですが、まれです。今回、ともちゃんが長良川SAにいた1時間足らずの間にも、ともちゃんを含めて4人の車椅子の人を見かけました。誰もが危険なく昇降できるようになって欲しいものです。
SAの建物に入ると、ともちゃんのワクワク感は高まって満面の笑顔です。レストランは朝から営業していますが、この時間はまだ空いていて、ゆったりと座れました。座席に着いても、ともちゃんはキョロキョロと周りを見回して「ここは初めて来たところやな。」とニッコリしていました。ミルクの注入をしている間、お腹が空いている両親は「奥美濃古地鶏の鉄板焼き」と「奥美濃古地鶏の唐揚げ」の定食をそれぞれ注文しました。そのどちらにも、小さなうどんの鉢が付いていたのですが、麺は讃岐うどん風でも、汁は鰹だしの効いた醤油濃い色で鰹の削り節が入っており、それはまさに名古屋のきしめんの出汁の味です。お父さんは名古屋食文化圏に来ていることを懐かしく思いました。
ミルクの注入が済んだら、次はお土産を選びます。SAはPAと違って建物が広く、余裕があるので、車椅子でもゆっくりと選べるのがうれしいところです。お土産コーナーに入ってすぐに飛騨の「さるぼぼ」キティグッズが目に入りました。「さるぼぼ」は飛騨地方の方言でサルの赤ちゃんのことで、縁起のよいお守りとされています。この棚には、キティの「さるぼぼ」だけではなくて、色々な(本物の)「さるぼぼ」も、ドラえもんの「さるぼぼ」もありました。ともちゃんと家族は喜々として、さるぼぼキティのマスコットを選びました。
ところが、その棚の裏に回って、ちょっと早まってしまったことに気が付きました。こちら側がご当地キティのメインコーナーで、岐阜や愛知のキティちゃんがたくさんいました。なんと長良川の鵜飼いキティのぬいぐるみもいます。このSAの裏には鵜飼いで有名な長良川が流れています。せっかく長良川SAまで来たのですから、これは是非押さえておかなければなりません。すでに、さるぼぼキティを買ってもらったともちゃんですが、鵜飼いキティのぬいぐるみも買ってもらいました。ともちゃんには、甘い両親です。
買物をした後、せっかく長良川SAまで来たので、なんとか長良川が見えないかなあと思い、辺りを散策しましたが、残念ながら川は見えませんでした。その代りに、SAの建物の横の公園に鵜飼いの模様を付けた細長い円筒状のオブジェがあったので、記念写真を撮りました。
帰りの水分補給は、来る時に見かけた観覧車のあるハイウェイオアシスに繋がっている川島PAで行いました。しかし、上りの川島PAは見事に何もない、自販機もなくてトイレしかないパーキングエリアでした。車の中で水分補給をしたともちゃんは、お母さんと車の中で待っていたのですが、お父さんはコーラの自販機を求めて、ハイウェイオアシスの方まで探検に行きました。観覧車は下り車線のPAの側にあります。
20分ぐらいしてコーラを買って戻ってきたお父さんは、「10分ほど、標識の誘導に従って歩いていくと、水族館と観覧車のあるハイウェイオアシスにたどり着くんやけど、そこまでは自販機も何にもないねん。ハイウェイオアシスのお土産屋さんを覗こうかと思ったけど、水族館のある建物に立ち入るだけでも入場料が必要なねん。それで、帰ってきてん。」、暑い中をお父さんが歩いている間、ともちゃんは涼しい車の中でお母さんの抱っこで眠っていたので、ニコニコと機嫌良くお父さんの話を聞いていました。
 今日はともちゃんの運動会です。ともちゃんは朝から張切っています。1学期は天候不順で思ったほどは登校できなかったのですが、それを取戻すかのように9月は毎週登校できて、たくさん練習もしました。その上、お父さん、お母さんだけではなく、アルバイトで忙しいお姉ちゃんも(アルバイトの)早朝勤、夜間勤の合間に見に来てくれます。お姉ちゃんがともちゃんの学校行事に来てくれるのは、7年ぶりくらいです。そんな訳で、ともちゃんが張切らない訳はありません。ともちゃんは開会式も含めると、何と4種目に出場しました。
今日はともちゃんの運動会です。ともちゃんは朝から張切っています。1学期は天候不順で思ったほどは登校できなかったのですが、それを取戻すかのように9月は毎週登校できて、たくさん練習もしました。その上、お父さん、お母さんだけではなく、アルバイトで忙しいお姉ちゃんも(アルバイトの)早朝勤、夜間勤の合間に見に来てくれます。お姉ちゃんがともちゃんの学校行事に来てくれるのは、7年ぶりくらいです。そんな訳で、ともちゃんが張切らない訳はありません。ともちゃんは開会式も含めると、何と4種目に出場しました。
朝のお粥を1時間で食べ終えたともちゃんは、ちょうどバイトから帰ってきたお姉ちゃんも一緒にお父さんの車に乗せて、学校に向いました。学校では、まだ開会式が始っていません。ともちゃんも運動場に向いました。生徒達がゆるゆると集合している背景が竹林というのは、やはりのどかでゆったりとした開放感が溢れています。ともちゃんは、校長先生のお話の間も、生徒会の人達が開会式を進行している間も、ずっと大きな口を開けて、嬉しそうにギャハギャハ笑っていました。みんながたくさん集ってザワザワしている雰囲気が楽しいのでしょう。
あまり大笑いしているともちゃんに、先生も家族も、ここで疲れてしまわないかとちょっと心配でした。去年は高等部の競技2種目だけに出場しましたが、今年は高等部の競技は昼休み直前まであるので、それまで疲れないで元気でいて欲しいのです。開会式が終って、黄色チーム(今年も、赤、青、黄色の3チーム対抗、ともちゃんの高等部2組は黄色チームです)のテントに戻ったともちゃんは、次の「全校玉入れ」までの少しの時間、車椅子を降りて先生に抱っこしてもらいました。少しでも、疲れないようにとの配慮からです。
玉入れが始るので、ともちゃんは意気揚々とした表情でテントから出ていきました。養護学校には、ともちゃんのように自分で玉を握ることもできない重症心身障害児から、勝ちたいと意欲満々で元気に体を動かすことのできる生徒まで、色々な障害児が在学しています。それで、玉入れの的も、通常の竹竿の先のカゴ(実はこれも一工夫されていて、カゴの上に厚紙で出来た巨大な漏斗が配されていて、より入れやすくなっています)とは別に、ともちゃん達車椅子に乗っている生徒用のコーナーが用意されています。
運動場の上に、ちょうど大きなビニールプールのような形で、段ボールの囲いが作られています。ともちゃんは、黄色チームのみんなと一緒に、囲いの前に陣取りました。スタートの笛の音にちょっとびくっとしたともちゃんですが、心逸る音楽が流れる中、先生に玉を持たせてもらって、囲いの中に玉を落としていました。その後の高等部の種目「今日のメニューは・・・コックさんとネズミ」と「2人でドン」は昼休み前にあるので、玉入の後しばらく間があります。この間を利用して、教室に戻ってゆっくりと水分補給を行いました。
「今日のメニューは・・・コックさんとネズミ」は重複重度の子供達が学ぶ高等部1組と2組の演技種目で、ストーリー仕立てになっています。コックさん達が食材を持寄って、大きな鍋で何やら作っています。そこへネズミが現れて、コックさんを追いかけ回します。コックさんが逃げてしまった後、ネズミは鍋の中から食材を引張り出してしまいました。「これは大変」と食材を取戻したいコックさんとネズミが食材の引張り合いっこ。その時、猫の声がしてネズミが逃げて、コックさんは料理を完成することができました。出来上がったのはカレー、ネズミ達も呼んでみんなで一緒に踊りました。
このストーリーの中で、子供達はそれぞれにできることを披露したり、車椅子での追いかけっこ、引張り合いっこやダンスを楽しんだりします。ともちゃんの役はコックさん。車椅子の上から着られるコックさんの白い衣装を着て、赤いスカーフをして、ピンク色のバンダナを被っています。ともちゃんコックさんの持つ食材はいつも食べているジャガイモ。大きなジャガイモを膝の上に置いて、車椅子に乗って友達と並んで出番を待っているともちゃんは、ずっとニコニコ、ニコニコとご機嫌で、運動会に出場しているのが嬉しい様子です。
NHKの「今日の料理」の音楽に乗って演技が始りました。食材を持って鍋の周りに集って来たコックさん達は順番に紹介してもらって、得意な方法で食材を鍋に入れていきます。ニンジンを手に持って鍋まで歩いて入れに行ったAちゃん、得意の左手でトマトを押して鍋に入れたKyちゃん。3番目はともちゃんの番。先生がジャガイモを持ち上げてアピールすると、それに答えるように大笑い。その後、先生がジャガイモを切るために(ともちゃんはそのリズミカルな音を聞いて楽しみます)ともちゃんの膝からジャガイモを持上げるとまた大笑い。トントントンという音をキョロキョロしながら聞いてニヤリ。先生と一緒に鍋に入れに行って、先生が鍋に入れるとまたまた大笑いでした。
顔をしっかり上げて、先生と一緒に包丁を持って肉をトントンしていたKzちゃん。ルーを持ったまま鍋に入れようかしばらく迷っていたYちゃん。全部の食材が鍋に入ったところでネズミ達の登場です。コックさん達が逃出した後、ネズミ達は順番に野菜を引張り出しました。コックさん再び登場。ともちゃんは左足をピンと突張って、笑顔で張切っています。引張り合いっこの相手はNちゃん。野菜に見立てた風船をいくつも取付けた紐の両端に輪を付けてもらって、その輪を持って引張ります。ともちゃんは目を輝かせて、楽しそうに引張っていました。
猫の声でネズミ達が退散した後は、食材を鍋に戻して鍋をかき混ぜる先生の声に合せて、鍋の周りを車椅子で回りました。料理ができて、ネズミ達も呼びました。出来上がった今日のメニューはカレー。お祝いに「かき混ぜよう」の歌に合わせて、みんなで踊りました。今まで張切ってきたともちゃんは、ここではちょっと力を抜いて、穏やかな表情で踊りの輪に加っていました。とても楽しんで、たっぷりと興奮したので、満足したようでした。
午前中最後の競技、「2人でドン」は高等部のチーム対抗の種目です。赤、青、黄色、それぞれのチームの色にちなんだシンボルをチーム活動の時間にみんなで決めたのですが、「2人でドン」ではそのシンボルの張りぼてを2人で協力して運びます。今年のシンボルは、赤がダルマ、青が(リロ&スティッチの)スティッチ、そしてともちゃんの黄色チームはともちゃんの好きな夏の花、ひまわりです。「2人でドン」は2部構成になっていて、重症心身障害児が参加する「シンボル飛ばし」(競争ではありません)と、色々な形でシンボルをリレーする「ザルとモッコと輪つなぎ」(段々と激しい競争になっていきます)で構成されています。
「シンボル飛ばし」では、車椅子の生徒の膝にシンボルを乗せてペアを組む生徒が車椅子を押してシンボルを「飛ばし器」のところまで運びます。シーソーのような形の飛ばし器の端にシンボルを置き、もう一方の端を二人で勢いよく押してシンボルを飛ばし、次の走者にキャッチしてもらいます。ともちゃんのペアは偶然にも誕生日が近いKさん。練習の時から、Kさんはともちゃんにたくさん声をかけてくれました。ともちゃんペアには、担任の先生、看護士さん、日傘を差掛けて下さる先生と、あと3人も一緒で、「ともちゃんペア御一行様」という感じでゾロゾロと行きます。
競争ではないので、ゆっくりと進みます。3チーム同時にスタートするのですが、段ボールで作られた「別世界のトンネル」も、飛ばし器も1つしかないので、順番に使います。ともちゃんは一番最後に別世界のトンネルを潜りました。出口には紫色のテープのフサフサが下がっているのですが、それに触れたからか、明るくなったからか、ともちゃんはにっこりしました。いよいよシンボル飛ばし、「よいしょっ」と押して、ポコーンと飛ぶかと思いきや、しゃもじでご飯をすくって茶碗に盛る時のような具合で、じんわりパカンと真下に落しました。でも、次の走者がうまくキャッチしてくれました。練習の時はうまく飛んでいましたが、こういうこともママあります。
神妙な顔つきでシンボル飛ばしをしていたともちゃんですが、出番が終って引上げてきた時に、待ちかまえていたお姉ちゃんに「上手に飛ばしたなー。頑張ったなー。」と声をかけてもらって、パッと笑顔になっていました。ともちゃんは、このあとのシンボルリレー「ザルとモッコと輪つなぎ」(シンボルをザルに乗せて引張る、モッコに乗せて2人で運ぶ、シンボルに2つの輪をつないで2人でそれぞれに輪を持って走る)を見ずに、教室でみんなの昼食より一足早く、ミルクの注入をしました。最後まで見ていたお父さんによると、残念なことに黄色チームは2位でした。そのうち、友達もみんな教室に戻ってきて昼食が始りました。今日の運動会、ともちゃんは午前中一杯ずっと参加して、大活躍でした。ミルクが終れば家に帰って、ゆっくりと休むことにしましょう。
 ともちゃんは、元気で楽しく修学旅行に行ってくることができました。運動会に参加して以来の9日間、修学旅行に備えて家で体調を整えていた甲斐がありました。ともちゃんも大いに旅行を満喫し、満足そうにしています。
ともちゃんは、元気で楽しく修学旅行に行ってくることができました。運動会に参加して以来の9日間、修学旅行に備えて家で体調を整えていた甲斐がありました。ともちゃんも大いに旅行を満喫し、満足そうにしています。
ともちゃんは家では酸素濃縮器を使っていて、夜の呼吸管理が大変になるので、日帰りの修学旅行を計画していただきました。みんなと一緒に京都駅から山陽新幹線に乗り、みんなは小倉駅まで行きますが、ともちゃんは広島駅で下車します。広島駅の構内でお土産を買って、再び新幹線に乗って午後3時過ぎには京都駅に戻るという、ともちゃんに無理のない行程です。中学の時の修学旅行も日帰りで、新大阪駅から岡山駅まで行きました。それが、今度はさらに東西に行程が伸びて、ともちゃんのお出かけ記録の更新です。
ともちゃんは、修学旅行に行くことをとても楽しみにしていました。訪問学級で先生が修学旅行の話をすると、敏感に反応して笑顔が出ます。家でも修学旅行の話題が出ると決って嬉しそうにします。お父さんは、ともちゃんが本当に「修学旅行」という言葉に反応しているのかどうかを試そうと、感情を込めない低い声で「修学旅行」とともちゃんにささやいてみましたが、ともちゃんは知らん顔でした。みんなが期待を込めて「修学旅行」と言うことが、ともちゃんにもワクワクした気持ちを起こさせるのでしょう。
張切っているともちゃんは朝食を早く食べて、おしゃれな服に着替えました。昨日、自分の服を買いに行ったお姉ちゃんが、出かける前に「ともちゃん、修学旅行に着ていく服あるんか?」と聞きました。「いつもの服着て行くんやんな。」お母さんがともちゃんの同意を求めるように代って答えると、「オネエがかいらしい服買うてきたるわ。」とのこと。本当に、レースやスパンコールが可愛らしいちょっとくすんだピンク色のキャミソールを買ってきてくれました。いつもの濃いピンク色のズボンと白いハイネックに合せるとぴったりで、ぐんとおしゃれになりました。その上に、これもいつものキティちゃんのワッペンの付いたピンクのパーカーを羽織りました。
用意も手早く済せて、予定時間よりも少し早めに家を出ました。お父さんの車で、集合場所である京都駅まで送ってもらいます。お父さんには見送ってもらって、お母さんはともちゃんの修学旅行に同行します。ともちゃんは以前に京都駅まで下見に来たことがあるのですが、その時は駅の正面西側にある百貨店に直結した駐車場に車を止めました。今日は、下見の時とは違う八条口の駐車場(最長1時間しか止められず、車の出入りがとても多い)に車を止めます。先生に集合場所に近い八条口の駐車場のことを教えていただいたので、先週の日曜日の同時刻に、お父さんが実際に走ってみて、所要時間と駐車場の様子を見てきていました。
先週お父さんが走った時よりも道路は空いていて、ともちゃんは集合場所の祭り時計広場に一番に着きました。朝の張切りの反動で、車の中ではボーッとしていたともちゃんですが、先生に見つけてもらって声をかけてもらうと、大喜びで笑顔が出ていました。集合場所で待っていると、友達が次々にやって来まます。修学旅行では班分けがされていて、日帰りで参加するともちゃんもパンダ班の一員です。パンダ班の班長さんは運動会の「2人でドン」でペアを組んだKさんです。Kさんがパンダ班の班旗を見せに来てくれて、ともちゃんは笑顔で答えていました。
ともちゃんの修学旅行御一行の団体(生徒は総勢24名)には車椅子の子供が6人います。そのため、車椅子の子供達がホームへ上がるのには、ホーム直通の荷物用の大きなエレベータを利用しました。それでも、何回かに分かれて上がります。駅員さんに導かれてスタッフ用の通路を通り、お父さんに見送られて、ともちゃんはエレベータに乗込みました。ホームに上がるとみんなが待っていました。何台かの新幹線を見送って、ともちゃん達の乗る新幹線のぞみ号が来ました。車椅子固定スペースのある11号車に席を取っています。11号車に隣接する多目的個室も予め予約しています。いくつかの入口に分かれて、限られた時間内に乗込みました。
ともちゃんが席に着くと、すぐにお母さんと看護師さんはミルクの注入の用意を始めました。広島までの1時間45分の間に、ミルクの注入を余裕を持って済ませなくてはなりません。ともちゃんは、先生に抱っこしてもらって、友達の気配を感じながらミルクの注入を始めました。窓の外を眺めていると、トンネルが多いことに気が付きます。団体で確保している多目的個室は交代で使っています。それで、さっきまで個室にいた友達が、ともちゃんの隣の車椅子スペースに車椅子を止めて、そこでゆっくりしたりしています。ザワザワする車中が修学旅行の楽しさです。ミルクを飲み終ったらパンダ班の人達が来てくれて、一緒に写真を撮ったりもしました。
のぞみ号で広島駅まではあっという間でした。楽しい時間だったので、余計に短く感じたのでしょう。「こんな調子ならみんなと一緒に小倉駅まででも行けそうなのにね。」と今は名残惜しく思うのですが、帰路や帰ってからのことを考えると、無理は禁物です。みんなの前であいさつをして、一足先に個室で昼食を食べ始めているKyさんにもさよならをして、広島駅で降りました。広島駅の駅員さんに車椅子を押してもらってホームを行きながら、停車している新幹線の横を車中のみんなに手を振って通り過ぎたのですが、列車が動き出すとまたみんなに手を振って見送りました。
帰りの新幹線の発車時刻までの1時間10分の間に、広島駅の構内のお土産屋さんで修学旅行のお土産を買って、「広島までやって来たぞ!」という気分を満喫します。ともちゃんは、家族でのお出かけの時も、お出かけ先でのお土産買いを大きな目的にしていて、お土産を買うことも大好きです。余裕を持ってホームに上がりたいので、40分位の間に集中して買物をします。駅員さんに案内してもらって、改札口まで来ました。先生の現地下見の結果、駅構内の改札を出てすぐのところに大きなお土産屋さんがあって、広島キティちゃんもたくさんいたとのこと、そこを目指しました。
ともちゃんは、お母さんが背負っているリュックからキティちゃんの顔の形をしたサイフを出してもらって、長い紐で首から下げました。そこには、お父さんに貰った修学旅行の決められたお小遣1万円が入っています。みんなは4日間で1万円を使いますが、ともちゃんはたった1時間で1万円を使うという豪遊ぶりです。お土産屋さんの明るいディスプレイに、ともちゃんは目を爛々と輝かせて、気分を高まらせています。ありました、ありました。お母さんが、紅葉のかぶり物をしてシャモジを持った広島キティちゃんのぬいぐるみを見つけて、「ほら、こんなんあったで。」と目の前にかざすと、もう嬉しくてたまりません。ギャハハハハと大笑いしていました。
よく見ると、もう一種類広島キティちゃんがいました。牡蛎の殻の中で眠る広島牡蛎キティちゃんです。「こんなんもあるわ。どっちがええ?」とお母さんはともちゃんに聞きますが、ともちゃんはキャッキャと喜んでいて、何を尋ねても満面の笑顔を返してくれます。この笑顔は何物にも代え難く、お母さんはぬいぐるみを2つとも買うことにしました。他にも、「キティちゃんのタオルも買わんとあかんし。学校の連絡ノートを入れるケースにつける根付けも買うやろ。」、「お姉ちゃんやお父さんにもお土産買おな。食べ物がええかな。パックに入ったレトルトの広島焼、これがええやん。広島焼風味のじゃがりこもええで。オネエ、じゃがりこ好きやし。」
ともちゃん(とお母さん)はどんどんお土産を買ってレジの前に積上げると、お勘定は締めて1万数百円。お父さんに貰った1万円は、おつりを貰うこともなく、一瞬にして無くなってしまいました。ともちゃんの首に下げた財布は空っぽになりましたが、代りに車椅子の押し手には、もうこれ以上は掛けられないくらい、たくさんのお土産の袋が掛かっています。先生と一緒に、クラスの友達や修学旅行に行けなかった友達にもお土産を買いました。その後、ともちゃんが看護師さんや先生と待っている間に、お母さんはお姉ちゃんとお父さんに広島駅の駅弁を買いました。
上りのホームに案内してもらうために迎えに来て下さったのは、降車時に手伝っていただいた駅員さんでした。降車時に、ともちゃんの修学旅行のスケジュールを話していたので、「(ともちゃんが広島に着いてから帰るまでは)すぐですなあ。」と笑っておられましたが、全くその通りです。すぐに帰るのがもったいないくらい遠く まで来たときほど、惜しげもなくさっと帰ってしまうのが(体力がなく、無理をしないがモットーの)ともちゃんらしいところです。
帰りの新幹線では、多目的個室を指定席として確保していただきました。行きはみんなでワイワイと行きましたが、帰りはゆっくりと休養しながら帰ります。個室の椅子は、座面を引出すとペタンと背もたれから座面に掛けて平らにすることができて、ベッドのようにその上でごろんと横になることもできます。ともちゃんは、いつも学校や家でしているように、座面の上にあぐらをかいた先生やお母さんに抱っこしてもらいました。京都に着くまでの間、水分補給をしたり、ボーッとして興奮した神経を休めたりして過ごしました。
午後3時7分、ともちゃんの乗ったのぞみ26号は無事に京都駅に到着して、ともちゃんの修学旅行も終りました。何ヶ月も前から、いや去年から、心の準備や体調管理に始って周到な計画をしていただき、物理的にも慎重に準備をしてきたのに、いざ行ってみると、あっという間でした。けれども、念入りな計画と下準備があったからこそ、何事もなく行ってこられたのです。先生や看護師さんを始め、関係して下さった全ての方々に感謝です。本当によい(ともちゃんにとって最後の)修学旅行でした。京都駅で先生とお父さんに出迎えてもらったともちゃんは、お父さんの車に乗ってからも(帰りの新幹線で休養したこともあって、元気を回復して)嬉しそうにしていました。大満足の旅行だったのでしょう。